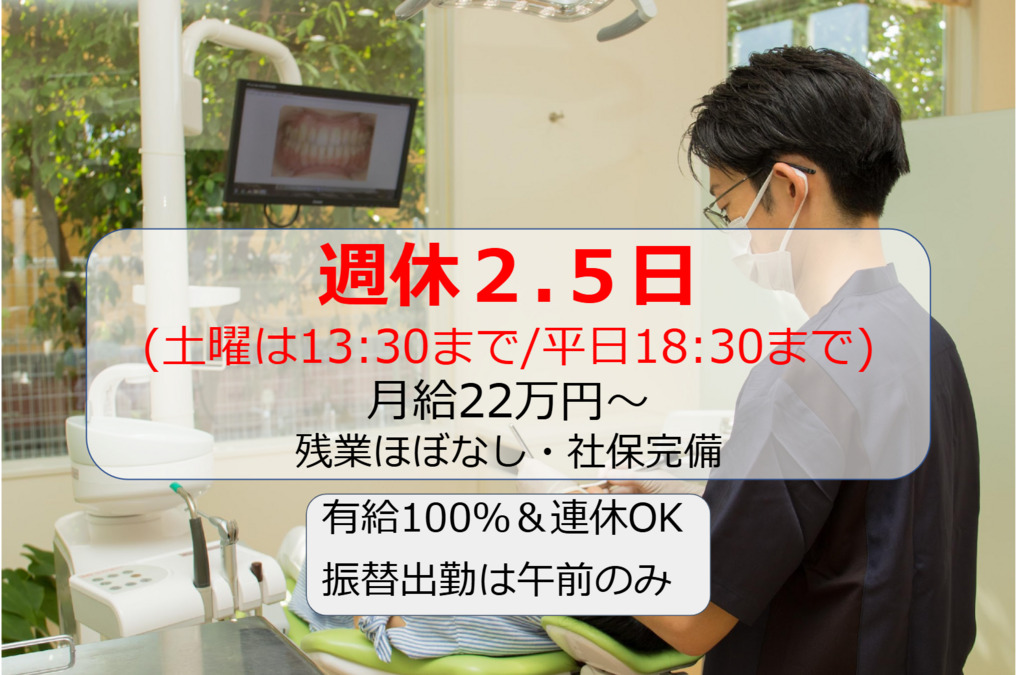目次
育児休業法は1992年に施行されて以来、対象者の拡大や給付金の引き上げなど改善が重ねられてきました。厚生労働省が2024年に公表した「令和6年雇用均等基本調査」によると、女性の育休取得率は1996年に49.1%だったのに対し、2024年には86.6%にまで上昇しています。
ところが医療・福祉の現場では、経営層や職場に制度への理解があっても、育休取得に際して苦しい思いをする人がいるのも現実です。
医療・福祉分野における育休制度の現状と課題を、経済学の観点から育休を研究する専門家と、医療現場で葛藤を感じてきた看護師2人とともに考えます。
制度があっても運用が追いつかない

慶應義塾大学商学部卒業。その後、ウィスコンシン大学マディソン校で経済学博士号を取得。マクマスター大学助教授・准教授、東京大学大学院経済学研究科准教授を経て、2019年より現職。
現場レベルで産休・育休制度を使いづらいとなると、国によるさらなる働きかけが必要に感じる人もいるかもしれません。ところが、労働経済学を専門とする山口教授は次のように話します。
「日本の育休制度は取得可能期間、給付金の支給率ともに高く世界トップレベルです。行政としてできることはある程度進んでいるといえます。
ただ、本来は取れるべき権利ではあるものの、理由をつけて押し戻されてしまったり、取得できても非協力的に感じたりする職場があるという声はいまだ多く耳にします」

当事者が直面した課題
産休・育休制度が整っている一方で、職場環境によって育休の取りやすさにばらつきも見られます。
看護師のMさんは自身の経験から「職場の理解を得るのが難しかった」と話します。

一方、限られた人員でも育休を取得できたケースもあります。

小規模事業所が多い分野ならではの課題
医療・福祉分野の従事者が育休を取りづらいと感じる背景の一つには、事業所の規模が関係している可能性があります。
まず、育休制度に関する全産業の調査結果を見ていきます。厚生労働省が2025年に公表したデータによると、育休制度を規定している事業所の割合は、規模が大きくなるにつれて高くなる傾向が見られます。

次に医療・福祉分野に目を向けてみます。統計局の「経済センサス(2021年)」によると、医療・福祉業界では19人以下の小規模事業所が全体の約80%を占めていることがわかりました。
この点について山口教授は次のように話します。
「代替要員の確保や業務分担が困難などの理由から、小規模である点は産業問わず不利といわざるをえません。ただ、日本は他国に類を見ないスピードで少子高齢化が進んでいますので、制度が整っていないことで、人が集まりづらくなる悪循環を招きかねません」
「お互いさま」を精神論で終わらせないために
小規模や抜けにくいという構造的な課題もある医療・福祉分野では、「お互いさま」の組織づくりが大切と山口教授は話します。
「個人の善意や自己犠牲によらない体制づくりが必要です。そのためには、特定の人への業務依存度をなくす、同業の医療機関や福祉施設と普段から連携を図ることが有効です。
加えて、女性だけでなく男性の育休取得の推進も欠かせません。国がおこなった調査によると男性育休によって、従業員の満足度や職場風土、ワークエンゲージメントの向上があることが立証されています」

育休取得は「経営にマイナスにならない」
男性育休が職場風土の改善に大きく影響したように、育休取得は経営にとってマイナスにならないと山口教授は指摘します。
「デンマークの中小企業4万社を対象とした研究では、育休取得前後の売上・利益を比較したところ、ほとんど変化が見られませんでした。この研究は、従業員30人以下を対象にしているため、日本の医療・福祉事業所の規模感に比較的近いと言えます。
また、2019年に私がおこなった研究でも、育休取得は復職後の定着率を高めるという結果が出ています。同研究では、一度離職した人が再び正社員として再就職する際の心理的・物理的なハードルは、育休から復職する場合より極めて高いという推計結果でした*1。
育休を1年程度取得させることは、経営側にとっては『貴重な人材の流出』という最大の損失を食い止め、従業員にとっては『スムーズな復職』を支える仕組みではないでしょうか」
どちらか一方にならない社会へ
育休制度への理解度や利用しやすさは、職場間でも大きく異なります。働き方が多様化したいま、運用に際しても難しさを感じる事業所も少なくありません。
ライフステージの変化は予想が難しいものです。だからこそ、想定外の変化が起きたとき、ライフとキャリアのどちらも諦めなくてよい柔軟な社会の構築が期待されます。
ジョブメドレーで求人を見る