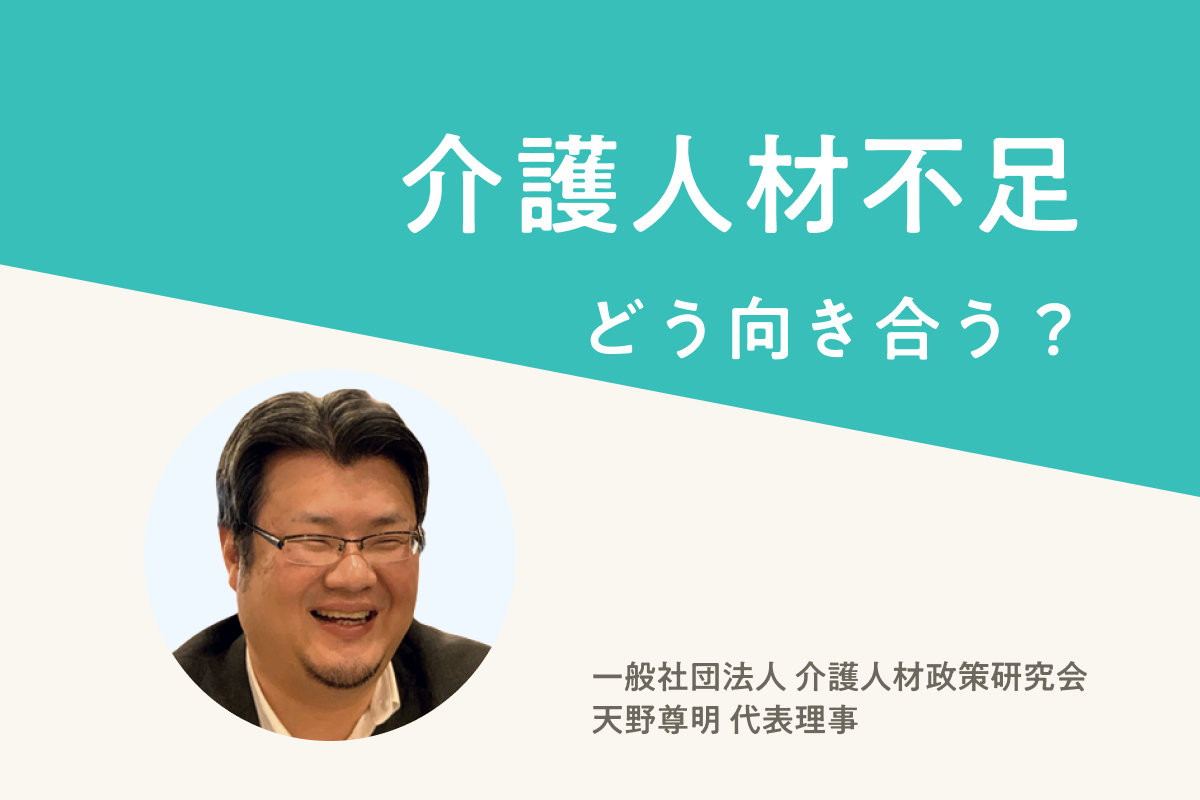長寿化が進み、介護を必要とする人が増える一方で、介護職の需要も高まっています。しかし、賃金や労働環境、離職率の高さなど、介護業界はさまざまな課題を抱えています。なかでも、介護職の人材不足は地域によらず深刻な問題です。
2024年に厚生労働省がおこなった調査によると、介護業界の有効求人倍率は4.08倍と、全産業平均の1.14倍と大きく差がある状況です。さらに、今後生産人口の減少が続くことから、2026年度には現状より約25万人多い約240万人、2040年度には現状より57万人ほど多い約272万人の介護職が必要になると予測されています。
人手不足が避けられない時代に、国や自治体、働き手には何が求められるのでしょうか。介護人材に特化したセミナーや政策提言をおこなう介護人材政策研究会の天野代表理事に、現場の課題や具体策について伺いました。
話を聞いた人

一般社団法人介護人材政策研究会 代表理事 天野 尊明さん
徳島大学卒業後、同県にある社会福祉法人に入職。その後、参議院議員秘書を経て、全国老人福祉施設協議会に出向し、2013年から2019年まで事務局長を務める。2019年に一般社団法人介護人材政策研究会を設立。
人材不足に“業界全体”で向き合うために

──2013年から2019年まで全国老人福祉施設協議会の事務局長を務めたのちに、介護人材に特化した法人を立ち上げた理由を教えてください。
参議院議員秘書や全国老人福祉施設協議会で働いていた10数年の間、全国の介護事業者や介護従事者の方々と話す機会をたくさんいただきました。また、事務局長をしていたころは介護報酬大幅削減の時期とも重なったことで、厚生労働省や政治分野の方々と関わる機会が多く、制度がどのように作られていくのかを学びました。
これらの経験から、業界全体で人手不足が共通課題であることは明確なのに、施設や職種の垣根を超えてこの問題に向き合う団体がないと感じていたんです。
当時、国がおこなっていたのは毒にも薬にもならない「介護の魅力発信」ばかりでした。魅力を伝えることは重要ですが、それだけでは人は集まりません。そこで協議会を退職後、「優れた職場に、優れた人材を。」というミッションを掲げ研究会の設立に至りました。
現場と政策の架け橋へ
──介護人材政策研究会ではどのような活動をおこなっていますか?
主に3つの柱があります。勉強会・情報共有・政策提言です。
勉強会では、事業所や法人の理事長や代表などの経営層を対象に、研究者や先進的な取り組みをしている事業所の代表を講師に招き、介護人材の確保と育成、定着をどう進めていくかなどをテーマに開催しています。
情報共有では、政策の最新動向を会員と共有したり、経営に関するトレンドを分析してレポートにまとめ配信しています。また政策提言では、現場の声をもとに国に制度改善や予算に反映してもらうための要望をおこなっています。
──なるほど。実際に、政策に反映された事例はありますか?
長崎県西海市での連携事業が挙げられます。人口の4割以上が高齢者という地域で、事業所単独では人材確保や運営維持が難しい状況でした。そこで、私たちは事業所同士が連携し、人材募集や経営支援、ノウハウの提供などをおこなう現地の取り組みに参画しました。
この取り組みをふまえ、厚生労働省の「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会で、地域の介護資源を有効に活用するための提言をおこなったところ、次年度の予算案や今後に向けた政策に反映されました。
──地方の人材不足はすでに深刻な状況なのでしょうか?
そうですね。都市部も事業所数が多く競争が激しいという意味では厳しいですが、地方の人口減少地域では、人材面だけでなく社会資源全般がすでに不足している状況です。そのため、エリア内にいくつかの介護事業所しかなく、利用者にとっても、サービスを提供する事業者にとっても選択肢が非常に限られているような地域もあります。
利用者が減少している地域では、運営が立ちいかず閉鎖せざるを得ないケースもあります。それでも、利用者の少ないデイサービスが訪問介護も兼ねるなど、制度を柔軟に運用して、地域に介護資源を1つでも残すことが大切だと思っています。
人材不足に向けてそれぞれができること
──介護業界における人材不足は今後も続く予想ですが、事業所にはどのような姿勢が求められますか?
事業所には、うまくいっている事業所の取り組みの過程や、新しい制度ができた背景まで含めて知ろうとする姿勢が求められます。
いまやネットであらゆる情報が得られますが、それは一部であり最大公約数のようなものです。つまり、表面的な結果だけを知っても実際の改善にはつながりにくいのです。成功事例や新制度が生まれるまでの課題、議論、試行錯誤といったプロセスを知ることこそが現場の改善に役立ちます。
たとえば、2024年度の介護報酬改定で新設された「生産性向上推進体制加算」は、業務の効率化を目的としたICTの導入などを後押しする制度です。生産年齢人口はすでに減少の局面に入っているので、いずれは導入しなければならないことは明らかです。ここを理解せず、コストが見合わないからといってこの加算を敬遠する事業所もみられます。そうではなく、「国が推奨している“いつかはやらなければならないこと”に、お金がついてくる」という理解が大切です。
介護業界は介護報酬が公定価格で決まるため、制度や経営を十分に理解していなくてもある程度は運営できてしまう特殊な側面があります。だからこそ、結果だけでなくその背景や意義にも目を向け、積極的に生きた情報を取り入れる姿勢が、優れた職場づくりや人材確保の鍵になると考えています。
──では、業界全体としてどのような取り組みが必要ですか?
まず、産業に関わらず人口動態の影響は受けると前置きさせてください。いわゆる2040年問題では、現在の人口の15%に当たる約1,100万人の生産年齢人口が減ります。そのため、介護に限らず人手不足の課題を抱えることが予想されます。
ただ、同じ環境下であっても、人を惹きつけられる職場には人が集まってきます。なので、働く場としての競争力を持った事業所を育てていくことがこれからの人材市場で戦ううえで大切です。
──事業所の努力だけでなく、それを後押しする行政のサポートも不可欠だと思います。国や自治体はどのような役割を果たすべきでしょうか?
国の役割としては、賃上げにかかる財源の仕組みを改善すべきだと考えています。現在の「介護職員等処遇改善加算」は基本報酬とは別枠で設定されています。これは、公定価格のなかでいかに賃上げのための財源を別枠的に担保していくかという発想からのもので、本来あるべき姿としては歪と言わざるを得ません。
言ってみればこの加算は、事業者に任せておくと賃上げに使われず、職場環境の整備や生産性向上に取り組まないのではないか、という性悪説に立って財源の使途を賃上げに限定したものです。
そうではなく、基本報酬に組み込み、適宜引き上げていく形が理想です。このご時勢に、財源を賃上げに使わないような事業者は働き手から選ばれません。逆に、事業者の裁量にゆだねて独自性を発揮したり、競い合ったりすることで、介護職の処遇改善につながります。
一方、自治体の役割としては、地域の実情に合わせた支援が大切です。よその地域で成功した型をただ持ってきても、自分たちの地域には当てはまらないケースもあります。自治体内での調査をしたうえで、先進的な取り組みを育てる役割を果たすことが求められます。
また、先進的な取り組みをしている事業所は身近に例がないことから、孤独になりがちです。自治体はこうした事業所を財政面を含め応援することも重要です。
「思い」を大切に、未来の介護業界をより良く
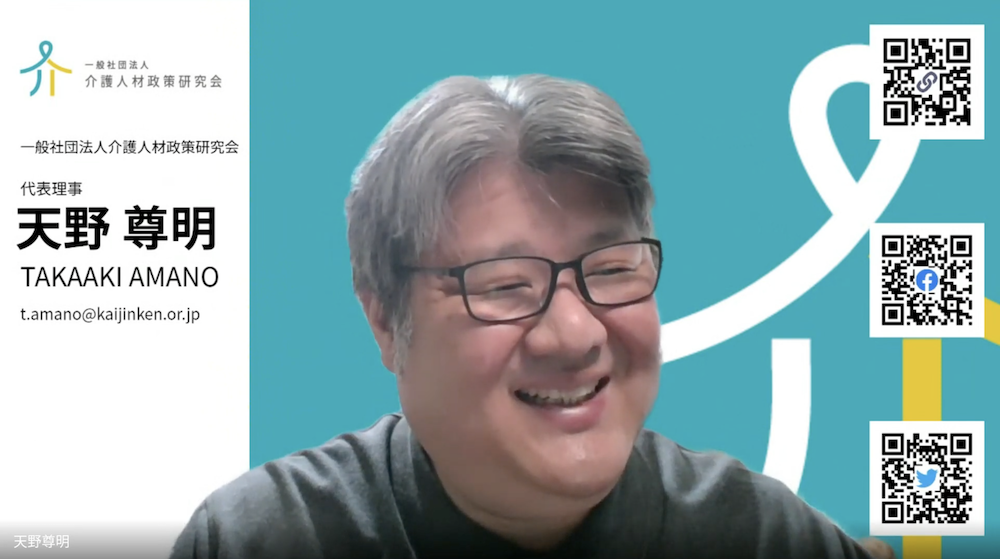
──今後、介護業界で求められるのはどのような人でしょうか?
マネジメント意識を持った人です。理事長や管理職だけがお金とにらめっこして頭を抱えている事業所も多いですが、職員一人ひとりが当事者の目線に立ち、日々のケアがどう利用者のためになり、どのように給与として手元に届いているのか意識することが大切です。これにより、現場での判断や行動、改善がより的確になり、優れた人材が活躍できる職場づくりにもつながります。
──では、こうした人が活躍できる介護業界にするためには、どのような姿勢が大切だと思いますか?
「未来を良くすることをとにかく諦めず、努力する」ことが大事だと思っています。SNSでは、毎秒のように誰かが不満や批判を発信しています。対人業務、チームプレーを主とする介護業界では、職員同士や利用者とのさまざまなトラブルにも接します。
ただ、ネガティブは原動力にはなりますが解決策にはなりませんから、「ならばどうするのか」という姿勢が必要です。介護に関わるすべての方が、それぞれの正義のなかでできることを一生懸命やれるよう、仲間を一人でも増やすサポートをしていきたいですね。
──それでは最後に、介護職として働く方やこれから働こうとしている方にメッセージをお願いします。
介護業界で働こうとした理由はさまざまかと思います。天職と感じた、身近だったから……どなたもこの介護分野においてかけがえのないプレーヤーです。
働くうえでしんどいと感じることもあると思います。そんなときは、自分一人で解決しようとすることが必ずしも正解ではないと知ってほしいです。横を見れば、同じ環境で働いている人もいて、一緒に苦労話を言いあうのもいいですし、言いづらければほかの施設の人とつながりを持つことも有効です。どうか自分だけで戦い、ひと知れず苦しむような日々を送ってほしくないと思っています。
皆さんの思いや感じたことや、率直に介護に触れていただくことが、必ず良い未来につながります。さまざまな「思い」を大切に、ときに我々を含む誰かに伝えたりもしながら、皆さんのペースで介護に携わっていただけたらうれしいです。