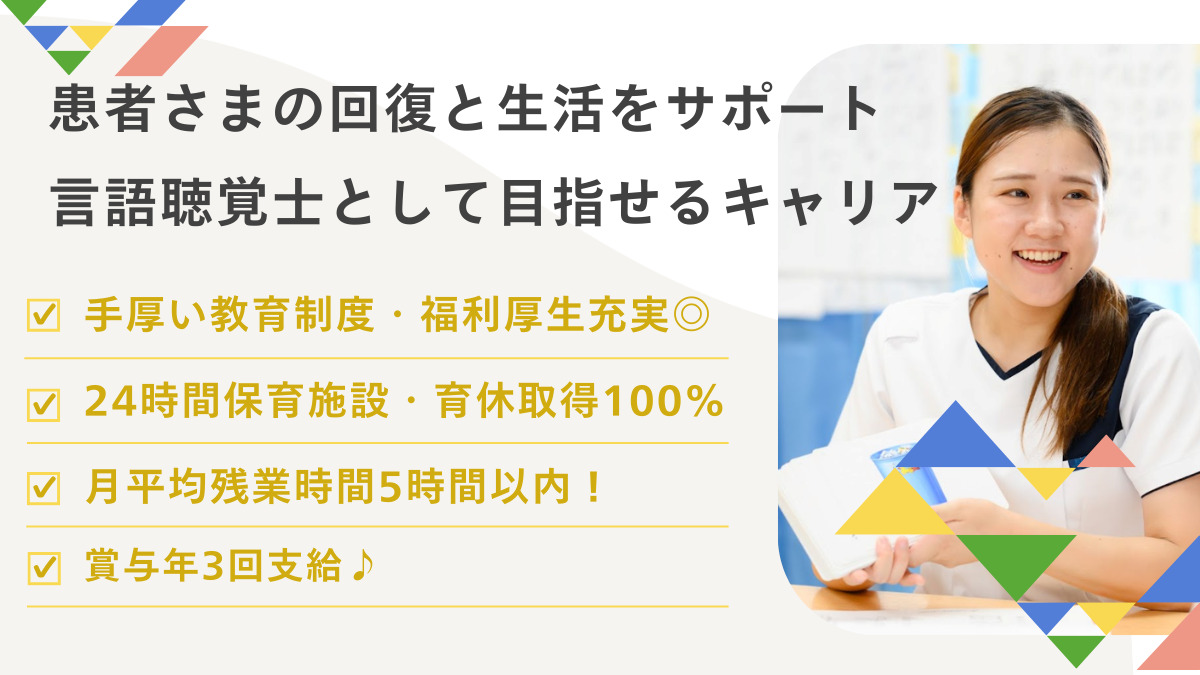1.話を伺ったのは、言語聴覚士歴10年目のRさん

2.訪問リハビリテーションの仕事内容

──まず簡単に訪問リハビリテーションの説明と、Rさんの勤務先について教えてください。
訪問リハビリは、病気や障がいを持った人、高齢で身体機能が低下している人のところに、私たちリハビリの専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)が訪問してリハビリを提供するサービスです。
訪問リハビリをするスタッフは病院や介護施設、訪問看護ステーションなどに所属してることが多いんですが、うちはちょっと珍しくてリハビリに特化した在宅診療をおこなうクリニックなんです。院長と私の2人体制で訪問してリハビリに取り組むこともありますし、私ひとりで訪問することもあります。
──利用されているのはどんな方でしょうか?
まず原則として、訪問リハビリは医師がその必要性があると判断した人しか利用できません。私たちリハ職は医師が作成する「訪問リハビリテーション指示書」をもとにリハビリのプランを立て、実行します。
今担当しているのは全員在宅で、要介護2〜要介護5の方が多いです。年齢でいうと70代後半から90歳くらいまでですね。
──皆さんどういった理由で利用されるんですか?
リハビリに取り組む目的としては「心身の機能の回復や維持、日常生活の自立」が一般的ですよね。
うちの場合は飲み込みリハビリテーションを得意としてるので、食べ物や水分を飲み込む「嚥下(えんげ)機能」に問題がある患者さんからの依頼が多いです。高齢になると嚥下機能が低下してしまう人が多くて、食べ物がのどに詰まる・誤って気管に入るなどして誤嚥性肺炎を引き起こすリスクが高まったり、口から栄養が摂れなくなって胃ろうが必要になったりするんです。
あとは食形態のレベルが低い人──例えばペースト食しか食べられない人が、常食を食べられるようになりたいと希望を受けることもあります。
──訪問リハビリの一日はどのようなスケジュールでしょうか。
日によっても違うんですけど、先生との訪問診療と単独での訪問リハビリ、どちらも行く日はこんなスケジュールになります。

今はスタッフが4人(医師、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、社会保険労務士)と少ないので、全員で社用車に乗りながら仕事してて、移動オフィスみたいになってます(笑)。
訪問リハビリはできるだけ昼食時・夕食時に行くようにしてます。食事中の状態を見ながら指導できますし、リハビリを先にすると食べる前の準備運動にもなるので。
──一日に訪問する件数はどのくらいなんですか?
院長と一緒に行く訪問診療は平均8人くらいです。車で片道30分ほどかかる距離まで行くので、移動時間に結構時間がとられます。単独で行く訪問リハビリは0人の日もあれば4人診る日もありますね。
一人あたりの訪問頻度でいうと、制度上訪問リハビリは1回20分で最大週6回まで(1日2回まで)入れます。ただ、訪問介護とか看護とかほかのサービスも併用しているとすぐに介護保険の限度額になってしまうので、週1日で2回分(40分)リハビリするのが現実的って感じです。本当はもっと回数を増やしてあげたい患者さんが多いんですけどね。
──訪問先での実際の取り組みや流れについて教えてください。
私が単独でおこなう訪問リハビリの場合で話しますね。
到着したら挨拶もそこそこに、まず患者さんと会話しながらバイタルチェックをします。血圧、体温、サチュレーション(酸素飽和度)を測ってPCに数値を入力。
そのあとリハビリに入ります。嚥下のリハビリは、食べ物を使う「直接訓練」と食べ物を使わない「間接訓練」の2つに大きく分けられます。いくつか紹介しますね。
寝たきり状態や食べられない重度の方は、口頭や頸部(首)の回りを動かす機会が減って硬くなってることが多いので、間接訓練としてストレッチやマッサージでゆるめてあげます。
「アイスマッサージ」というのも間接訓練のひとつで、凍らせたスポイトや綿棒を舌の奥や軟口蓋に触れて飲み込む動作をしてもらいます。寒冷刺激を受けると嚥下反射が起きやすくなるので、飲み込みやすくなるんです。
それから口の中を綺麗にする「口腔ケア」も間接訓練のひとつ。重度の方だと自分の唾液を誤嚥してしまう人もいるので、口腔内を清潔に保つのは重要ですね。
直接訓練の最初のレベルだと、ゼリーを使った訓練があります。薄くスライスしたゼリーを丸飲みするトレーニングから始めて、嚥下力を見ながら少しずつ食形態のレベルを上げていきます。
──そういった訓練は、ご家族に協力してもらうこともありますか?
ありますよ。在宅リハビリでは患者さん本人の訓練も必要ですけど、日ごろ患者さんを見てくれるご家族への指導も大切です。
アイスマッサージや口腔ケアはご家族でもできるので、道具をお渡ししてレクチャーしたり、リハビリ中の不安や疑問があれば相談にも乗ってます。
──リハビリの道具はどんなものを持っていくんでしょうか。
道具は家庭にあるコップとかガーゼを借りてできるものも多いので、持参するものは意外と少ないんですよ。持っていくのはざっとこんな感じです。
訪問言語聴覚士の持ち物リスト
- 状態観察に必要な道具(聴診器、血圧計、体温計、パルスオキシメーター、ペンライト)
- リハビリで使う道具(リハビリゼリー、スポイト、バルーンカテーテル)
- 使い捨て手袋、消毒スプレー、スリッパ
- 筆記用具、メモ
- PC

──結構コンパクトですね。服装はどんなでしょうか?
自分は紺色のスクラブを着てます。ちなみに先生は白衣ですね。
──院長と一緒に訪問診療する場合は、リハビリ面でやることに違いはありますか?
うちのクリニックの強みでもあるんですが、ポータブルの内視鏡を使って訪問先でも内視鏡検査ができることですね。のどの中の飲み込む様子を直にモニターで見れるので、より正確な評価と指導ができるようになるのが大きな利点です。

嚥下のリハビリって普通は見えない部分を診るので、「ブラックボックスに手を入れてやるようなもの」と表現されるくらい、客観的な評価が難しいんですよ。だから本来言語聴覚士の経験とかセンスによるところが大きいんです。
あとは院長と一緒に診療すると、理学療法や作業療法を含めた全身訓練や、内部疾患についても隣で学べるのでかなり勉強になりますね。
──そういえば、同時期に理学療法士や作業療法士が訪問リハビリに入ることもあるんですか?
ありますよ。嚥下機能と全身の身体機能は比例すると言われてるので、身体機能を回復することは嚥下機能を良くするためにも有効なんです。
ただ私が理学療法士や作業療法士と直接関わることはあまりなくて、なにか申し送りがある場合は患者さんの家にメモを残しておいたりしますね。
──そうなんですね。ほかにはどんな職種の方と関わりがありますか?
訪問リハビリは主治医からの指示とケアマネジャーから依頼を受けてサービスが開始するので、その2名との関わりが多いですね。月に1回報告書を作成して医師とケアマネジャーに提出しますし、ほかにも気になることがあれば都度連絡してます。
あと他職種と関わる機会といえば、退院前カンファレンスとサービス担当者会議ですね。退院前カンファレンスは、その名のとおり退院前に開かれる関係者会議で、患者さんが在宅生活に戻ったあとのケア方針について話し合う場です。サービス担当者会議は、在宅サービスが開始してからその経過と今後についてを話し合う会議です。
これらの会議には医師、看護師、ケアマネジャー、ヘルパー、リハビリ職が参加するので、ここでなにかあれば情報共有するのが基本ですね。例えば日常的に食事を作ってくれるのがヘルパーさんだったら、調理法についてのアドバイスをしたりとか。
ただ新型コロナウイルスが流行ってからは、退院前カンファレンスはZoomでの開催が増えて、サービス担当者会議は開催されないことが増えました。だから以前よりも他職種と直接関わる機会は減ってしまいましたね。
3.在宅医療・訪問リハビリの世界で働くということ

──Rさんは9年間病院で働いてたとのことですが、訪問リハビリを始めようとしたきっかけは何だったんですか?
病院では急性期・回復期・維持期と、その人が病気になってから回復するまでの経過を見てきました。でも病院にいると、その人が退院したあとの生活までは見えないんですよね。
中には一度退院したのにまた戻ってくる患者さんもいて。聞けば病院でできてたリハビリが自宅でできなかったり、そもそも入院期間中に十分なリハビリができずに退院してしまう人も少なくなかった。そこにもどかしさを感じたというか、自宅に帰ったあともサポートできる言語聴覚士がいたらいいなって思ったんですよ。
そう思ってたときに、飲み仲間だった今の院長が在宅診療専門のクリニックを開業するから一緒にやらないかって話になって。それで立ち上げメンバーとして転職したって感じですね。
──実際に在宅医療の現場に出られるようになって、どう感じてますか?
病院と違って、なにかあったときすぐにヘルプに来てもらえない不安はあります。とくに嚥下訓練中にサチュレーション(酸素飽和度)が下がるなど、命に関わるリスクもあるので……。なので、なにがあっても落ち着いて対応できるように心がけてます。
あと言語聴覚士は発話などの言語訓練もやるんですが、訪問先によってはリハビリに必要な道具を並べるスペースが確保できなかったりして、病院のようにはいかないなと思うこともあります。
良い面でいえば、「食べたかったごはんが食べられるようになった」と患者さんやご家族から喜んでもらえるのが一番嬉しいですね。
──訪問するなかで思い出に残っているエピソードはありますか?
誰かひとりの思い出じゃないですけど……訪問では、お金持ちの社長さんから生活保護の家庭まで、本当にいろんな人たちの人生を垣間見るんですよ。それまで自分が知ってた世の中はほんの一部で、自分の思ってた普通は普通じゃなかったってことを思い知らされましたね。
今日の訪問先もちょっと大変でした。独居の認知症のおばあさんで、ヘルパーが入ってるはずなのに出来合いのごはんが置いてあるだけで食べられてなかったりとか、警察のお世話になってたりとか。院長が見かねて役所に相談しに行ってたところです。
──それは大変でしたね……でも本来、そういった役所への相談などはケアマネジャーの役割なのでは?
そうなんですよね。詳しい事情は聞けてないですけど、ケアマネさんもどうすればいいか対処しかねてたんじゃないかな。訪問診療で回ってると、こういう事例って決して珍しくないですよ。
だからというわけじゃないんですけど、実は今、ケアマネジャーの資格取得を目指してます。今のケアマネジャーって介護職出身者が多くて医療的目線で考えられる人って少ないんですよね。それが悪いわけじゃないんですけど、医療職出身のケアマネが増えたらもっとできる幅も広がるんじゃないかと思って。
ゆくゆくは、クリニックに併設した居宅サービス事業所を開けたらいいななんて考えてるところです。
──そんな目標をお持ちなんですね。では最後に、現在のお給料についても伺っていいですか?
基本給が36万円で、交通費と残業代が追加されて額面で40万円くらいです。
ボーナスは今のところ出てませんけど、病院時代と比べるとかなり上がりました。
──病院時代はどのくらいだったんですか?
残業代や手当も含めて、額面で30〜32万円くらいですね。ただその分、ボーナスは年間で月給の5ヶ月分出てました。
病院はどうしても給料が低めになりやすいですけど、それでも若いうちは総合病院でいろんな患者さんを見て知識と経験を積んでおいて良かったと思います。
実際訪問に出てみると、在宅で嚥下を見てほしいって依頼はかなり多いです。でも言語聴覚士はそもそもの従事者数が少なくて、供給が追いついてません。経験を積んだ言語聴覚士が訪問リハビリの現場にもっと増えたらいいですね。