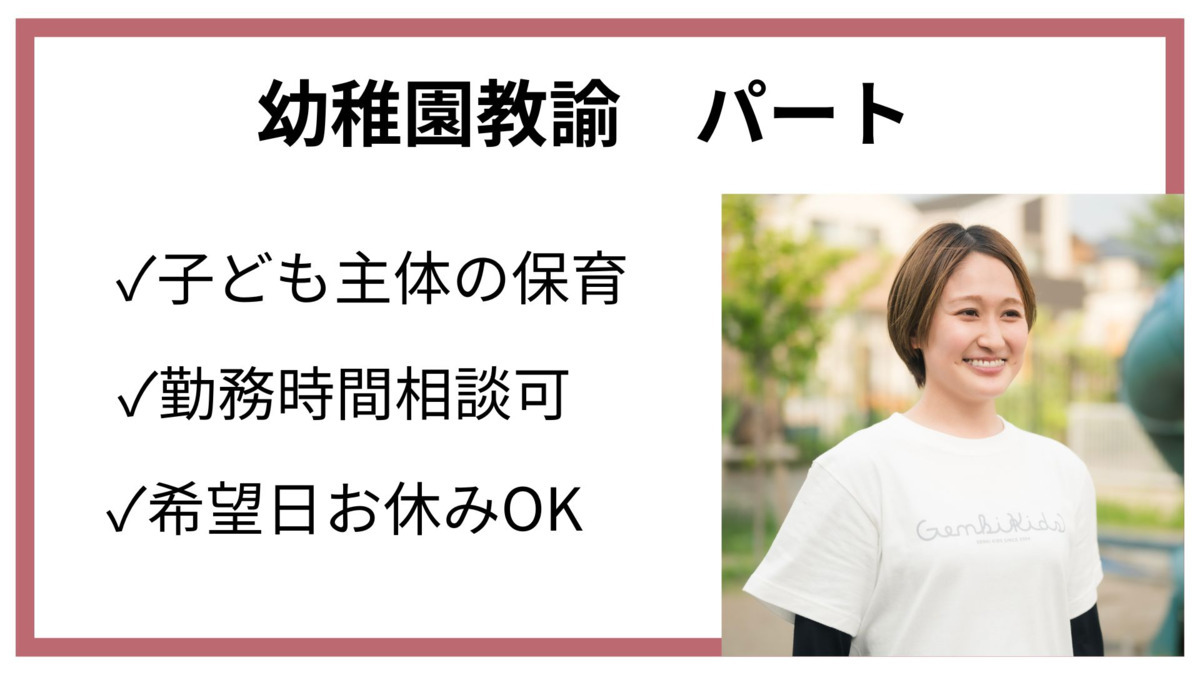1.認定こども園とは
1-1.概要
1-2.幼稚園、保育園との違い
1-3.利用手続き
1-4.保育料
1-5.認定こども園の4つのタイプ
2.認定こども園で働く
2-1.必要な資格・免許
2-2.仕事内容
2-3.働くメリット・デメリット
2-4.給料
3.さいごに
1.認定こども園とは
1-1.概要
認定こども園とは、幼稚園と保育園の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一体的におこなう施設です。0歳から就学前の子どもまで、保護者が働いている・いないに関わらず利用でき、預かり時間が長いことが特徴です。
認定こども園の制度が開始されたのは2006年。都市部を中心に全国で約2万人の待機児童が存在する一方で、幼稚園の利用児童は10年間で10万人も減少しました。この背景には、共働きの家庭の増加に伴い保育園の入園希望者が増える一方で、 専業主婦(夫)の家庭が減り幼稚園の入園希望者が減少していることがあります。そこで、幼稚園と保育園の機能を併せ持った認定こども園ができることで、既存施設の有効活用と効率的な運営をおこない、待機児童問題の解消を目指しています。
また、少子化が進み子どもや兄弟の人数が減る中で、子どもの成長にとって大切な集団活動や異年齢交流の機会を増やす目的もあります。
認定こども園の施設数は、2022年4月時点で全国に9,220施設あります(※1)。
1-2.幼稚園、保育園との違い
認定こども園、幼稚園、保育園それぞれの違いはどのようなところでしょうか? おもな点を以下にまとめます。
| 認定こども園 | 保育園 | 幼稚園 | |
|---|---|---|---|
| 管轄省庁 | 内閣府 | 厚生労働省 | 文部科学省 |
| 施設の位置づけ | 園により異なる | 児童福祉施設 | 教育施設 |
| 利用できる年齢 | 0歳〜就学前 | 0歳〜就学前 | 3歳〜就学前 |
| 利用できる認定区分 | 1・2・3号認定 | 2・3号認定 | 制限なし |
| 標準的な保育時間 | 4〜11時間 | 8〜11時間 | 4時間 |
| 保育料 | 世帯収入などに応じて自治体が定めた金額 | 世帯収入などに応じて自治体が定めた金額 | 園により異なる |
| 保育者の資格 | 保育教諭 保育士 幼稚園教諭 | 保育士 | 幼稚園教諭 |
| 給食の提供 | 義務 | 義務 | 任意 |
2015年に誕生した「子ども・子育て支援新制度」により、認定こども園や新制度下にある幼稚園、保育園に入園するためには、自治体から認定を受ける必要ができました。認定は、子どもの年齢と「保育を必要とする事由」によって1号・2号・3号と区分が分かれています。
■「保育を必要とする事由」とは?
・妊娠、出産
・保護者の病気、障害
・親族の介護、看護
・災害復旧
・求職活動中
・就学や職業訓練中
・虐待やDVの恐れがある
・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
・その他、市町村が認める場合
■認定区分の決まり方

<利用できる施設>
1号認定:認定こども園、幼稚園2号認定:認定こども園、保育園
3号認定:認定こども園、保育園、地域型保育
認定こども園では、1号・2号・3号のすべての子どもが対象なので、たとえば共働きで3号認定で入園した子どもが、3歳を過ぎて保護者の離職により1号認定になった場合でも、退園せず同じ園に通い続けることができます。
なお、利用可能な保育時間は認定区分によって異なります。1号の場合は4時間(教育標準時間)、2号・3号の場合は11時間(保育標準時間)または8時間(保育短時間)です。
そのほかにも市町村ごとに設定している条件があるため、詳しくは各市町村のホームページなどを確認するようにしましょう。
1-3.利用手続き
認定の申請〜入園までの利用手続きは、認定区分によって異なります。
<1号認定の場合>
1. 認定こども園に直接申し込みをします。
2. 園から入園の内定を受けます(定員超過の場合、選考を実施することもある)。
3. 園を通じて市町村に認定を申請します。
4. 園を通じて市町村から認定証が交付されます。
5. 園と契約をおこないます。
<2号・3号認定の場合>
1. 市町村に認定を申請します。
2. 市町村が「保育の必要性」を認めた場合、認定証が交付されます。
3. 市町村に認定こども園の利用申し込みをします。
4. 申請者の希望、園の状況、保育の必要性を踏まえ、市町村が利用調整をします。
5. 利用先の決定後、園と契約をおこないます。
認定こども園はどの認定区分でも利用できる施設ではありますが、定員に達した場合など、状況によっては入園できないこともあります。両親が共働きであったり、ひとり親世帯であったりする場合は優先される傾向にあるようです。
1-4.保育料
認定こども園の保育料は、国が定める上限額の範囲内で、市町村ごとに設定されます。
<国が定めた上限金額(月額)>
1号認定:0~25,700円2号認定:0~101,000円
3号認定:0~104,000円
認定区分、子どもの年齢、兄弟の人数、世帯収入などのさまざまな条件を加味して保育料は決定します。また、地域によっては補助金制度を設けている自治体もあるので、確認してみると良いでしょう。
1-5.認定こども園の4つのタイプ
認定こども園は、地域の実情や保護者のニーズに応じて選択できるように、以下4つのタイプに分かれています(カッコ内は2022年4月時点での施設数)。
■幼保連携型(6,475園)
幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持つタイプ。
認定こども園として独立しており、教育機関かつ児童福祉施設として文部科学省と厚生労働省から認可を受けている。
■幼稚園型(1,307園)
既存の幼稚園に、保育園の機能が追加されたタイプ。
幼稚園としての位置づけ(教育機関であること)は変わらず、「幼稚園教育要領」に基づいた教育をおこなう。
■保育園型(1,354園)
既存の認可保育園に、幼稚園の機能が追加されたタイプ。
保育園としての位置づけ(児童福祉施設であること)は変わらず、「保育所保育指針」に基づいた保育をおこなう。
■地方裁量型(84園)
既存の認可外の幼稚園や保育園などに、認定こども園の機能が追加されたタイプ。
一口に認定こども園といっても、タイプごとにその内容はさまざまです。幼稚園がベースとなっている園は、運動会やお遊戯会などの園行事、英語学習やスポーツなどの教育環境が充実しているところもあります。保育園がベースとなっている園は、共働きの両親が多く保護者同士の付き合いが幼稚園と比べると少ないとも聞きます。
園によって特色や教育・保育方針は大きく異なるため、家庭の状況や子どもにどのような過ごし方をさせたいのかを考えて選ぶと良いでしょう。
2.認定こども園で働く

2-1.必要な資格・免許
認定こども園で働くのに必要な資格は、「幼保連携型」と「そのほかの認定こども園」の2パターンで大別されます。
■認定こども園で必要な資格| 幼保連携型認定こども園 | そのほかの認定こども園 |
|---|---|
| 保育教諭の資格が必要 (幼稚園教諭+保育士) | 満3歳以上: 幼稚園教諭+保育士の併有が望ましいが、いずれかでも可 満3歳未満:保育士資格が必要 |
保育教諭とは、2015年の「子ども・子育て支援新制度」の開始および「認定こども園法」の改正により新しく誕生した「幼保連携型認定こども園で保育にあたる職員」のことです。「幼稚園教諭免許状」「保育士資格」の2つの資格を保有することが原則となっています。
2030年3月31日までは経過措置期間として、どちらか一方の資格を持ち一定の実務経験がある場合は、保育教諭として働くことが可能です。
また、もう一方の資格取得を推奨するための「資格取得特例制度」も設けられています。幼稚園教諭または保育士として3年かつ4,320時間以上の実務経験がある人、または、幼保連携型認定こども園で2年以上2,880時間以上の実務経験がある人は、試験や履修科目数が一部免除され少ない負担で取得することができます。
なお、幼稚園教諭免許状を持っている人向けの資格取得特例制度は、2025年3月末まで、保育士資格保有者向けの資格取得特例制度は、2030年3月末までの期限がありますので注意しましょう。
■資格取得特例制度について方法1:幼稚園などで3年かつ4,320時間以上の実務経験がある人が、保育士養成施設で特例教科目8単位を修得する(保育士試験は全科目免除)
方法2:幼保連携型認定こども園で2年以上2,880時間以上の実務経験がある人が、保育士養成施設で特例教科目6単位を修得する(保育士試験は全科目免除)
<新たに幼稚園教諭免許状を取得する場合>
保育士として3年かつ4,320時間以上の実務経験がある人が、大学で指定の8単位を修得後、教育職員検定を受験し合格する
この特例制度にあわせ、最低限の受講で済む通信制カリキュラムを用意している学校が多数あります。取得を考えている人は調べてみると良いでしょう。
また、特例制度について詳しくは、こども家庭庁と文部科学省の案内を確認してください。
・幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例(こども家庭庁)
・幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例(文部科学省)
2-2.仕事内容
認定こども園では、園のタイプや方針、受け持つ子どもの認定区分によってスタッフの仕事内容が変わります。
3〜5歳の幼児(1号・2号認定)を受け持つ場合は、1号認定の子どもの帰宅時間にあわせ、14時前後までをメインの活動時間とすることが多いようです。また、子どもの年齢によって途中で保育者が交代することもあるため、引き継ぎをしっかりおこなう必要があります。
保育時間が長い認定こども園では、シフト制を組むことが一般的です。そのため、預かり時間が短い幼稚園で働いていたスタッフは、はじめは少し戸惑うかもしれません。
2-3.働くメリット・デメリット
保護者にとってはありがたい条件が多い認定こども園ですが、スタッフにとってはどうでしょうか? 認定こども園で働くメリット・デメリットをまとめます。
<メリット>
◎ 受け入れる子どもの分だけ、幅広い保育経験ができる
子どもの年齢層が広く、異年齢教育に力を入れている施設が多い認定こども園。これまで特定の年齢の子どもだけを対象にしていた人にとっては、業務の幅が広がり、保育者としてのスキルを磨くことができます。
◎ 幼児教育、保育の両面を学べる
「学習面を中心とした指導」をおこなう幼稚園と「生活面を中心とした指導」をおこなう保育園の機能を持った認定こども園で働くことで、それぞれの教育方針や保育観について学ぶことができます。
<デメリット>
△ 業務範囲が広く負担が増える
さまざまな経験を積めるメリットがある反面、仕事の幅が広がることで負担に感じる人もいるでしょう。
△ 保護者のタイプもさまざま
幼稚園と保育園では、保護者の考え方やコミュニティにも違いがあります。保護者と接することが好きな人にとってはやりがいを感じられる部分かもしれませんが、多様な価値観を持った保護者の対応を難しいと感じる人もいるかもしれません。
2-4.給料
認定こども園で働くスタッフの平均給料はどのくらいでしょうか? 2020年6月にジョブメドレーに掲載されている認定こども園の求人を集計したところ、以下の金額となりました。
■認定こども園の平均給料| 正職員(月給) | 20.6万円 |
|---|---|
| 契約職員(月給) | 18.3万円 |
| パート・アルバイト(時給) | 1,076円 |
この金額には、各種手当や交通費、賞与などは含まれていないため、実際の支給総額はさらに高い可能性があります。とくに私立の場合は、園独自の福利厚生などを設けているところもあるため、募集要項を確認すると良いでしょう。
また現時点では、認定こども園で働く保育教諭、幼稚園教諭、保育士の資格に応じた待遇制度は設けられていません。しかし幼稚園教諭と保育士の両資格取得を推奨していることからも、将来的に待遇の見直しがされる可能性は考えられます。
3.さいごに
幼稚園と保育園の良さを併せ持ち、保育者としてのスキルアップを望める認定こども園。メリットが多い反面、幼稚園か保育園一方のみを経験してきた人にとっては、ハードル高く感じてしまうかもしれません。そういった人は、まずは幼稚園型か保育園型の認定こども園に入職してみて、「幼保一体」の環境に慣れてみてはどうでしょうか?
保育教諭になるための資格取得特例制度は、2019年の法改正にて当初の5年間から10年間(2025年3月31日まで)に延長されました。また、2024年の法改正により幼稚園教諭の普通免許状取得に関する特例がさらに5年間(2030年3月31日まで)延長されています。働きながらでも少ない負担で資格取得できるのは今のうちなので、どちらかの資格を持っている人は、一度検討してみることをおすすめします。
※1:都道府県別の認定こども園の数の推移(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0f3ffc2a-7126-4f96-9497-dd3dbfb5438f/abda85e0/20230929_policies_kokoseido_kodomoen_jouhou_02.pdf
※2:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/sukusuku.html
※3:幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339596.htm