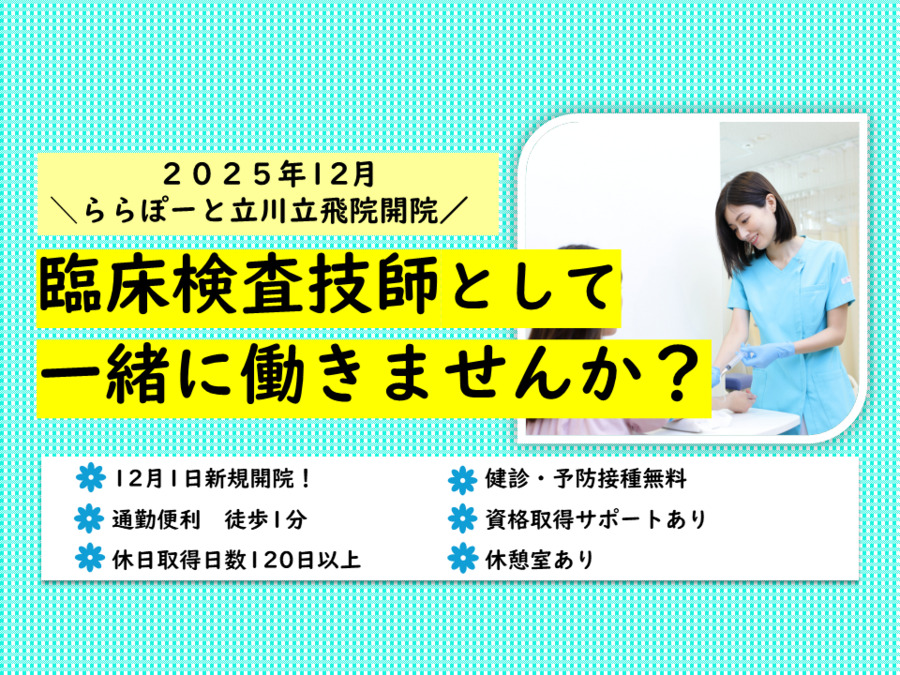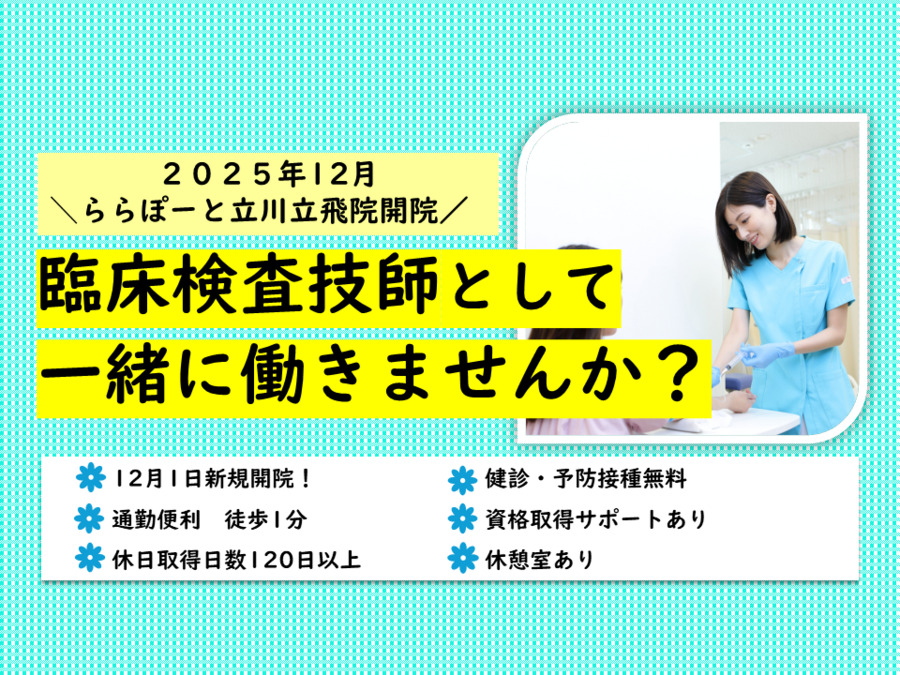臨床検査技師は、病気の診断や治療に必要な検査をおこない、その結果を医師に提供する専門職です。日本の病院で15年間の経験を積んだ臨床検査技師が選んだのは、独立行政法人国際協力機構(以下、JICA)での国際協力でした。
JICAは、インフラ整備や教育、防災・復興支援に加え、医療・福祉分野でも開発途上国を支援しています。
今回取材したIさんは、勤務先の休職制度を利用し、JICA海外協力隊としてフィジーに渡航しました。キャリア15年目にして海外での挑戦を選んだ理由と、現地での活動をとおして感じた変化を伺いました。
話を聞いた人

臨床検査技師 Iさん
祖母が障がい者支援をおこなっていたことから、福祉が身近な環境で育つ。次第に医療への興味がふくらみ、病院で働きたいという希望を抱く。東北大学医学部保健学科検査技術科学専攻を修了し、卒業後は地元の総合病院に入職。4つの部門を経験したのち、2024年4月からJICA海外協力隊としてフィジーで活動中。
就職の原点は中学からの夢
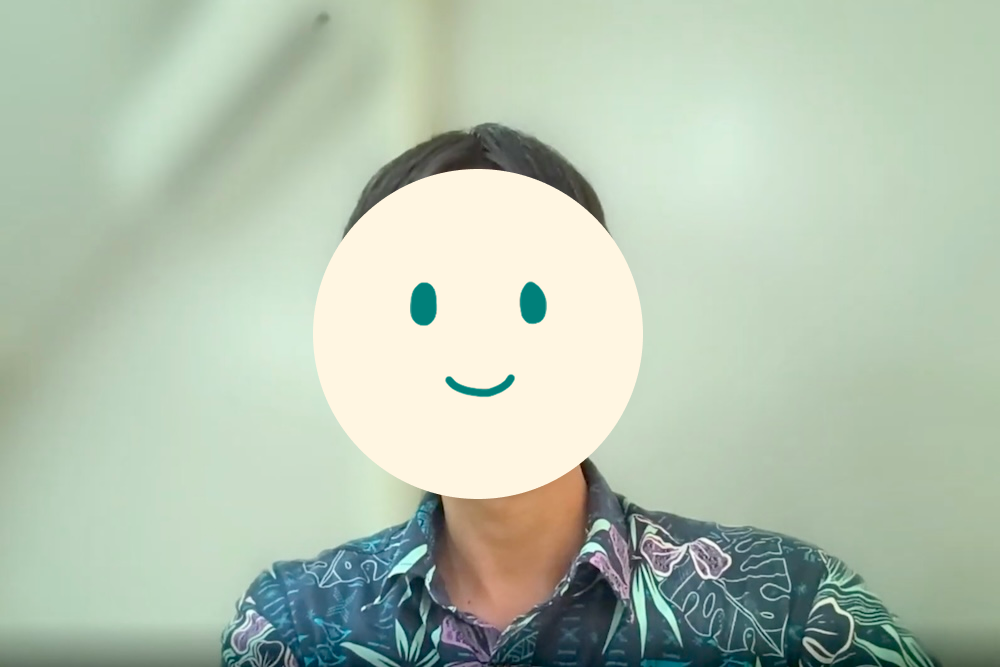
──まず、なぜ臨床検査技師になろうと思ったのか教えてください。
Iさん:もともと祖母が障がいのある方に裁縫を教える活動をしていて、子どものころから人の役に立つ仕事を身近に感じていました。そんな祖母の姿を見ているうちに、「人の健康や生活を支える医療にも関わってみたい」と興味を持つようになったんです。中学生のころには「いつか病院で働きたい」という夢が芽生えました。
ただ、高校で進路を選ぶ時期に、自分は内向的だから看護師のように直接患者さんと接するよりも、ラボで黙々と仕事するほうが合っていそうだと思ったんです。そこで出会ったのが臨床検査技師でした。
──新卒で入職した病院では、どのような業務に携わりましたか?
新卒で地元に近い東北にある市立病院に就職し、現在もその病院に籍を置いています。
最初の5年はまず血液検査部門に配属となりました。ここでは機械を使った血液検査や、輸血で問題が起きないか事前にチェックするなどの業務をおこなっていました。うち2年はMRIとの兼務で、週3日は血液、それ以外はMRI検査に携わっていました。
それから細菌検査部に異動になり、感染症の検査やウイルスの特定をおこなっていました。実務経験5年を満たしたので、微生物検査や院内感染制御に関する知識の証明となる認定臨床微生物検査技師を取得したのもこのころです。
そのあとは健康診断などのデータを出す、生化学検査部に異動となりました。
コロナ禍で気づいた挑戦への意欲
──JICAへの参加を決意したのはいつですか?
最初に意識したのはコロナ禍でした。細菌検査部にいたので、ダイヤモンドプリンセス号の集団感染があった2020年1月ころから忙しくなり、ピーク時は早朝・夜間・土日問わずコロナの検査に追われる日々でした。病院の職員も陰性を証明しないと働けなかったり、勤務中に体調不良になった職員の検査をしたりと、どの職員よりも早く来て遅く帰るという。
──それは大変な日々でしたね……。
間違いなく最も激務だった時期なんですが、なりたくてなった職種だからか、仕事を辞めることは一切考えませんでした。むしろ、「こんなに過酷な状況も乗り越えられるなら何でもできるかもしれない」と感じたんです。
──多忙さに嫌気がさしたのではなく、逆にやる気が湧いたのですね。
そうです。それまで時間がたっぷりあったはずなのに、帰宅後も休日もダラダラと過ごしていたことに気づきました。コロナが落ち着いてきたころ、いままで何していたんだという後悔が押し寄せてきて、これまでやったことのないことに挑戦しようと思ったんです。
──その挑戦として国際協力を選んだのはなぜでしょう?
父が阪神淡路大震災にボランティアに行った姿を見ていたので、自分もいつか困っている人の役に立ちたいという思いが頭の片隅にありました。JICAは小学生のころから知っていましたが、自分が関わるイメージを持てずにいました。
それでも、40歳を目前にして「いま挑戦しなかったら今後も挑戦しないまま人生が終わってしまう」と思い立ち、改めてJICAのサイトを見てみると、臨床検査技師として応募できるプロジェクトを見つけたんです。募集要項にある「実務経験10年以上(が望ましい)」を満たしていたので、思い切って申し込みました。
──なぜフィジーに応募したんですか?
募集していた院内環境整備でなら、これまで感染制御チームでおこなっていた経験が活かせると感じたからです。あと、応募した2023年はコロナ禍の疲れが残っていて、海が見える国がいいなと思ったのも理由の一つです。アフリカなどは任期である2年間をやり遂げる自信がありませんでした。
あとから事務局の人に聞いたら、単一応募は珍しいケースで、ほとんどの人は複数応募しているようです。
──海外協力隊になるには、どのような選考フローがありましたか?
まず書類選考があり、応募要件を満たしているかなどが審査されます。そのあと専門職による面接があり、これまでの経歴を詳しく聞かれました。
募集しているプロジェクトや国によっても異なると思いますが、私がフィジーに赴任したときは、基本的に少人数体制だったため、ある程度の経験を積んだ人が派遣されていました。
──2023年の春に応募して、2024年の8月からフィジーに渡っています。職場とはいつ、どのように話しましたか?
書類選考が通過した時点で上長に相談しました。辞めたいとは思っていなかったので、勤務先の制度を調べたところ、自己啓発や進学、ボランティア活動の参加のための休職制度があることを知ったんです。
人手不足でさらなる厳しさも懸念されるなかでしたが、上長は私の思いを汲み取り休職を受け入れてくれました。ただ制度利用の前例がなかったので、細かい部分は私の応募が決まってから整えてもらい、派遣前訓練開始の2024年4月から2年間休職することになりました。
──国際協力の参加を、職場以外の誰かに相談しましたか?
結婚しているので、妻には応募前や選考など都度相談していました。応援してくれていたのでその点は心強かったんですが、妻のご両親に報告する際は理解が得られるか不安で緊張したことを覚えています。しっかり話をした結果、納得してもらい無事参加することができました。
──フィジーに来てから研修などはありましたか?
こちらに来てからまず1週間はフィジーJICA事務局のあるビティレブ島というところで、オリエンテーションがありました。ビザの登録や銀行口座の開設手続きをして、安全管理について学びました。
翌週からは赴任先のバヌアレブ島に来て、病院での勤務開始という流れです。

院内環境を改善する“5つのS”
──どのような頻度・時間で働いていますか?
平日の8時〜16時30分勤務です。JICAでは勤務先の規定に準じる決まりになっているため、赴任先や職種によっては夜勤や土日勤務が発生することもあります。
──担当業務によって異なるんですね。現在取り組んでいる内容を詳しく教えてください。
主に、「5S-KAIZEN-TQM」と呼ばれる活動をおこなっています。5Sとは「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の頭文字を取った標語です。TQMはTotal Quality Managementの略で、安全性や品質の継続的な向上を目指す取り組みです。これにより、職場環境を改善し、業務の効率化やパフォーマンス向上につなげています。
赴任先は島内で一番大きな国立病院ですが、廊下に物が置かれて車イスやストレッチャーが通りにくかったり、整理整頓が十分ではなかったり、紙カルテの保存状態が悪いなど、改善の余地があります。
なので、日々いろいろな科を巡回して、整理整頓の状況や感染対策、薬品の取り違えリスクなどをチェックしています。約30部門を回り、改善が必要と思う箇所は撮影して後日改善要望として提出する流れです。

──部署に所属して、チームで業務にあたっているのでしょうか?
そうです。病院の運営管理や環境整備全般を担うクリニカルガバナンス部門という部署に所属しています。私以外に感染管理ナースが3人とお客さま苦情係が1人、そのほか部門長の看護師が1人の計6人のチームです。
私1人で各部署に行き現場のスタッフと一緒に5S活動をおこなうこともあれば、チームで病院内の巡視をすることもあり、日々多くのスタッフと連携しながら取り組んでいます。

働いて見えた現実と課題
──Iさんがフィジーに赴任してから約1年半が経ちました。現地での業務や暮らしについて率直な感想をお聞かせください。
現地の方の人柄に大きく助けられていて、人間関係で悩むことがないのがありがたいですね。文化や仕事の進め方が異なる自分が新しく加わったのに、スタッフや患者さんはとてもフレンドリーに接してくれました。
日本での感染制御チームにいた経験から、院内の環境について思うところもありますが、自分のやり方や考えを押しつけないようにと心がけています。
──実際に働いてみて、病院の環境やご自身のスキルで課題に感じることはありますか?
環境面で言うと、島なのでやはり物資は不十分に感じています。例えば、整理整頓のためにキャビネットやラベルシール機、ブックエンドなど細々とした物が必要なのですが、国内でこうしたものを製造しておらず輸入に頼っているので、価格が高く入手しにくいです。
自分のスキル面では英語が得意でないので、いまだにスタッフ同士の会話に付いていけなかったり、自分の考えを伝えるのに苦労しますね。
──物資の充足面以外では、日本の病院との違いをどのようなところで感じますか?
人手不足が日本の比ではないと感じています。人口1,000人あたりの看護師数は日本の場合12人ですが、フィジーは2人です。赴任先の病院でも、人が足りず別の科に土日出勤できる人を募るなど、深刻な状況が続いています。
フィジーは公用語が英語なので、語学と医療技術を活かせて高い賃金が得られる、ニュージーランドやオーストラリアに流出しているようです。
──医療現場で働く人々について、日本で想像していたイメージとの違いがあれば教えてください。
そうですね、一般的にフィジーは南国でゆったりとしたときが流れているようなイメージを持たれるかもしれません。街中を歩いているとそのイメージどおりなんですが、一緒に働いてみるととても仕事熱心だと感じました。デング熱が流行した際は、その対策のために同僚の感染管理ナースは遅くまで残業していて、コロナ禍を思い出して胸が熱くなりました。
経験がいつか自分を支えてくれる
──フィジーに来てから、自身のなかで変化はありましたか?
フィジーと日本、それぞれの良さが見えてきたことで、考え方が少し変わりました。
こちらでは「フィジータイム」と言われる感覚があるくらい、時間に対して寛容なんです。日本で言う5分前行動は、ほかの人を急かしてしまい、かえって失礼なんじゃないかとすら思うことが多々あります。一方で急な予定変更にも誰一人嫌な顔をすることなく臨機応変に対応している点は、見習いたいと思っています。
また、フィジーにはあらゆるものを共有する「ケレケレ」という文化があります。食べ物や時間、楽しさ、幸せまで分かち合う姿勢が根付いています。そのため、ランチを食べるとき自分の分しか持っていなくても、当たり前のように分け合うんです。
一方、日本はタイムマネジメントに長けていると感じます。先を見越して行動するので、逆算して仕事を着実に進められますし、言わなくても一人ひとりがルールを守れるので建設的に物事を進められる点が魅力です。
日本に戻ってもフィジーと日本で学んだ価値観を活かし、より広い視野で物事を捉えていきたいですね。
──異なる環境に身を置いたことで、改めて日本の良さにも気づいたんですね。ほかにフィジーで印象的だった文化や考え方はありますか?
人と人との距離感ですね。フィジーは「幸せ」と感じる人が多い国といわれていますが、その理由が暮らすなかでなんとなくわかってきました。
子どもを預け合ったり、他人の子どもも分け隔てなく育てるようなコミュニティ文化があり、大人も子どもも自然に助け合っています。仕事から帰宅すると、隣の子どもたちが夕飯のお裾分けを持って遊びに来ることもしょっちゅうです。
日本の感覚では個の時間や空間が侵害されるように感じるかもしれませんが、慣れるとその距離感が心地よく、自分もその一員なんだと実感できました。

──最後に、現在転職や海外での勤務など新しいことへの挑戦を検討している人にメッセージをお願いします。
現在の業務には、日本で感染制御チームにいた経験が活かされています。ですが、より役立っていると実感するのは、入職3年目に血液検査部と兼務したMRIでの経験です。
それまでは検査室だけで完結する仕事でしたが、MRIでは患者さんはもちろん、医師や看護師など多職種と関わる必要がありました。ここで「自分の仕事はこの先に広がっている」という感覚を初めて持てたことが、今の自分を支えています。
これまでの経験は、いつか必ず役に立ちます。一歩踏み出さなければ見えない景色があり、挑戦は必ず人生の糧になります。