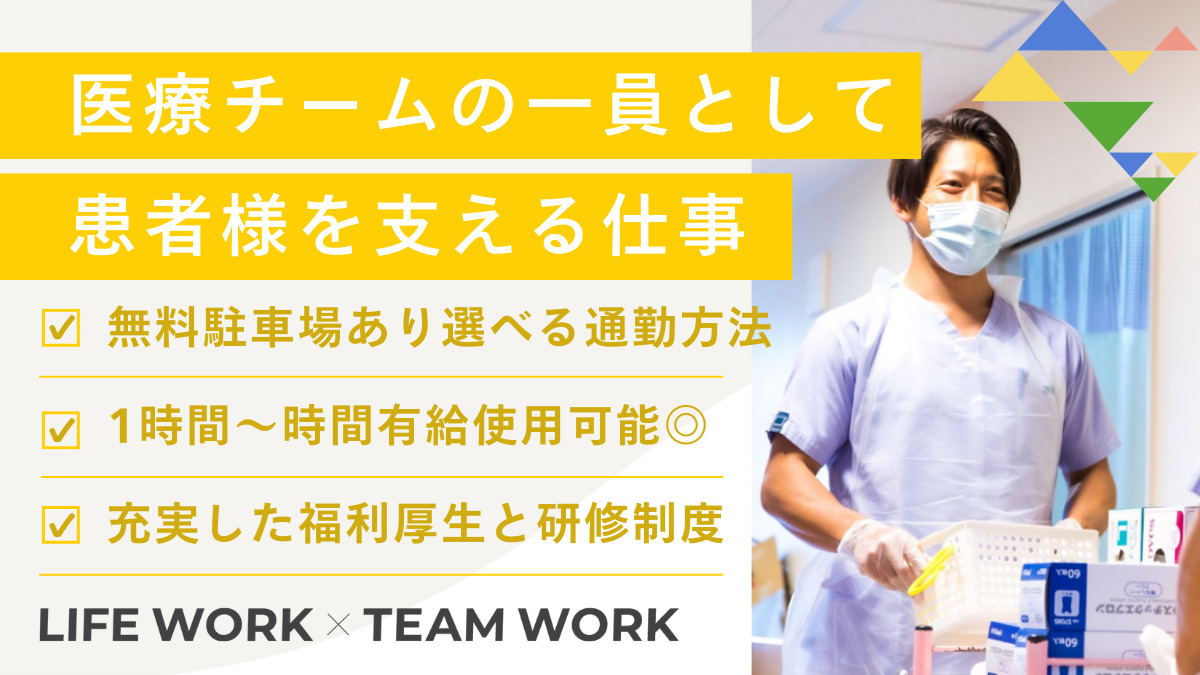準夜勤と深夜勤の違いとは?
準夜勤は「3交代制」を取り入れている、病院や施設における看護師や介護職の勤務形態です。「3交代制」を取り入れている施設では、1日の勤務が「日勤」「準夜勤」「深夜勤」の3種類に分かれており、それぞれの時間帯を8時間勤務にしているところが多いです。深夜勤は深夜〜朝方までの勤務に対し、準夜勤は夕方〜深夜までの勤務となります。
最近では、看護師の労働負担を軽減する取り組みとして、「3交代制から2交代制に切り替える病院」「3交代制と2交代制を併用する病院」など、独自の勤務形態を取り入れる病院が増えてきました。病院や施設で働く職員の負担を考え、夜勤の負担軽減や十分な休息がとれる仕組みを作るなど、労働環境が少しずつ変化してきています。
3交代制に見られる準夜勤のメリット
準夜勤のメリットは、1回の勤務時間が決まっているケースが多いことです。準夜勤のない「2交代制勤務」と違い、準夜勤のある「3交代制勤務」ではほとんどの場合、日勤・準夜勤・深夜勤がそれぞれ8時間と決まっています。ただし、病院や施設によっては、いずれかの時間帯の勤務時間を増減し、3つの勤務時間を変える「変則3交代制」を取り入れている場合もあります。
また、準夜勤のメリットは、午後10時を過ぎた勤務に対して、割増賃金(深夜手当)がつくことです。労働基準法では、午後10時~午前5時までの勤務は深夜労働扱いとなり、雇用者は労働者の時間給に対して、2割5分以上の割増賃金を支払うことが定められています。
準夜勤だから起こる2つのデメリット
準夜勤のデメリットとしては、勤務の間隔が短くなるケースが考えられます。たとえば、日勤で勤務した日の夜に深夜勤をしたり、準夜勤で勤務した翌日が日勤になる場合が挙げられます。
また準夜勤では、勤務終了時の帰宅手段を考慮する必要があります。早朝に勤務が終了する深夜勤者と違い、準夜勤者の勤務終了時刻は深夜24時を回る場合があり、電車やバスなど、公共交通機関の利用が難しくなります。そのため、一定額のタクシーチケットを支給したり、タクシーでの送迎制度を取り入れている職場もあります。
ライフスタイルに合わせた勤務形態を
日本看護協会が行った調査によると、看護師の離職理由として、妊娠・出産・結婚に続き、勤務時間の長さと夜勤の負担が大きいことが多く挙げられています。
(参照:日本看護協会/現状と現行施策について)
職員の負担軽減策として、病院や施設では、看護師や介護職のさまざまな勤務形態が取り入れられてきています。取り組みの例としては、「短時間の正職員制度の採用」「夜勤免除と夜勤専従制度の活用」「職員による2交代・3交代制の選択」「育児期間中の夜勤回数の軽減」「看護補助者の増員による労働負担の軽減」などが挙げられます。
職種が同じであっても個人のライフスタイルは異なります。多様な働き方が許容されつつある今の時代、仕事と生活のバランスを考えたうえで、勤務形態を選択してみてはいかがでしょうか。