保護者の就労や病気などの理由に関係なく、0〜2歳の子どもが月10時間まで保育園などを利用できる「こども誰でも通園制度」が、2026年度から全国で実施されます。すべての子どもの成育環境を整備し、多様な働き方やライフスタイルの家庭を支援するための制度です。
新制度では、これまでと利用時間・登園頻度の異なる子どもたちが保育園を利用します。この変化は保育の現場にどのような影響をもたらすのでしょうか。2024年からモデル事業としてこども誰でも通園制度に取り組んでいる、認定NPO法人フローレンスおうち保育園あさがやの橋本英気園長に、業務の変化や保育士の反応について伺いました。
話を聞いた人

認定NPO法人フローレンス おうち保育園あさがや
橋本 英気 園長
人材派遣会社と結婚相談所で勤務したのち、子育て家庭や働く女性への支援を志して、保育士資格取得。在学中より認定NPO法人フローレンスの保育園でアルバイトとして勤務し、卒業と同時に入職。保育士として複数の園で勤務し、現在はおうち保育園あさがやの園長を務める。
空き枠を活用し0歳児を受け入れ
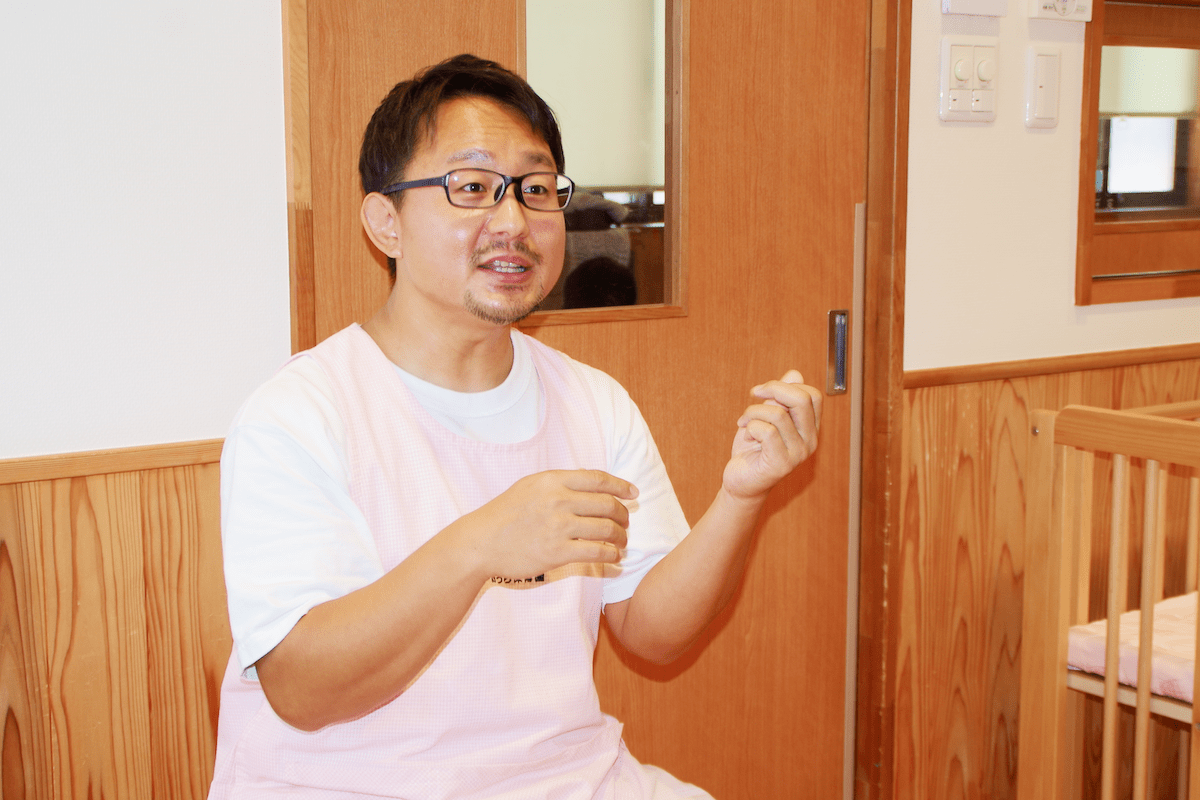
──おうち保育園あさがやでは国の「こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業」として、2024年度から先行実施しています。どのような体制でお子さんを受け入れているのでしょうか?
橋本園長:当園は定員12名(0歳、1歳、2歳の各4名)の小規模認可保育所で、認可定員に空きがある場合にその枠を活用する「余裕活用型」で、こども誰でも通園制度の受け入れを実施しています。現在は0歳児の空き1枠を活用しています。
利用時間は9時から12時半のうちの3時間で、一緒に遊んで昼食を食べたらお迎えの時間になります。週1回までの利用としているので、月曜から金曜まで最大5家庭のお子さんを預かることが可能です。
2025年度もすでに3家庭から申し込みをいただいていて、月曜、火曜、水曜にそれぞれ預かることになっています。実は今日(9月1日)がちょうど新年度の受け入れ初日なんです。
tips|こども誰でも通園制度はどのように実施される?
保育園などが定員の範囲内で受け入れる「余裕活用型」と、定員を別に設ける「一般型」に大別される。預かる時間や回数などは施設ごとに設定でき、2.5時間なら月4回、5時間なら月2回のように回数も変わる。
>制度について詳しくはこちら
こども誰でも通園制度とは?対象者と利用の流れ、費用、メリットをわかりやすく解説
──初日のお子さんはどんな様子ですか?

登園してお母さんと離れるときは泣いていましたが、もう穏やかに過ごしています。子どもはすごく生きる力が強いんですよ。子どもですから泣くこともありますが、それも含めて普段の保育と大きくは変わりません。
「保育士が意義を理解すること」がカギ
──2024年度に初めて実施した際、保育士の皆さんはどのような反応でしたか?
やはり不安の声はありました。制度について知らない保育士もいるので、受け入れ前にミーティングをして不安な点を出してもらったところ、「どんな子が来るかわからない」「週に1回だけだと園に慣れてくれるか心配」「どんな家庭かわからない」などの意見が出ました。
でも、それは新年度の入園や途中入園でも一緒ですよね。それを受け止めることが保育のプロとして大切だと考えています。
──保育する子どもが増えて、登園頻度も異なると保育士さんにとっては不安に感じますよね。不安解消のために何か取り組まれましたか?
ミーティングで制度の意義をしっかり伝えて理解してもらいました。具体的には、これまで保育の認定を受けられなかった専業主婦のご家庭などに対して、保育園・保育士ができる役割が増えることや、社会全体で子育てを支える必要があることを伝えました。
また、この制度が子どもの成長を大切にする点も重要です。子どもの成長にとって社会との接点は大切なもので、いわゆる「無園児」への支援も必要だと説明しました。
利用する家庭とは事前に面談しており、わかった情報はすぐに現場に共有するようにしていて、どのようなお子さんかできるだけ早く把握できるようにしています。
tips|一時預かり事業との違いは?
一時預かり事業は、家庭での保育が一時的に困難な乳幼児を預かる制度。一時預かり事業は保護者の負担軽減の側面が強いが、こども誰でも通園制度は保育園を利用することで子どもの成長を応援することを主な目的としている。
>制度について詳しくはこちら
一時預かり事業での保育士。保育園との違いは?
──こども家庭庁の調査でも実施前に意義や目的を理解することが重要とされていますね。
必須だと感じます。やはり何のためにお子さんを預かっているのか理解があるとないとでは、取り組む姿勢が変わってくると思います。
──2024年度に受け入れを実施して、現場の負担は増えましたか?
それが、想像していたより大変ではなかったんです。実施してみて、これまでに「どうしようもない」というケースはありませんでした。保育士からも「預かり回数を重ねると、自然と落ち着きました」という声がありました。
お子さんが泣く時間は次第に短くなっていきますし、保育士はプロなので、1日あたり3時間の関わりであっても「目の前の子どもが何を求めているか」がわかってくるんです。
──受け入れが始まって不安が解消されていったんですね。保育の現場以外では、運営上の課題はありますか?
25年度からは保育計画の作成も必要になったので、事務の負担が増えています。例えば、通常の入園なら、0歳児は最大で4人ですが、空いている1枠を活用して曜日ごとに異なる家庭のお子さんを受け入れると、保育する0歳児は合計8人まで増える可能性があります。子どもが増える分だけ、事務的な作業は増えています。
週1回でも成長に貢献できる
──週1回の通園でも、子どもの成長や変化につながるのでしょうか?
週1回の保育でも、その日だけでなく生活全体にも良い影響を与えると感じます。2024年度は、母乳じゃないと飲めないお子さんをお預かりしました。お母さんもとても心配されていましたが、ほかの子どもたちと過ごすうちに、哺乳瓶から飲めるようになったんです。
その後は食事もきちんととれるようになり、落ち着いて眠ることもできるようになりました。たとえ週1日であっても、集団の中で過ごすとほかの子から刺激を受けて成長するんです。
また、保護者の方から「生活リズムが整った気がします」という声もいただきました。家庭だけにいると睡眠や食事のリズムがばらつくことがありますが、保育園では保育のスケジュールを決めているため、その影響が家庭生活にも広がったようです。

ワンオペ育児の救いにも
──2024年度に利用されたのはどのようなご家庭でしたか?
2人の0歳児をお預かりしました。一家庭は2歳上のお姉ちゃんと0歳児を育てる専業主婦のご家族です。お父さんは平日ほとんど不在で、日中は完全にお母さんのワンオペ状態となり、かなり疲弊していました。
もう一方はお母さんが育休中で、資格の勉強をする時間が欲しいというお申し込みでした。
──利用家庭の状況はどのように把握するんですか?
受け入れ前に面談をするので、そこで利用の背景や状況をお聞きします。そのうえで登園やお迎えの際にお話しすることで理解を深めていきます。たとえば、お子さんの様子や保護者の話ぶりから、疲れているのではと気づくこともあるんです。こういった場合は、全員で情報共有しチームとして関わるようにしています。
──利用した保護者の反応はいかがでしたか?
「定期的にこの日は預けられるとなって、精神的にすごい負担軽減になった」という声をいただきました。3時間だけでも、お母さんが完全にフリーな時間を作れたことが大きかったそうです。そのうち1時間だけでも睡眠に充てたり、ゆっくりリラックスしたりできたそうで、自分のペースで過ごせる時間の尊さを実感したと話していました。
ただ残念なことに、通常利用の認可定員が埋まってしまったので、2ヶ月間の利用で終了せざるを得なくなったんです。
──空き枠を利用しているとはいえ、保育園との関係が途絶えてしまうのは残念ですね。
こちらとしても、何かつながりを維持したいと感じました。ご本人もまた機会があれば利用したいとのことでした。そのため、お子さんを預かることはできなくなっても、クリスマス会など園の行事をご案内して、希望されれば参加できるようにしていました。
「10時間」では足りない
──「こども誰でも通園制度」を2年間実施してみて、制度に課題は感じましたか?
月10時間では保育士の専門性を発揮しきれないと感じます。上限が月10時間だと、1回2.5時間の場合は月4回、5時間なら月2回しか預かれませんよね。保育士の仕事は子どもとの継続的な関係性のなかで、より効果を発揮できるものなので、子どもの育ちの観点からはせめて月20時間くらいまでは広げてほしいというのが正直なところです。
また、保護者のレスパイトの観点でも、家と園の往復にも時間がかかる場合、1日数時間の利用だと効果を感じにくくなってしまいます。
──2026年度から全国で実施が始まります。運営面での懸念事項はありましたか?
事務的負担の増加です。保育計画の月案なども作成するので、負担は確実に増えています。保育士は常に子どもたちに対応していて忙しいので、事務的負担をなるべく軽減できるフォーマットづくりが必要だと感じています。
また、経済面での課題もあります。空き枠の利用は、認可定員が埋まった場合ほどの収入はありません。関わる子どもの延べ人数が増えて、やることは増えるのに収入面でのメリットは限定的というのが現状です。多くの保育園が前向きに取り組める環境整備が必要です。
保育士の“誇り”高めるきっかけに
──こども誰でも通園制度が実施されることで、保育士にはどんなメリットがありますか?
新制度は保育士が今以上に、誇りを持って仕事ができるきっかけになると考えています。これまで光が当たらなかった「無園児」家庭の子育てに、保育園や保育士が貢献できるということはすごく意義深いことです。
制度の主眼は子どもにあります。単なる保護者のレスパイトではなく、子どもにいろんな人と関わる機会を提供し、成長に貢献します。保育士として在園児だけでなく、地域社会の子どもたち全体のためにも貢献できる。そう考えれば、この制度の意義を理解できるのではないでしょうか。
──地域での役割が増す制度になりそうですね。最後に今後こども誰でも通園制度に取り組む人へのメッセージをお願いします。
開始前は漠然とした不安があるかもしれませんが、新制度も普段の保育の延長線上かなと思っています。子どもを育む、成長を促す、発達を考えるというのは、保育士がいつも頑張っていることなので、利用時間や頻度が変わっても、思っていたほど大変ではないというのが実感です。
むしろ、保育士の仕事がすごく大変で意義深いことなんだということを、改めて認識できる機会になると思います。制度に課題が出てくるかもしれませんが、地域全体で子育てを支える新たな保育のかたちとして、保育士の役割がより一層重要になっていくきっかけになればいいなと考えています。
取材協力:認定NPO法人フローレンス
参考
こども家庭庁|こども誰でも通園制度について













