2000年代、薬科大学や薬学部の新設が相次ぎ、薬剤師数が増加しました。しかし、地方の病院では依然として薬剤師不足が続き、地域偏在は大きな課題となっています。
鹿児島県はその典型です。県内には薬学部を持つ大学がなく、厳しい採用環境に置かれています。同県の川内市医師会立市民病院も例外ではなく、かつて14名いた薬剤師が半減し、深刻な危機に直面しました。

そこから採用活動を抜本的に見直し、現場主導で戦略的に取り組むことで薬剤師不足を解消したといいます。
地方病院の採用困難という課題を、同院はいかにして解決したのか。薬剤部部長の田邉さんと事務部長の米山さんに、その取り組みの裏側を伺いました。
人事任せから薬剤部主導の採用へ
──川内市医師会立市民病院では独自の取り組みで薬剤師不足を解消したと伺いました。その経緯と取り組みについて教えてください。
田邉薬剤師:私が入職した当時(2009年)は薬剤師が十分に在籍しており、採用も比較的うまくいっていました。当時はまだ病棟に薬剤師を配置しておらず、薬局内業務が中心の時代です。その後、病棟薬剤師の配置加算が始まり、診療報酬を算定するために採用競争が加速しました。
当院では薬剤師を7人から14人まで増員し、県内でも一定の存在感を示しました。しかし、安心している間に求人環境が変化し、人員が徐々に減り、最終的には6人まで落ち込みました。

田邉薬剤師:退職理由は他院への転職や家庭の事情などさまざまでした。関係団体からも「なぜここまで放置したのか」とお叱りを受けるほどで……。しかし採用がうまくいかず、現場は疲弊していました。
米山事務部長:当時を振り返ると、設備も老朽化していましたし、当時の薬剤部の主任が退職したことも大きな影響がありました。職場の空気もどこか閉塞的で、「このままではいけない」と強く感じたのを覚えています。
そこで、人事が主導していた従来のやり方を改め、薬剤部が直接採用を担うことにしました。また、即戦力を求める中途採用中心では限界があると判断し、長期的に人材を育てる新卒採用を軸に据えたのです。

──以前はどのような採用活動をしていたのでしょうか。
米山事務部長:ハローワークや大学訪問といった方法に頼り、費用もほとんどかけていませんでした。その方法では次第に採用につながらなくなったんです。
田邉薬剤師:そこでまず「お金をかける」決断をし、就職サイトに求人を掲載しました。私たちは薬を扱うプロであって採用のプロではありません。だからこそ、外部サービスを利用しながら採用の基礎を学び、そのうえで当院らしさを打ち出そうと考えたんです。
──では、薬剤部が採用を担うようになった背景を教えてください。
田邉薬剤師:専門職の採用は非常に特殊です。人事が医師や薬剤師の特性を十分に理解するのは難しいですし、逆に専門職が採用を担おうとしても採用のノウハウがないので、場当たり的なやり方しかできません。
その点、大手薬局チェーンでは薬剤師が自ら採用を担い、魅力をダイレクトに伝えています。当院は採用を人事任せで進めていたため魅力を伝えきれておらず、結果的に人材を取りこぼしていたことに気づきました。
米山事務部長:田邉は我々が発想できないようなことにどんどん取り組んでくれました。例えば、薬剤部のホームページを自作して活動を発信するなど、独自のやり方で採用を推し進めたんです。

採用改革のカギは“数字で示す力”
──これまでお金を使わない採用をしていたとなると、予算の獲得に苦労したのではないでしょうか。
田邉薬剤師:理事会の理解と協力を得るため、何度も議論を重ねました。採用を進めるには“数字で納得いただくこと”が不可欠であり、その点をしっかりと共有したことで、理事の先生方から大きな後押しをいただけました。
薬剤師をはじめとした専門職は、医療倫理観が強い一方で、経営的な数字や戦略に疎い傾向があります。私自身もそうでしたが、その課題意識から医療経営を学び、実際に医療経営士の資格を取得しました。これにより、採用戦略についても数字と理念の両面から説得力のある提案ができるよう努めていました。
──数字で納得してもらうとは?
例えば、「この人数を採用できればこれだけ収益が見込める」というシミュレーションをするんです。採用にかかるコストと、それによるリターンを数字で示しました。実際に採用したら翌年に収益データをまとめ、その結果を持ってまた次の予算獲得につなげています。
このやり方で初年度(2020年度)は7人を採用し、徐々に増員して現在は18人の体制を維持できています。
病院の“ブランド格差”をどう埋めたのか
──初年度から7人も採用できたとは驚きです。就職サイトの求人掲載だけでそこまで結果が出せたんですか?
田邉薬剤師:いえ、当院に大手のようなブランド力がないからか、求人を出すだけでは応募につながりませんでした。そこで、学生に直接アプローチする必要があると考え、九州の学生が集まる就活イベントに出展したんです。そこで薬剤部の価値をイチから伝えようと考えました。
それまでは、県内の人を採用していましたが、そもそも薬剤師の絶対数が少ないので、県外の人を採用しなければ解決できないと思っていて。例えば、福岡県の大学には薬学部もあり人材が豊富だったため、そこから呼び込む戦略に切り替えたんです。
──県外の学生に対して、病院の魅力をどのように伝えたのでしょうか?
田邉薬剤師:単に「うちの病院はここがすごい」といった自慢話ではなく、学生たちの進路の基準となる大病院や保険薬局との比較を織りまぜながら当院で働くメリットを説明しました。
田邉さんが学生に説明した内容の一部
大病院との比較:大病院では業務が細分化される傾向が強い一方で、川内市医師会立市民病院では、調剤・病棟・無菌調製などを短期間でローテーションし、幅広い業務を経験できる
病院と保険薬局の違い:病院では注射調剤やチーム医療など幅広く学べ、学部で得た知識を存分に活かせる。将来保険薬局を志望する場合でも、病院での数年間の経験は大きな強みとなり、転職市場でも高く評価される
田邉薬剤師:そもそも採用は、求職者数という限られたリソースを各病院・薬局が取り合う“相対的な競争”です。だからこそ、自院の強みだけを一方的に語っても意味がなく、ほかとの違いを示しながら比較の中で位置づけることを重視しました。
こうした説明に興味を持ってくれた学生とはSNSなどで継続的に接点を持ち、実際に当院まで見学に来ていただきました。
──結果として何名の学生が見学にいらしたんですか?
米山事務部長:たしか40人くらいです。九州に住んでいても鹿児島に来たことはない学生も多かったので、交通費や宿泊費を病院が負担し、旅行感覚で鹿児島に来てもらいました。
田邉薬剤師:実際に来てもらえれば、他院や保険薬局では経験できない業務や、当院ならではの強みを伝えられると考えていました。
規模が同じ病院であっても、職場の毛並みや空気感はまったく違うものです。だからこそ、現場に足を運び、自分の肌で感じてもらうことに意味があると思っています。
実際に体験に来た学生からは「雰囲気がいい」「居心地がいい」という声が多く寄せられましたし、アンケートでも「現場で体感できたことが最も印象に残った」という回答が一番多く、この“肌感覚”こそが採用の決め手になったと感じています。
──「居心地がいい」と感じた背景には、職場づくりの工夫があるのではと思います。どのような点を意識されていますか?
田邉薬剤師:私が着任した当時は、いわゆる縦社会の部署だったんですよ。急須を温めてお茶を出さないと叱られたという話を聞きましたし、飲み会での上座・下座までも厳格に決まっていました。
そうした業務に不要な慣習は徹底的に取り払い、意見を出しやすい風通しのよい職場づくりを意識しています。こうした積み重ねが、安定した採用につながったのだと思います。
人が育ち、人が残る制度づくり
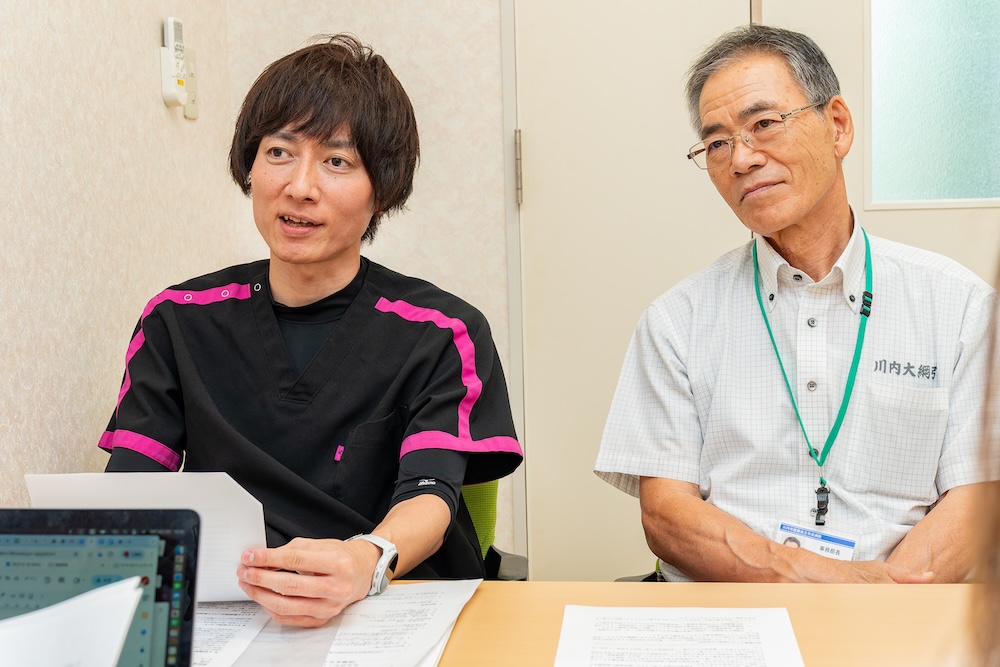
──冒頭で「長期的に人材を育てる新卒採用を軸に据えた」と伺いました。入職した人の成長は、具体的にどのように支援していますか?
田邉薬剤師:プリセプター制度を導入して、新人には先輩がマンツーマンで指導にあたっています。まずは一般的な業務を担えるジェネラリストを目指し、そこからは個々の特性に応じて強みを伸ばす教育をしていきます。
得意な分野を伸ばしてあげれば自信につながりますし、モチベーションも上がりますよね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを立て直したマーケターの森岡毅さんも著書で「成果や結果は強みから生まれる」と述べていて、私もまさにその考えです。
その結果として、当院では専門薬剤師や認定薬剤師の資格を取得する職員が多く育っています。こうした姿を目にすることで、後輩も「自分も挑戦してみよう」と思える、良い循環ができているのではないでしょうか。
米山事務部長:学びの支援という観点ですと、資格取得のための費用はもちろん、資格の更新費用も病院が全額負担しています。また、社会人になってからも大学院に進学できるよう支援体制を整え、費用を全額補助しています。
──大学院の費用まで補助するんですか、かなり手厚い支援ですね。
田邉薬剤師:現場に出ると臨床課題に直面し、論理的に解決する力の必要性に気付くことがあります。その結果、臨床と研究を行き来するハイブリッドなキャリアを志す人も少なくありません。そうした職員を支える意味でも、大学院進学を含めた学び直しの制度は大切だと思います。
このような制度の効果もあってか、離職率はかなり低いです。当初は、医療業界全体の離職率を見ると年間に2人程度辞めるのは仕方ないと考えていましたが、実際はそれよりも少ないですね。
米山事務部長:5、6年生を対象とした給付型奨学金制度があることも離職をおさえられる理由の一つです。返済義務が5年で免除されるため、そのタイミングで離職する人は数人程度いますが、それでも残ってくれる人のほうが圧倒的に多いです。
──5年というと、業務に慣れて転職を考えるタイミングなのでしょうか?
田邉薬剤師:ある程度経験を積むことで自信がつきます。これまで経験のない分野に挑戦したい、スキルアップしたいという気持ちが芽生えるのは当然のことです。そういった別の環境を経験させながらも定着率を上げる一手として、今年から出向制度と研修制度を導入しました。
──どちらに出向されるのでしょう?
田邉薬剤師:地域包括ケアや慢性期病床を持つ病院、さらには在宅医療の現場です。出向する職員は幅広い業務を経験できますし、他院を含めた病院全体の人材基盤を支えることができる仕組みです。
この制度が安定すれば、たとえ産休・育休などで職員が抜けたとしても出向者を戻すことで現場の人数を維持できると考えています。
──出向期間はどのくらいですか?
田邉薬剤師:基本は1ヶ月ずつのローテーションで回そうと考えています。短期間であれば“研修”として受け入れられますが、長期になると「行きたくない」という声が出てしまいますし、離職率が上がるリスクもあります。
──“隣の芝生は青い”とよく言いますが、今の環境を見つめ直すことにもなりそうですね。
田邉薬剤師:そうなんです。当院しか経験していない人は、「もっと輝ける環境があるのでは?」と思いがちです。実際に他施設での勤務を経験すれば、当院の良さを再認識します。
米山事務部長:当院は地域医療支援病院としての役割を担っています。ですから、自院だけで完結させるのではなく、こうした仕組みを導入しながら「地域全体の医療を支えていくんだ」という意志を持つことが、今後ますます重要になっていくと考えています。
改革を進めた薬剤部長の原動力

──田邉さんの採用に取り組むモチベーションや、病院を支えたいという思いはどこから生まれているのでしょうか。
田邉薬剤師:病院への貢献というより、“学び続けたい”という思いが強いです。学生のニーズと僕らのニーズは本質的に同じだと思います。新しい知識を得たい、最新設備のある環境で働きたい、プライベートも大事にしたい、そういう思いは誰にとっても変わらないと思うんです。そのためにこれまで努力してきた、というほうが正直な気持ちです。
──では、市民病院で仕事を続けてこれた理由は?
田邉薬剤師:一言でいうと、反骨心です。「神の手」のように、その人にしかできない特別な医療は確かにありますが、薬物治療に長けた人がいれば、世界中どこでも標準的なことができます。私にとっては川内でも標準の治療が受けられることがすごく魅力的なんです。
──「地方でも標準的な医療を」という思いですか?
田邉薬剤師:はい。とくにこの地域は身体の不自由な高齢者が多いですし、慣れ親しんだ地元で治療を受けたいという方もたくさんいらっしゃいます。大学病院なら当たり前にできることを川内という地方で実現する、そこにこそ夢があると思っていますし、当院で薬剤師として働くことに関心を持ってもらえたらうれしいです。
取材協力:公益社団法人 川内市医師会立市民病院











