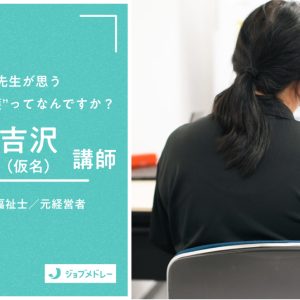こんにちは。なるほど!ジョブメドレー編集部の松田です。先日、介護職員初任者研修を修了し、介護の現場についてもっと知りたいと思うようになりました。
なかでも気になっていたのが「訪問入浴」です。利用者宅に浴槽を持ち込んで入浴をサポートする仕事ですが、実際の現場はどのように支援しているのか、見えない部分が気になりました。
そこで今回は、アサヒサンクリーン株式会社の訪問入浴体験会に参加し、実際の流れを教えてもらいました。
アサヒサンクリーンはこんな会社

1974年(昭和49年)、日本で初めて「巡回入浴サービス」を事業化した訪問入浴のパイオニア的企業。訪問入浴事業所数は全国271箇所(*1)。同サービスにおける国内シェアは30.1%(*2)を占める訪問入浴事業のほか、介護施設の運営や、福祉用具のレンタル・販売など、総合的な介護サービスを全国で展開中。
訪問入浴ってどんな仕事?
訪問入浴介護とは、職員が専用の浴槽を利用者宅に持ち込み、入浴の介助をおこなう介護保険サービスです。
自身での入浴が困難な人や、医療的なケアが必要な人を主な対象としており、要介護度3以上の人が約9割を占めています。
多くの場合、看護師1名と介護職員2名のチームで訪問し、1件あたりのサービス提供時間は45〜60分程度です。そのうち、実際にお湯に浸かる時間は15分程度で、残りの時間は浴槽の準備や片付け、利用者の着替え、看護師によるバイタルチェック(体温・血圧測定)などに充てられます。
訪問入浴の体験会で利用者役になってみた
体験会では、浴槽の搬入から片付けまでの一連の流れを見学しました。同社の訪問入浴は1件あたり45分で以下の流れでおこなうそうです。
アサヒサンクリーンの訪問入浴の流れ
準備:15分
- 訪問あいさつ・手洗い消毒などの感染予防
- 看護師によるバイタルチェック
- 入浴機材搬入
- 衣服の着脱介助
入浴:15分
- 浴槽への移動
- 洗顔・洗髪
- 洗身
- リラックス時間
片付け:15分
- ベッドへの移動
- 薬剤の塗布
- 衣服の着脱介助
- バイタルチェック
- 撤収
同社では利用者と同性の職員が担当する同性介助をおこなうため、チームは男女混合で構成することが多いそうです。例えば利用者が女性の場合、女性スタッフが洗身を担当し、その間に男性スタッフはベッドメイキングをおこなうなど、チーム内で役割を分担して対応しています。
機材の搬入・組み立て
まずは搬入です。訪問入浴で使用する浴槽は、最も大きいパーツでも10kg程度に分割できるよう設計されており、3人で分担して運びます。

スタッフによると、搬入時に最も気を使うのは「廊下の幅」と「天井の高さ」だそうです。狭い廊下では浴槽を縦にして運んだり、天井の照明に当たらないよう注意したりと、運搬にも工夫が必要とのことでした。
ベッドから浴槽への移乗
訪問入浴のデモンストレーションが始まり、利用者役を体験させていただきました。

まずはベッドの高さを調整します。実際の訪問では、ベッドを上げる前に衣服の着脱介助をおこなうとのことでした。
準備を終えたらベッドから浴槽への移乗です。移乗は「マルチ担架シート」という、寝たまま移動できる専用のシートが使われます。

「これからシートを入れますね」と声をかけられ、移乗の準備が始まりました。3人のスタッフの補助のもと、ベッドと体の間にシートを滑り込ませます。



スタッフに補助されながら体を転がすと、あっという間に移乗の準備が整っていました。この間わずか30秒ほど。プロの手際の良さとチームワークに驚きました。続いて、シートを使って浴槽に移動します。


掛け声と同時にシートごと体を持ち上げられます。大きな揺れや窮屈感はなく、気づいたときには浴槽のなかでした。

スタッフによると、訪問入浴ではベッドと浴槽の高さを必ず合わせる、体重が重い場合は橋のようにスライドボードを渡して滑らせるなど、スタッフの負担軽減と利用者の安全を両立する仕組みが徹底されているそうです。
入浴
訪問入浴で使われる浴槽には、事故防止のためのネット状のシート(ハンモック)が取り付けられています。

利用者はこのシートに寝た状態で、ゆっくりとお湯に浸かっていきます。体験会ではお湯を使いませんでしたが、実際の入浴ではネットを下げている間に体が冷えないよう、シャワーでお湯をかけ続けるそうです。また、お湯の温度にも工夫があるといいます。
「急激な温度変化による心臓への負担を避けるために、最初は38度くらいのぬるめのお湯を張ります。洗髪や洗顔をしている間に40〜41度の適温まで徐々に上げていくんです」
洗髪・洗身
洗髪や洗身でも、丁寧な対応が印象的でした。シャワーのお湯が熱くないか、スタッフが自分の指に当てて確認し、洗髪時は顔にお湯がかからないよう徹底的にガードするそうです。
また、「背中を洗うので右側に体を傾けてくれますか?」「耳に入った水を拭きますね」など、必ず「今からする行動」と「その理由」を説明してくれます。細かい声かけや所作、専用の道具など、随所に利用者への気遣いが感じられました。

入浴時間
洗髪・洗顔・洗身を終えたら、ゆっくりと浴槽に浸かるリラックスタイムです。「お湯加減いかがですか」「気持ちいいですか」と、常に快適さを確認するスタッフの声かけも印象的でした。これについて、スタッフはこう話します。
「訪問時間は45分ですが、準備と片付けで30分を使います。残りの15分でいかに満足してもらうかが、腕の見せ所なんです」
実際の現場では、利用者の好みに合わせた入浴剤を使用したり、静かにお湯を楽しむ方とはゆったり過ごしたり、会話を楽しみにしている方とはおしゃべりをしたり、一人ひとりに合わせた時間を提供しているそうです。

現場スタッフに聞いた「訪問入浴のリアル」
体験会終了後、スタッフに訪問入浴に関するいくつかの疑問をぶつけてみました。

——体験中、スタッフ同士の「次、背中いきますよ」「お湯上げますね」といった声かけが印象的でした。訪問中はどんなことを意識されていますか?
「そうですね、やはりチームワークでしょうか。例えば移乗のときに『1、2の3』の掛け声でタイミングを合わせないと、スタッフが腰を痛めてしまったり、利用者さんに不安を与えてしまったりすることもあります。だからこそ、お互いに声をかけ合って息を合わせることを大切にしています」
——未経験でも訪問入浴に挑戦できますか?
「うちに入社される方の半分くらいは、無資格・未経験から始めていますよ。スタッフ同士の連携が重要な仕事なので、経験や専門知識より『チームワークを重んじること』のほうがこの仕事では大切ですね。
技術については、研修でしっかり学べますし、現場には必ず3人チームで出るので、未経験でも安心して始められる仕事だと思います」
——「訪問入浴」とネット検索すると、「きつい」「やめとけ」と表示されますが、やはりきつい仕事なんでしょうか……?
「1日に7〜8件を回り、エレベーターのない高層階に訪問することもあります。なので身体的な負担は確かにあります。過去に入社された方のなかには、短期間で離職してしまう方もいらっしゃいました。
一方で、長く続く方は10年、20年と続けています。利用者さんの多くは、1週間から2週間に一度しかお風呂に入れません。ですから、訪問入浴の日を心待ちにしてくださるんです。身体的な大変さはありますが、やりがいの大きい仕事だと思いますよ」
体験してわかった訪問入浴という仕事
今回の体験をとおして感じたのは、訪問入浴は単なる「体を洗う介助」ではなく、くつろぎの時間を提供し、心身のゆとりを取り戻してもらうためのケアだということです。一見すると機材の搬入や手際の良さといった作業に目がいきますが、その裏側には、利用者一人ひとりに合わせた工夫と技術が丁寧に積み重ねられていました。
次回の介護体験会は2025年11月26日、ジョブメドレースクール高田馬場校で開催されます。興味のある方はぜひ参加してみてください。
<第2回 介護体験会 概要>
日時 : 2025年11月26日(水)17:30~18:30
場所 : ジョブメドレースクール高田馬場校(東京都新宿区高田馬場3-3-1 ユニオン駅前ビル6F)
参加費: 無料
服装 : 自由
対象 : 介護業界の仕事に少しでも興味がある方、未経験者歓迎
内容 : 訪問入浴のデモンストレーション見学、現場スタッフへの質問会など