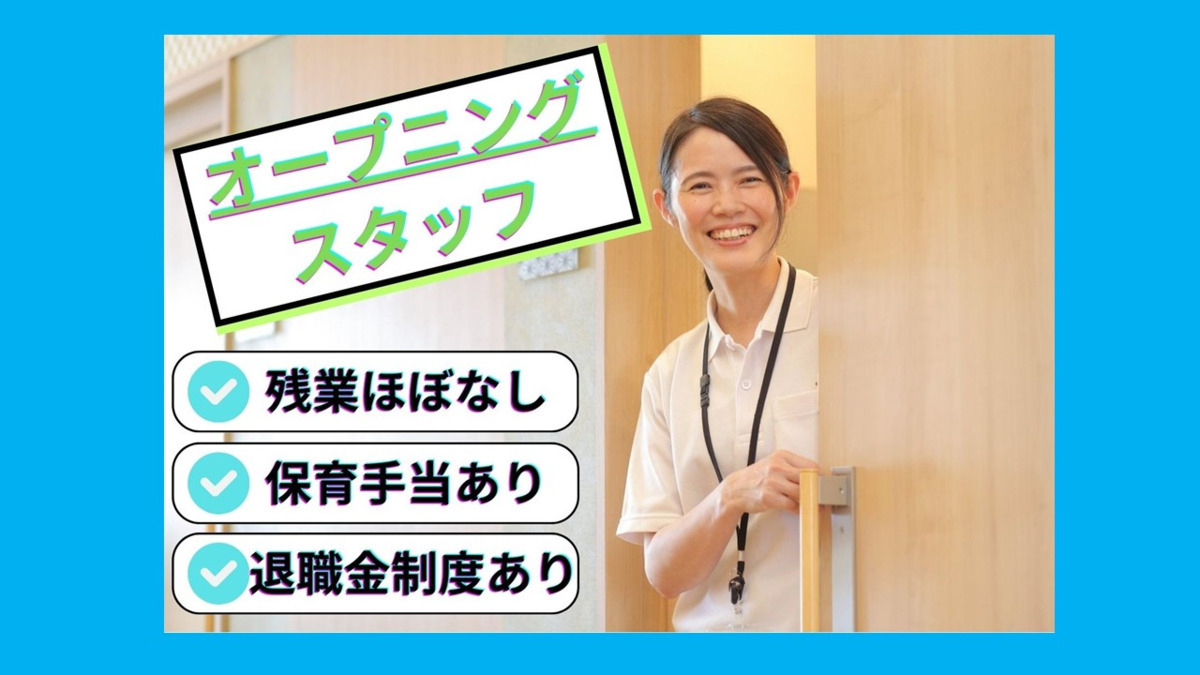私たちにとって理想の死とは?
「みなさんはどのような人生の最期を迎えたいですか?」という質問に対して、65%の人が「突然死」と答えています(第一生命経済研究所資料参照)。
その理由は、「家族に迷惑をかけたくないから」となっています。
在宅介護は本当に大変なことであり「家族に迷惑をかけるくらいなら、突然死したい」。そんな切ない想いがにじみ出ています。
また「死への心配なことは?」という質問に対して、男性は「自分のやりたいことができずじまいになること、やり残した仕事があること」「残された家族が経済的に困るのではないかということ」といった回答が女性よりも多い結果となっています。
また、女性は「家族や親友と別れなければならないこと」「残された家族が精神的に立ち直れるかということ」といった回答が男性を大きく上回る結果となり、残される家族のことを経済的に心配する人は男性に圧倒的に多く、精神的な立ち直りを心配する人は女性に多いという結果となりました。
どちらにしても死を考えた時に、自分よりも残された家族のことに関して安心感を得ることが理想の死に近づくのだと考えます。
看取りって何??
死を迎えるのは、病院がいいですか? 住み慣れた場所がいいですか? この質問には多くの方が「住み慣れた場所がいい」と答えると思います。そこで、特別養護老人ホームなどの施設では多く看取り介護を行っています。
医療体制が病院と比べると不十分な施設の場合、病状が悪化したときは病院に搬送することになりますが、それでも慣れ親しんだ場所である施設で最期を迎えたいという利用者様の希望が多く、看取り介護が注目されています
看取り介護の種類
介護現場における「看取り介護」には、どのような種類があるのでしょうか? 以下で代表的な例を見ていきましょう。
(1)精神的ストレスの緩和
死を感じると誰もが不安やさみしい気持ちになってきます。また、できなくなることが増えたり、友人知人も亡くなることが増えたりと、喪失体験から大きなストレスを感じる方が多いです。
そこで、利用者様に対して、相手を理解するような声掛けをしたり、手や身体をさすったりと、優しいコミュニケーションをとることで少しでもストレスを減らせるように努めることが大切です。また、本人の希望を聞き出し、極力希望に沿った生活を送れるよう支援をしていきます。
(2)身体的ストレスの緩和
体調が今以上に悪くならないように、日々観察を行い、とくにバイタルの変化の管理をしていきます。また、死を間近にすると趣味嗜好が変わることもあるため、利用者様の希望を引き出すために声掛けをします。
たとえば、食事の味付けが変わったり、水分の温度や種類の好みが変わったり、運動や入浴をしたがったり嫌がったりといろいろな変化が出てきます。
とくに、寝たきり状態になることが多いため、床ずれ(褥瘡)を予防するために定期的に体位変換を行ったり、クリーム等で皮膚を保持したりして、身体に負担を軽減するよう気をつけながら介護をしましょう。
(3)家族の方に対するケア
利用者様本人はもちろん、利用者様のご家族にもこまめに情報共有をして、いつ最期を迎えるかもしれないのか、またそのために何をしていくのか、しっかり説明をしてご家族の納得を得ることが大切です。
冒頭にも書きましたが、利用者様自身は「家族に迷惑をかけたくない」と考えています。逆に家族は、利用者様(家族)に充実した人生の最期を送ってほしいと考えています。このギャップを埋めるのも介護職として大切な役割です。
利用者様が亡くなった後に重要なグリーフケアとは
グリーフケアとは、利用者様(お父さん・お母さん)などの身近で大切な人を亡くし、大きな悲しみを感じている人を支えるためのケアです。
介護現場におけるグリーフケアでは、利用者様がどのような介護を受けながら生活していたのかお伝えし、ご家族が納得され、精神的にも肉体的にも、利用者様の死を受け入れ、立ち直り、正常な日常生活へ戻っていくことを支援していきます。
最初はどうしても死を受け入れられず、泣いて過ごすご家族も多いと思います。そのご家族に対して有効なのは写真や映像です。
利用者様のいろいろな場面の写真や映像を撮りためておくことで、ご家族も癒されていきます。グリーフケアのためにも写真や映像を残していきましょう。
利用者様が亡くなるまでの介護職としての心構え
介護職は専門職です。利用者様が亡くなることで精神的なストレスを抱えすぎると仕事を永く続けることはできません。
とは言いながらも「死に対して慣れるのもどうなんだろう…?」と思う方も多いはず。
そこで利用者様がどう幸せな最期を送ることができるのかを考え、そのプランに基づき実行する。そして利用者様やご家族が、納得して感謝の気持ちを持って最期を迎える。これを私たち介護職がプロデュースするという気持ちで介護をすることが大切です。
最後に
マザーテレサはこう言っています。
『人生の99%が不幸だとしても、 最期の1%が幸せならば、 その人の人生は幸せなものに変わる』
看取り介護はこの1%をプロデュースすることが仕事です。死に直面するからこそ、人を幸せにすることができる看取り介護はやりがいある仕事だと私は思います。
最後にそれぞれの最期を迎えた利用者様のエピソードをご紹介させていただきます。
(例1)釣りが大好きなAさん
Aさんは昔から大の釣り好き。昔から川で魚を釣るのが大好きで、休日になると家族を連れて川に魚釣りに行っていました。
それから20年。認知症の症状が出たため、介護施設にへ入所した直後、身体に末期ガンが見つかり、余命は3か月となりました。
医師は絶対安静と言いましたが、本人は「どうしても最期に川に魚釣りに行きたい」と外出を希望されました。
医師は反対しましたが、介護職としてAさんの意思を医師に伝え、医師を納得させることに成功し、Aさんとご家族の最期の魚釣りに行くことができました。
孫に餌のつけ方や竿の振り方などを教えるAさんはとても活き活きとされ、魚は釣れなかったものの「最期の願いを叶えてくれてありがとう」と涙を流しながら笑っていました。
それからAさんはご逝去されましたが、ご家族も最期の思い出を作ることができ、笑顔のお葬式を迎えることができました。もちろん、遺影は魚釣りの写真でした。
(例2)スイーツが好きなBさん
Bさんはスイーツが大好きで昔からお菓子やケーキ、アイスを食べていました。その後、糖尿病を発症し、入院。退院したものの高齢ということもあり、家に帰らず介護施設に入所されることになりました。
医師からは糖質制限が出ていて、スイーツが大好きなのに食べられませんでした。
それから数年して、病気を発症。寝たきり状態になりました。ベッド上でBさんは「モンブランが食べたい」とずっと言っていました。
余命宣告が出て、数日。また「最期にモンブランが食べたい」と言うので、医師に確認のもとモンブランを食べていただこうという話になり、ご家族に相談しました。
すると「もしよければ私がそのモンブランを作っていいですか?」とご家族が申し出てこられたので、施設の調理室を使い、手作りモンブランをみんなで作りました。
完成後Bさんに食べていただくと「おいしい!こんなおいしいモンブランを食べられて幸せ!」と涙を流されました。もちろん、ご家族も涙が止まりませんでした。
それからご逝去されるまで約1週間。
ずっとBさんは「あのモンブランはおいしかった」と言っていました。ご逝去されて、Bさんの棺の中にご家族はモンブランを入れて、「あの世でもおいしいスイーツを食べてね」と言ってお見送りされました。
利用者様の最期をいかに幸せなものにするかというのが介護職の役割です。利用者様やもちろん、ご家族の想いを実現し、お互いに納得した最期を迎える支援をする。これが看取り介護の根底なのだと思います。