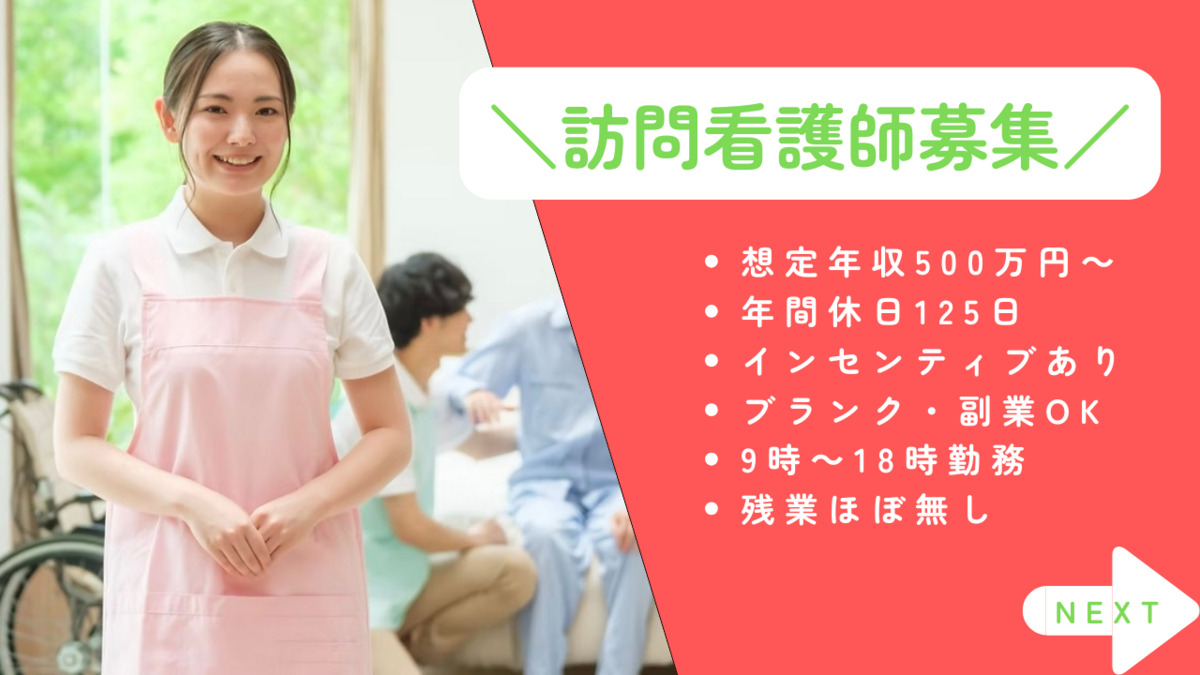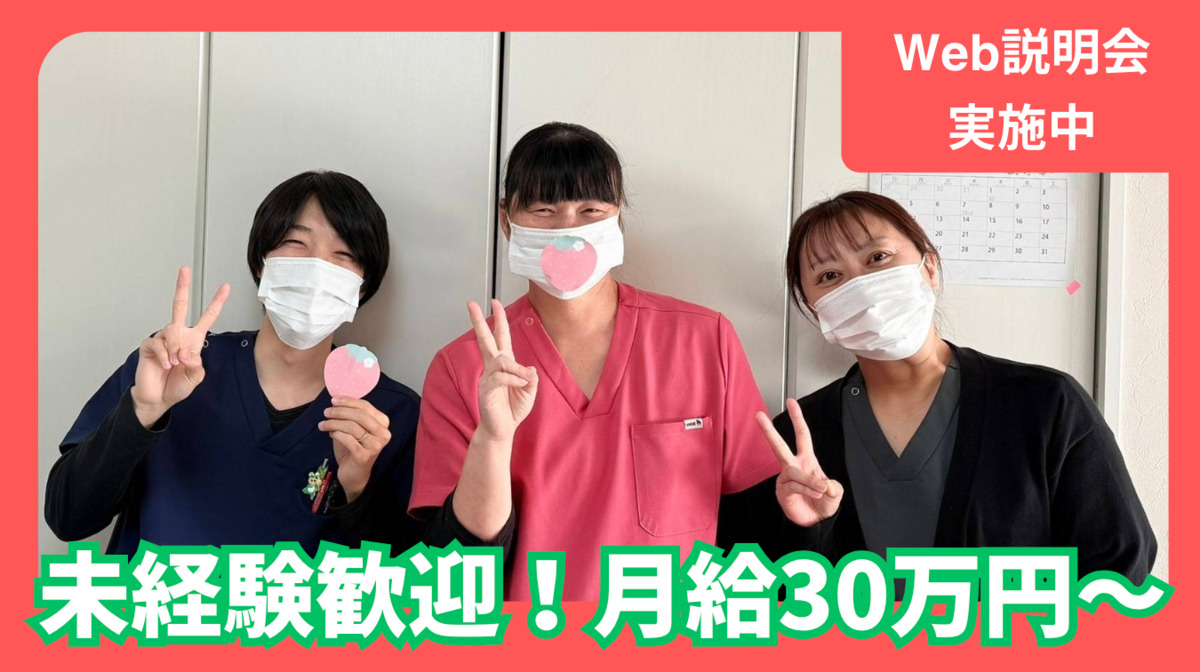慢性期とは
現代の日本では、欧米化した食生活や車社会による運動不足、喫煙などによる生活習慣病にともない、「高血圧症」「糖尿病」「高脂血症」の慢性疾患にかかった方が脳卒中等を発症し、寝たきりになる率が上昇しています。
国民医療費も1978年に10兆円を超えて以降、毎年1兆円ずつ増加しているうえに、人口構造はつぼ型であり、少子高齢化は社会保障制度にも大きな影響を与えています。
日本の医療は「1.高度急性期」「2.急性期」「3.回復期」「4.慢性期」の4つの機能に分けられ、高齢化率の上昇にともない、回復期から慢性期の病床数の不足が指摘されています。
この結果、厚生労働省は「病院完結型」の医療から、地域全体で治し、支える「地域完結型」の医療への転換を求めています。
慢性期のとらえ方はさまざまですが、これらの背景を踏まえたうえで、ここでは重点的に療養型施設について述べていきますね。
慢性期施設って?
慢性期の入院施設として「療養型病院」があり、医療措置の必要な「医療療養」と要介護認定の必要な「介護療養」に分けられます。
しかし、高齢化が進んでいることと、看護師不足などを理由に「介護療養」は廃止が決定し、現在、大幅に減少しています。(新設は認められていないこともあり、私の近隣市では一施設のみです。)
医療療養病床の定義は、病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものとされています。
つまり、急性期での治療後も、喀痰(かくたん)吸引のような医療措置が日常的・継続的に必要な患者の入所を対象としているということですね。
また、厚生労働省は規定により、日常生活動作(ADL)の自立度を以下の3つに分けています。
<区分3>
24時間持続点滴や中心静脈栄養が必要か、人工呼吸器を装着している患者が対象。
<区分2>
経管栄養や気管切開などのケアが必要か、神経難病や肺炎の患者が対象。
<区分1>
区分2・3に該当しない患者が対象。主に老人保健施設など介護施設に入所している。
慢性期施設の患者の半数は脳卒中疾患であり、24時間体制での管理だけでなく、看取り・ターミナルケアも必要とされています。また、看護師の人員配置は20対1であり、患者の平均在院日数は170日前後と示されています。
慢性期の勤務形態は?
今、施設形態に関係なく全国的に2交代勤務者が増えています。働き方改革の後押しもあり、同施設内で2交代と3交代勤務者が混在している施設も多いのが現状です。
急性期では、休憩をとることが難しいときもありますが、慢性期では、平均16時間勤務で仮眠は1時間半から2時間を時間どおりにとれることが一般的です。
今回の執筆にあたり、療養型に勤める友人たちに勤務形態と夜勤手当を尋ねました。回答は全員2交代勤務であり、夜勤手当は12,000円~15,000円/回(地方中堅都市)でした。
慢性期に関わる職種って?
医師、看護師はもちろんですが、薬剤師や管理栄養士の比重も大きく占めています。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士やソーシャルワーカーも加わり、チーム医療を推進して在宅復帰機能強化加算を取っている施設もあります。
また、最近は、患者だけでなく家族のQOLも考慮し心理療法士を採用している施設もあります。これは、その施設によって在宅か見取りかの方針によって大きく変わります。
慢性期の看護って?
前述したように、慢性期施設の患者の半数は脳卒中疾患であり、長期にゆっくりとターミナルに向かっています。その上、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、心疾患、慢性呼吸器疾患、癌などの疾患も複合しています。
残りの人生を疾患と共に生きることを余儀なくされている患者に、看護師のできることはたくさんあります。
具体的には、疾患の悪化の早期発見、合併症や廃用症候群の予防、ターミナルケアなどの視点から、ポジショニングや口腔ケア・吸引処置、経管・経腸・静脈栄養の管理だけでなく、丁寧に全身の状態観察(バイタルサインだけでなく、褥瘡好発部位の観察や点滴挿入部位の発赤の有無、口腔内環境の観察、排泄の性状など)を看護実践します。
私はすべての場面において、最も重要なのは“気づく”ことだと思っています。
言葉として患者からの表出が少ない、または少なくなっていく中で、「いつもより眉間が険しいな」「呼吸がいつもと違う」などの気づきが一人ひとりへの看護の始まりだと思います。
そして、24時間患者の一番そばにいる看護師だからこそ、小さな残存能力に気づくことができます。その気づきを家族だけでなく、多職種に伝え喜びを分かち合い、最期の生活をどのように過ごすのか一緒に考えていく…。
慢性期の看護は、どれだけ小さい気づきができるかで変化していく場だと思います。
時々「人工呼吸器が苦手だから、療養型に行きたくない」という看護師の声を聞きます。私も医療機器は苦手です。しかし、医療機器は以前より簡単に扱えるようになってきています。
そして、療養型では患者が安定している状態で人工呼吸器を装着しているので、「離れていても異常があればアラームが教えてくれるから安心」程度の気持ちでいいと思います。
人工呼吸器を扱えるかどうかは、単に1つのスキルでしかなく、看護の価値とは関係していないので、安心してください。
慢性期の看護師にはどんな人が向いている?
慢性期の施設は、1日の看護業務がルーチン化されている施設がほとんどです。そのため、急性期や回復期などの医療機能の施設より、残業が少なく家庭と仕事を両立しやすい環境であると思います。
また「一人ひとりへの看護が充分に行えていない」とジレンマを抱えている看護師にとって、対象患者の特性上、ナースコールに中断されることなく、個別に関わることができる時間は多いと思います。
そして、例えるならば、乾いたスポンジに少しずつ水が浸み込むように、家族が患者のターミナルを少しずつ少しずつ受け入れ、良い時間を持てるように気長に関わることもできます。訪問看護師はまだハードルが高いけれど、家族看護に興味があるという方にも向いていると思います。
・療養病床・慢性期医療の在り方の検討に向けて~サービス提供体制の新たな選択肢の整理案について~.厚生労働省
・厚生労働統計協会(編).(2017).国民衛生の動向・厚生の指標 増刊・第64巻第9号 通巻第1006号.厚生労働統計協会