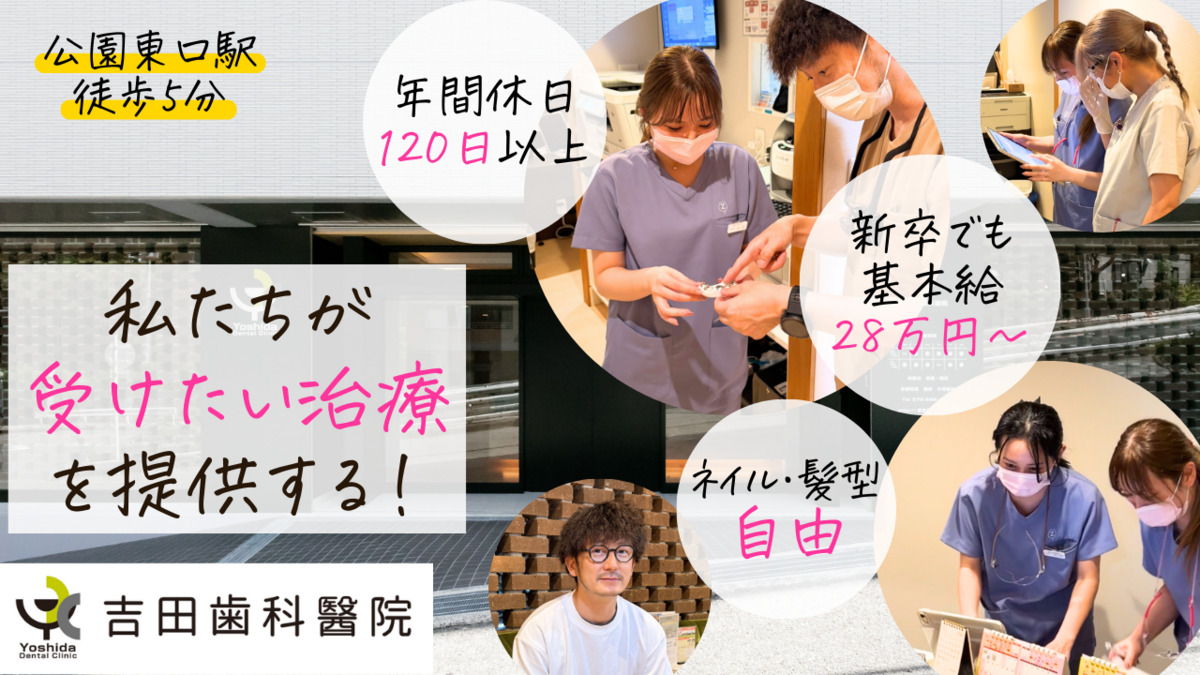看護師の母の姿を見て育った子ども時代

—歯科衛生士になろうと思ったきっかけはなんですか?
中鉢さん:わたしの母親は看護師なので、子どもの頃から漠然と自分も医療従事者になるものだと思ってました。
看護師については、母の口から良い面も悪い面も聞く日々だったので、わたしの中ではそこまで良い印象を持っていませんでした。
母は10年以上のブランクから復職したということもあって、新しい医療の知識についていくのが大変そうな姿をすぐ近くで見ていたからかもしれません。そこで「看護師も楽じゃないよなぁ」と思って進路に悩んでいました。
当時は「歯科衛生士」という職業のことをぜんぜん知らなくて、なぜかというと、わたしは虫歯がぜんぜんないんです(笑)。子どもの頃に小さな虫歯で1回だけ歯医者さんに行ったのが最後です。
歯磨きをきちんとしてくれたり、甘いものを食べないような食生活を身につけさせてくれたり、地道な努力をしてくれた母のおかげですね。
歯科衛生士という職業に出会ったのは高校生のはじめの頃です。親知らずが腫れてしまってすごく痛くて、ほぼ人生初となる歯医者さんデビューをすることになったんです。
そこで働いていた歯科衛生士さんが40代の大ベテランの方だったんですけど、いろいろな話を聞くなかで、「40歳になっても1つのキャリアを積み上げられるってすごいな」と思いました。
女性は結婚や出産、旦那さんの転勤など、何かしらの要因で生活スタイルが変わってしまうことがあると思うんですけど、歯科衛生士は生活の変化があっても働き続けられるというところに魅力を感じて、歯科衛生士になるための専門学校に入学しました。
専門学校を経て、歯科衛生士の道へ
—専門学校ではどんなことを学ぶんですか?
一般歯科のことから「レントゲンとはなんぞや」という放射線学のことまで、3年間でたくさんのことを勉強しました。当時は「これ必要かな?」と思うこともあったんですけど、働いてみて「やっぱり必要だったな」とわかりました。
専門学校では、2年生の後半に国家試験の模試が始まります。大学受験と同じようなかたちで過去問を解かされて、「あと1年しかないけど大丈夫!?」という感じでお尻を叩かれてましたね(笑)。
歯科衛生士の国家試験は午前と午後に分かれて1日で筆記試験を受験するんですけど、ふだんは国家試験専門の参考書を使って勉強をしていました。
—歯科衛生士の就活はどのような感じなんですか?
3年生の夏頃になると、みんな「就活どうしようかな?」と考えはじめます。歯科衛生士の就活には、学校に届く求人票や合同説明会、就活フェアなどいろいろな方法があります。
学校に届く求人票経由で就職する子はあまりいなくて、実習先にそのまま就職するパターンと歯科衛生士の就職サイトをつかって就職するパターンが多いです。
インターネットで求人を見て、条件に合ってると思ったら見学に行って、クリニックの1日を見させてもらって、合う合わないを判断するというかたちです。
—職場選びで重視したポイントはありますか?
わたしだけではなく、自分が希望する診療科に行けるかどうかということを気にする人が多いと思います。一般歯科という広いくくりの中でも、矯正歯科や口腔外科、予防歯科などいろいろあって、今後のキャリアに響いてくるからです。
ファーストキャリアとしては、はじめは幅広くやっていこうということで、一般歯科の中でもとくに予防歯科に力を入れている歯科医院が人気です。
わたし自身は、一般歯科から小児歯科、入れ歯治療、セラミック治療まで、やっていない治療はないというくらい幅広い治療をおこなっているクリニックに就職しました。
—夏頃に就活をはじめて、いつ頃に決まるものなんですか?
人によって分かれるんですけど、2月に歯科衛生士の国家試験を受けて、3月になるまで合否がわからないんですよね。
そうなると、夏からけっこうなタイムラグがあるので、先んじて就職を決めてしまうと「落ちた時にどうしよう…」という気持ちがあって、3月の合否を待ってから就活をはじめるグループがまず1つ。これは一番少数派です。
それ以外は年明けから動く人が多いと思います。11〜12月までは実習があってみんなヒーヒー言っているので、実習が終わってから本格的に就活をはじめて、だいたい1・2月で就職先を決めている印象です。
また、大学病院や区役所への就職を目指している人たちは、エントリーシートの提出期限の関係で夏頃から早めに動いていました。わたしもわりと早いほうで、9・10月で動いて、11月頃には就職先が決まっていました。
国家試験に合格して、専門学校の卒業式が終わったあとはやることがないので、遊んだり、旅行にいったりする人もいると思うんですけど、わたしは「ちょっと仕事に慣れておこうかな」と思って、就職先のクリニックで歯科助手としてアルバイトをしていました。
歯科衛生士の1日とキャリアプラン

—歯科衛生士の1日の流れを教えてください。
9時半に制服に着替えて出勤。出勤後は看板を出したり、入り口の掃き掃除をしたり、室内の電気や各医療機器の電源を入れたりして患者さんを受け入れる準備をします。
その後、治療器具・歯科材料を確認したり、当日来院する患者さんのカルテをチェックしたりしておきます。
オープン前にそれらの準備を終えて、10時になったら午前診療をやりつつ、お会計をしたり、患者さんの対応をしたり、空き時間に治療器具の洗浄や滅菌、翌日の準備を並行して進めていくようなイメージです。
午後は診療をやりつつ、歯科技工所さん・歯科材料屋さんの対応や発注業務をおこないます。診療が終わると、ユニット周りを全部分解して洗います。最後に翌日使う器具の準備を確認して、終わったら帰るというかたちです。
人員体制は院長が1人と副院長が1人。この2人が常勤のドクターです。あとは常勤の歯科助手が2人、わたしともう1人の歯科衛生士の6人体制でした。その他、週によって代診に来る先生が2人と月に1回来る矯正の先生がいました。
うちのクリニックはすごく仲が良くて、みんなフランクに話していたので、とくに人間関係で悩みを抱えるようなことはなかったですね。
—最後に歯科衛生士を目指す人へのアドバイスをお願いします。
専門学校で使っている教科書があるんですけど、そこに載っている「正常な歯周組織の構造と機能」という項目は絶対に復習し直して、プロフェッショナルになっておいたほうがいいです。
やっぱり正常な組織がわからないと病的な組織がわからないし「なぜ歯周病になるのか」という組織学的な話がわかっていないと、どんなにテクニックを身につけても話にならないなと私自身も痛感しました。
学生のときは組織図を覚える意味もぜんぜんわからなくて、みんな「丸暗記すればいいや」みたいな感じでやっていたんですけど、実際に歯科衛生士になってからめちゃくちゃ使います。ここはみんな「ちゃんと勉強しておけばよかった…」と後悔して、教科書で勉強し直す項目第1位ですね(笑)。
国家試験の勉強と関係なく、今後、歯科衛生士としてステップアップしていく中で避けて通れない知識なので、ちゃんと理解できている人はすごく強いと思います。
—中鉢さん、ありがとうございました!