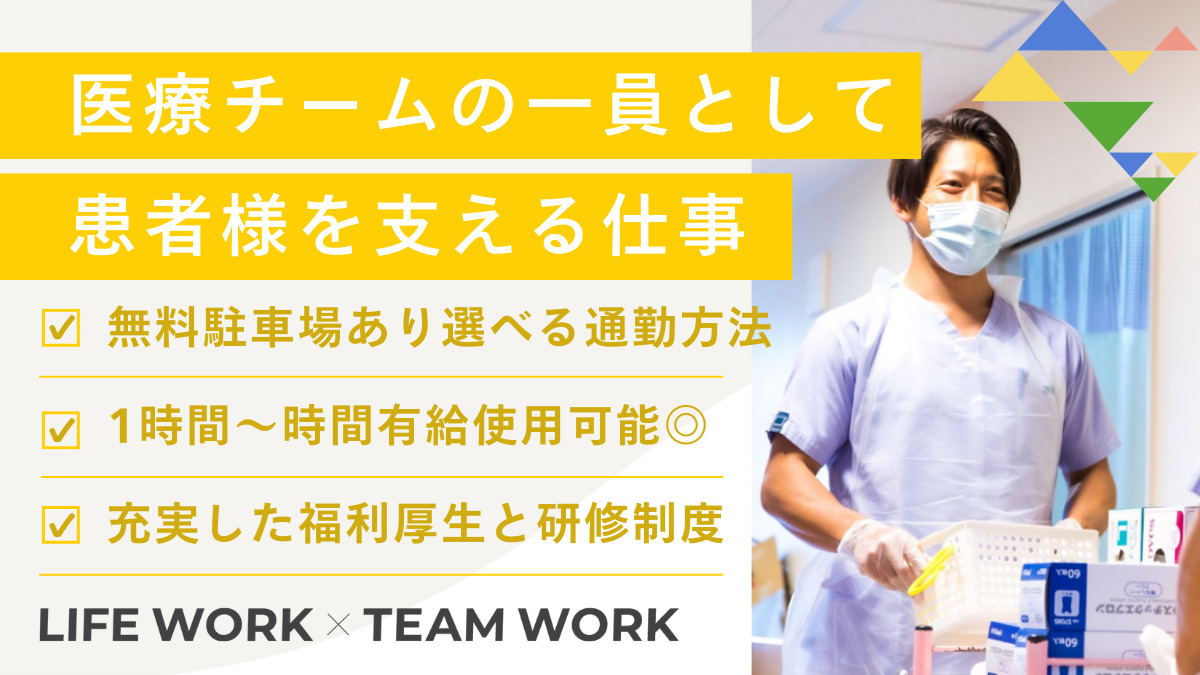目次
1.成年後見制度とは
後見人を立てて判断力が不十分な人を保護する制度
成年後見制度とは、認知症や知的・精神障がいなどにより判断能力に不安のある人を法的に保護するため、代理人(後見人)を立てて意思決定支援をおこなう制度です。
具体的には、不動産やお金の管理、相続関係の手続きなどの「財産管理」、介護サービスの利用・契約や入院手続きといった「身上保護」の意思決定が必要な場面で、後見人が本人の代わりに手続きや契約の同意・取消などをおこないます(法律行為)。介護サービスなどに限らず、本人が意図せず不利益な契約を結んでしまわないように支援することで、詐欺などの被害を防ぐ役割もあります。
成年後見の種類
成年後見制度は、現在の具体的な支援に取り組む法定後見と、将来的に支援をしてほしい人をあらかじめ選んでおく任意後見があります。
法定後見
法定後見制度は、必要な支援の程度に応じて3種類に分かれています。補助、保佐、後見の順で支援度が高くなり、後見(成年後見人)は本人に代わってすべての法律行為ができる、強い権限が付与されます。

任意後見
任意後見とは、判断能力が十分あるうちにあらかじめ任意後見人を選び、任意後見契約を結んで将来的に支援を受けられるようにしておく制度です。
任意後見契約は締結しただけでは効力が発生しません。判断能力に不安が生じたら、本人または親族、任意後見人(効力が生じる前は任意後見受任者という)が家庭裁判所に申立をおこないます。それにより任意後見人の監督をする「任意後見監督人」が選任されることで初めて有効になり、後見人が法律行為などの支援ができるようになります。
成年後見制度の利用者数は増加している
最高裁判所の資料によると、成年後見制度の利用者数は2022年までの5年間で約21万8,000人から約24万5,000人に増加しています。後見開始の理由は認知症が63.2%、次いで知的障がいが9.4%と認知症が多くの割合を占めており、高齢化に伴う認知症患者の増加が大きな要因だと考えられます。

2.成年後見人になれるのは?
親族、専門家、研修を受けた人、福祉法人
成年後見人になれるのは、以下に挙げる人で家庭裁判所によって選任された人です。
- 親族
- 弁護士や司法書士などの法律・福祉の専門家
- 親族以外の研修を受けた市民(市民後見人)
- 福祉法人
家庭裁判所は必要な支援内容や本人の事情を考慮し、後見人を監督する成年後見監督人を選んだり、希望の人以外を選任したりする場合もあります。後見開始の審判(裁判所が調査や検討を経て判断を下すこと)に対しては、希望が通らなかったとしても、不服申立をおこなうことはできません。
成年後見人になれない人
以下の条件に該当している場合は、成年後見人になれません。適切な財産管理や身上保護をおこなえるよう、管理能力が不十分な人、支援される本人と利害が対立する立場にある人は、後見人に適さないとみなされます。
- 未成年者
- 成年後見人等を解任された人
- 破産者で復権(破産による制約の解除)していない人
- 本人に対して訴訟したことがある人、その配偶者・親子
- 行方不明の人
成年後見人にできること
成年後見人等の役割は、本人の意思や心身の状況などを配慮しつつ、代理人として法律行為などをおこない、適切に財産を管理することです。具体的には同意、取消、代理権の行使をすることができます。
権限の範囲は成年後見人がもっとも広く、補助人・保佐人の権限はそれより限定的です。
| 補助 | 保佐 | 後見 | |
|---|---|---|---|
| 同意権 | 申立の範囲内で、裁判所が認めた特定の法律行為 | 民法第13条1号で定められている行為* 家庭裁判所が認めた上記以外の行為 |
―** |
| 取消権 | 申立の範囲内で、裁判所が認めた特定の法律行為 | 民法第13条1号で定められている行為* 家庭裁判所が認めた上記以外の行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
| 代理権 | 申立の範囲内で、裁判所が認めた特定の法律行為 | 申立の範囲内で、裁判所が認めた特定の法律行為 | 財産に関するすべての法律行為 |
成年後見の支援例
認知症、アルコール依存症がある60代男性
早期退職して一人暮らしをしていた60代男性。生活習慣の変化から飲酒量が増え、昼間から騒いで通報されることも増えてきた矢先、体調を崩し入院。認知症とアルコール依存症と診断され、入院先から地域の成年後見センターに退院後の支援について相談があったため、隣町で暮らす親族の同意を得たうえで後見開始を申し立て、同センターが後見を引き受けた。
本人が在宅復帰を希望したため、同センターが要介護認定の申請と介護サービス契約を代行し、定期的に親族に状況を報告。退院後は週3日介護サービスを利用しつつ、年金を使い切ってしまわないよう週単位で収入を管理して生活している。
成年後見人にできないこと
上述のように成年後見人には幅広い権限がありますが、できないこともあります。支援する本人の不利益になること全般はもちろん、以下の行為が挙げられます。
事実行為
事実行為とは、契約を結ぶといった「法律行為」に対し、実際に介護をする、送迎や付き添いをするといった具体的な行為を指します。成年後見人の役割は意思決定の支援であり、介護が必要であれば本人に代わって申請やサービスの契約をすることです。そのため後見人自身が事実行為をおこなうことはできません。
現実的には事実行為は完全に禁止されているわけではなく、成年後見人が親族の場合は介助や付き添いなどの世話をすることもあるでしょう。しかし事実行為はあくまで成年後見人の責任の範囲外です。
身分行為
身分行為とは、結婚・離婚、養子縁組、子の認知など、その人自身の法律上の身分に関する意思決定をいいます。このような身分行為は当然ながら本人にしか決定できません。
保証人になること
成年後見人は、支援する本人の保証人や身元引受人になることはできません。
もし滞納があったり財産が足りなかったりした場合に成年後見人が支払いを立て替えると、本人に請求をすることになり債権者・債務者という利害関係が発生してしまいます。利害が対立する立場は成年後見人の責務と矛盾するため、金銭の肩代わりをおこなう(可能性がある)ことはできません。
医療行為への同意
医療行為の選択・決定は重要な自己決定権のひとつであり、成年後見人が代理でおこなうことはできません。仮に病院などから医療行為の同意を求められた場合、できない立場であることを説明する必要があります。
ただし、成年後見人が親族であるときは、後見人としてではなく親族として同意や署名をおこなうケースはあり得ます。
3.成年後見制度を利用するときの流れ

後見開始の手続き
成年後見を始めたいときは、必要な書類をそろえ、家庭裁判所に申し立てます。申立は本人、配偶者や4親等以内の親族のほか、親族がいない場合は代わりに市町村長がおこなうことができます。
成年後見開始の手続きに必要な書類
- 申立書
- 診断書(成年後見の場合)
- 収入印紙(手数料、登記嘱託手数料)、郵便切手
- 戸籍謄本
後見開始の審判を経て後見登記(後見人である事実の証明)が完了すると職務説明がおこなわれ、支援が始まります。成年後見人は定期的に支援内容を家庭裁判所に報告をする義務があります。
また、一度申立をおこなうと、家庭裁判所の許可を得なければ取り消すことはできません。
成年後見制度にかかる費用
成年後見開始の手続きにかかる費用は、手数料と切手代、鑑定料(保佐、後見の場合)です。申立手数料800円と、登記手数料2,600円の合計3,400円分の収入印紙を購入して支払います。書類送付のための切手代がいくら必要になるかについては、申立をおこなう家庭裁判所に確認しましょう。
保佐または後見の申立に際しては、本人の判断能力を医学的に確かめるため、医師による鑑定を求められることがあります。裁判所が必要と判断した場合に依頼するもので、10〜20万円程度かかります。本人負担とされた場合は、本人の財産から支出することができます。
専門家に依頼するときは報酬が必要
後見人が報酬付与の申立をしたとき、または弁護士や司法書士などの専門家に後見人を依頼する場合、毎月の報酬支払いが必要になります。
専門家ではない後見人の場合月額1〜2万円程度です(管理する財産が高額だと、最大5〜6万円程度となることもあります)。
弁護士などに依頼する場合、申立をおこなう際の着手金は数万〜数十万円程度、後見人としての報酬額は月2〜10万円程度のことが多いようです。
4.成年後見制度を利用するときの注意点やデメリットは?
成年後見は途中で辞められない
成年後見人の任期は本人の判断能力が回復するか、または亡くなるまでずっと続きます。やむを得ず途中で後見人を辞めたい場合は家庭裁判所の許可を得なければならず、かつ次の成年後見人が就任するまでは辞めることができません。
辞任の正当な事由としては、病気や高齢のため業務を遂行できなくなった、転勤などで離れることになり後見業務ができないといったものがあります。
親族の負担やトラブルに注意
さまざまな契約や手続きの代行をおこなう後見業務は、個人にとって重い負担となることがあります。また、後見人は希望通りの人が認められるとは限らず、親族の中の一人が強い権限をもって財産管理をする(場合もある)ことから、親族間での不満や不公平感につながる可能性もあります。
成年後見制度を利用するときは事前によく話し合いをおこなったうえで、後見業務についての理解を深めるとよいでしょう。
成年後見人を解任するときは
成年後見人が不正行為をしたり、何かしらの事情で後見業務に適さないときは、本人や親族は家庭裁判所に解任を申し立てることができます。
2022年の成年後見人による不正件数は191件(うち専門家が20件)、被害額は約2億1,000万円でした。ゼロになったわけではありませんが、不正件数が4倍以上・被害額が3倍弱だった2014年に比べると大きく減少しています。
親族、親子間で成年後見を担う場合、本人の財産を悪意なく家族の用事などに使ってしまい、意図せず不正利用となってしまうリスクもあります。身内といえども後見をおこなう場合は、正確で適切な管理に努める必要があります。
5.成年後見制度をよく知って活用を
認知症などで判断力に不安のある人にとって、身の回りの判断をサポートしてもらえる成年後見は心強い制度です。補助、保佐、後見の順で支援の必要性が高くなり、また後見人の権限の範囲も広くなります。将来的に後見を依頼する任意後見もあるため、将来生活や介護の手続き・契約が難しくなりそうであれば、一度成年後見制度について調べておくのがおすすめです。
参考
- 厚生労働省|成年後見はやわかり
- 裁判所|成年後見制度について