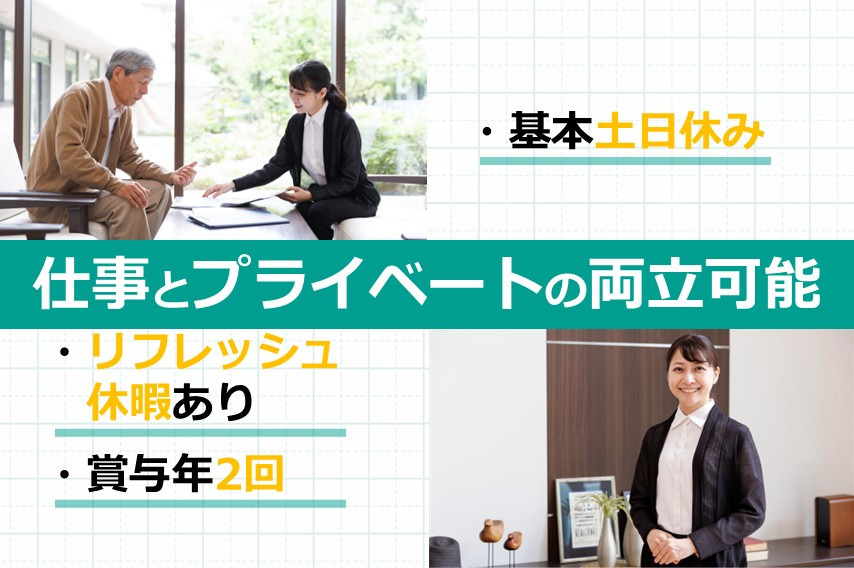目次
- 1. 家族信託とは
- 家族信託の仕組み
- 2. 家族信託の8つのメリット
- メリット1:認知症での資産凍結に備えられる
- メリット2:柔軟に財産を管理・運用・処分できる
- メリット3:財産を希望どおりに引き継げる
- メリット4:障がいのある子どもに財産を残せる
- メリット5:不動産を共有せずに済む
- メリット6:遺族の負担を軽減できる
- メリット7:事業承継にも対応できる
- メリット8:倒産隔離機能がある
- 3. 家族信託の4つのデメリット
- デメリット1:受託者の担い手がいない可能性がある
- デメリット2:親族間の合意が得られない可能性がある
- デメリット3:遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
- デメリット4:節税にはならない
- 4. 高齢者の財産管理を支援するほかの制度
- 成年後見制度
- 日常生活自立支援事業
- 5. 家族信託契約の手続き
- 6. 家族信託を始める際の注意点
- 家族全体で合意する
- 成年後見制度や遺言と組み合わせる
- 信託する財産や受託者をよく検討する
- 7. 家族信託制度を適切に活用しよう
1. 家族信託とは
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を任せる制度です。認知症などで意思能力・判断能力が低下すると、預金口座は凍結され、不動産関連の契約もできなくなってしまいます。親がまだ元気なうちに、家族信託で財産の管理・運用・処分を子どもに任せることで、老後に備えることが可能になります。また、家族に財産を託す制度なので、費用は契約時の公正証書作成費などだけで済み、維持費はかかりません。
従来、信託制度は金融機関が財産を預かることを前提としていましたが、2006年の信託法改正で、金融機関以外でも信託を受けられるようになり、家族信託が可能になりました。親と子どものように、家族間で信託するケースが多いため「家族信託」と呼ばれますが、家族・親族以外の人への信託も可能です。
家族信託の仕組み
家族信託では、財産を信託する人を「委託者」、任される人を「受託者」、財産からの利益を得る人を「受益者」と呼びます。委託者から任された預貯金や不動産を、受託者は委託者の希望に沿って管理・運用・処分し、利益は受益者が得ます。多くの場合、委託者と受益者は親、受託者は子どもとなります。

2. 家族信託の8つのメリット
家族信託にはさまざまなメリットがあります。ここでは、家族信託の8つのメリットをご紹介します。
メリット1:認知症での資産凍結に備えられる
家族信託のメリットとして、資産凍結の事態に備えられる点が挙げられます。認知症などで意思能力・判断能力が低下すると、預金口座は凍結されます。また、不動産関連の契約もできなくなり、自宅を売却したり、所有するアパートの賃貸借契約をしたりすることもできなくなります。
家族信託では財産の名義が受託者に変更されます。そのため、意思能力・判断能力がしっかりしているうちに、家族に財産を信託しておけば、認知症が進んでしまったとしても、資産が凍結される心配はありません。
メリット2:柔軟に財産を管理・運用・処分できる
高齢者を支える制度として成年後見制度があります。この制度は財産の保全を目的としているため、不動産の売却や積極的な投資などは、容易にはおこなえません。一方、家族信託は成年後見制度よりも柔軟な制度のため、委託者の気持ちに沿った財産の管理・運用・処分が可能です。
例えば、アパートを所有している場合、成年後見制度では入居者を増やすためのリフォームなど積極的な投資はできません。その点、家族信託であれば、委託者があらかじめ財産をどのようにするか方向性を定めておけば、受託者は裁量を持って管理できます。
メリット3:財産を希望どおりに引き継げる
家族信託には遺言と同等の機能があります。そのため、財産ごとに残したい相手を指定して引き継いでもらうことが可能です。例えば、不動産はAさんに、預貯金はBさんにといったように、生前から遺言のように委託者本人の意向を反映できます。
また、家族信託では、財産を相続した人が亡くなったあと、さらに誰が財産を継承するかも決めておくことが可能です。例えば、祖父がアパートを所有していて、子どもが受託者の場合、祖父の次の受益者となる祖母の死後は、受益権を孫に移すなどの承継が可能になります。なお、一般的に家族信託の契約は公正証書でおこなわれるため、自筆の遺言と家族信託の内容とが食い違う場合は、家族信託が優先されます。
メリット4:障がいのある子どもに財産を残せる
家族信託では、知的障がいなどで金銭の管理ができない子どものために、親から財産を残すことも可能です。親が亡くなったあとの生活を支えるため、子どもに遺す財産を信頼できるきょうだいや親族に信託します。子どもを受益者とすることで、適切にお金を管理・使用してもらいます。
さらに、家族信託であれば、子どもが亡くなったあとに残る財産についても、あらかじめ決めておくことができます。例えば、きょうだいや親族に引き継いでもらったり、お世話になった施設に寄付したりすることが可能です。これは家族信託だけの機能です。
メリット5:不動産を共有せずに済む
賃貸用の不動産をきょうだいなどの複数人で相続すると、相続した全員の同意がないと修繕や売却、賃貸借契約はできません。そのため、一人でも認知症などで意思能力・判断能力がなくなってしまうと、契約や管理が難しくなる可能性があります。相続する前に、家族信託で管理権限を一人に集約しておけば、こうしたリスクを減らすことが可能です。
メリット6:遺族の負担を軽減できる
財産の相続は遺族にとって大きな負担になります。遺産分割協議でどの財産を誰が相続するのか決める必要がありますが、それぞれの主張が対立したり、相続人がすでに認知症だったりすると、スムーズに進まない可能性もあるでしょう。
親が健康なうちに、財産の継承について家族信託で定めておけば、相続のトラブルや口座の凍結を防ぐことができ、遺された家族の負担軽減につながります。
メリット7:事業承継にも対応できる
家族信託は家業の事業承継にも有効です。中小企業の場合、一般的に後継者に株式を譲渡・売却して事業を継承します。その際に、贈与税・相続税が発生したり、株式の購入資金が必要になったりして、後継者の経済的負担になる場合があります。
一方、家族信託であれば株式も信託することができます。委託者と受益者が同じ人なら、贈与税の対象とはなりません。なお、株式の種類によっては、株主総会や取締役会の議決がないと信託できない場合もあるのでよく確認しましょう。
メリット8:倒産隔離機能がある
信託された財産は、委託者・受託者の両者から独立した財産となります。そのため、両者の倒産や差し押さえの影響を受けません。これを「倒産隔離機能」と呼びます。信託した財産は受託者の名義になり、受託者が管理しますが、受託者の財産になるわけではありません。同様に委託者の財産でもなくなり、独立した財産となります。
ただし、制度の悪用は禁止されているので、破産や差し押さえが想定されるときに、財産を家族信託して強制執行を逃れることはできません。
3. 家族信託の4つのデメリット
さまざまなメリットがある家族信託ですが、介護施設の入居契約など、生活や健康を守るための「身上監護」ができない以外にも、デメリットがあります。ここでは4つのデメリットについて解説します。
デメリット1:受託者の担い手がいない可能性がある
家族信託は受託者がいないと成立しません。財産の管理・運用・処分には責任と負担が伴います。例えば、受託者には財産の収支状況の帳簿付けや、受益者への報告が義務付けられています。また、不動産を任されている場合には、老朽化で事故が起きないよう管理しなければなりません。このような負担が敬遠されて、受託者が見つからない可能性があるのです。
デメリット2:親族間の合意が得られない可能性がある
家族信託では多くの場合、将来的に受託者が信託された財産を相続することを想定しています。委託者と受託者の合意があれば、家族信託契約は成立するため、ほかの家族が知らないまま進めてしまうと、不満を招く可能性もあるでしょう。トラブルに発展しないよう、事前に家族の間で合意を得ておくことが重要です。
デメリット3:遺留分侵害額請求を受ける可能性がある
財産を相続する際、配偶者や子どもなどの相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が発生します。例えば、子どもが複数いる場合、家族信託ですべての財産を一人に信託していたとしても、配偶者やほかの子どもにも遺留分が発生します。本来相続できる分を相続できないケースでは、遺留分侵害額請求をすることが可能です。請求に応じないと訴訟に発展するリスクもあるため、家族信託をする際には遺留分に配慮することが重要です。
デメリット4:節税にはならない
家族信託は財産の管理を目的としているため、節税対策にはなりません。家族信託は実際の相続と異なり、財産の名義は受託者に変わるものの、多くの場合に受益権は委託者に残ります。委託者が亡くなったときに初めて財産として相続されて、相続税が課されるため、相続税の節税が目的の場合は、ほかの方法を検討しましょう。
4. 高齢者の財産管理を支援するほかの制度
成年後見制度
成年後見制度は認知症の高齢者などの財産管理や契約行為を支援する制度です。家族信託は財産管理の制度のため、介護施設の入居契約などの身上監護はできません。身上監護をするには成年後見制度を利用する必要があります。
支援を担当する成年後見人は家庭裁判所によって選任されます。そのため、家族が選ばれるとは限らず、多くの場合に司法書士や弁護士などの専門家が選任されます。家族信託と成年後見制度の主な違いは、以下のとおりです。
|
家族信託 |
成年後見制度 |
|
|---|---|---|
|
財産を管理する人 |
受託者 |
成年後見人 |
|
財産管理を始める時期 |
家族信託契約の締結時 |
成年後見人の選任時 |
|
監督機関 |
とくになし |
家庭裁判所 |
|
初期費用 |
公正証書作成費用など |
専門家への相談費用:10万〜20万円 |
|
月々の費用 |
一般的に費用はかからない |
成年後見人が家族の場合:0〜5万円/月 成年後見人が専門家の場合:2万〜10万円/月 ※後見人への報酬 |
成年後見制度については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
>成年後見制度とは? なれる人や気をつけることをわかりやすく解説!
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、全国の社会福祉協議会が実施している事業です。社会福祉協議会の専門員や生活支援員が、日々の生活に使うお金の出入金や通帳の預かりなどを支援します。金銭の管理だけでなく、福祉サービスの利用手続きなどの幅広い支援が受けられます。一人暮らしの高齢者だけでなく、福祉施設や病院に入っている人も利用可能です。
5. 家族信託契約の手続き
家族信託契約は委託者と受託者の合意があれば締結可能です。ほかの家族にも説明したうえで、家族信託契約を締結しましょう。

財産が預貯金の場合は、金融機関で信託口口座を開設します。不動産を信託する場合は、信託登記をして、名義を変更しましょう。必要に応じて信託監督人を設定し、財産の信託管理が始まります。
6. 家族信託を始める際の注意点
家族全体で合意する
家族信託を始める際は、委託者と受託者だけで話し合うのではなく、ほかのきょうだいなど家族全体で合意するようにしましょう。
家族信託では受託者に財産の名義や管理権限が移ります。そのため、制度の理解が不十分だと、将来相続人になる家族などから不満がでてしまう可能性もあります。トラブルにならないよう、家族全体が納得できるよう説明し、協力できるようにしましょう。
成年後見制度や遺言と組み合わせる
家族信託だけでは、認知症になった親のサポートに不十分な場合があります。家族信託では介護施設への入居契約などの身上監護ができないため、親の認知症に備える目的なら、成年後見制度の利用も併せて検討しましょう。
また、一般的に家族信託は財産の一部を信託するものです。ほかの財産には効力がないため、信託していない財産について希望があれば、遺言を残してもらうと良いでしょう。
信託する財産や受託者をよく検討する
家族信託を始める際、どの財産を誰に信託するのか、慎重に検討しましょう。受託者以外の家族にも財産を相続する権利があるため、遺留分に配慮することが重要です。
また、配偶者などすでに高齢の家族を受託者にしてしまうと、委託者よりも先に亡くなってしまう可能性もあります。委託者の希望を理解してくれて、中長期的に財産をしっかり管理できる家族を選びましょう。
7. 家族信託制度を適切に活用しよう
家族信託を利用すれば、高齢になった親の財産を、子どもが管理・運用・処分することが可能になります。多くのメリットがありますが、身上監護ができないなどのデメリットもあるので、十分に制度を理解したうえで、適切に活用しましょう。
ジョブメドレーではケアマネジャーや生活相談員など、高齢者やその家族を支えるさまざま職種の求人を幅広く扱っています。希望の勤務地や給与、特徴などを選択して、あなたの希望にあった仕事を探してみてください。