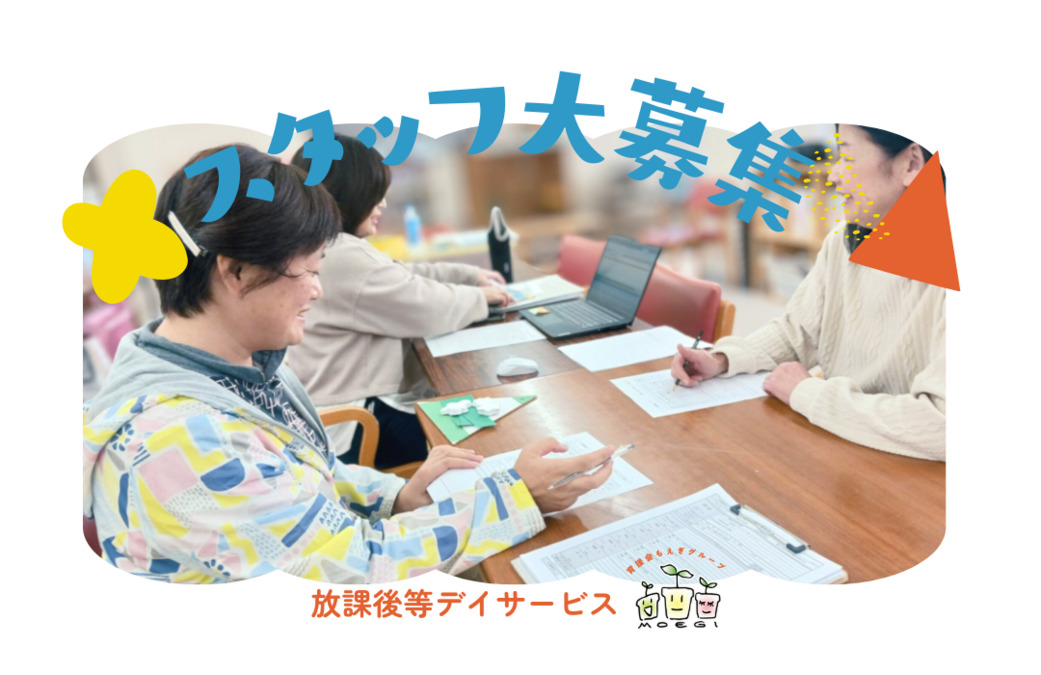1.訪問リハビリテーションとは
・訪問リハビリの概要
訪問リハビリテーションとは、リハビリの専門職である理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅や施設を訪問し、リハビリテーションを提供することです。利用者ができる限り自立した日常生活を送ることを目標に、心身機能の維持・回復に向けたリハビリをおこないます。
高齢化が進み、医療・介護の現場は医療機関から在宅へと変わってきています。高齢者が住み慣れた自宅や地域で生活を続けられるよう、退院後のリハビリのみならず、予防医療・介護の観点からも在宅でおこなう訪問リハビリは注目されています。
訪問リハビリのメリット
- 自宅でリハビリを受けることで、日常生活に直結する機能回復・維持に繋がりやすい
- リハビリ職が直接利用者の生活環境を見ることで、的確な機能訓練やアドバイスができる
- 寝たきりなどで通所リハビリの利用が難しい人でも、移動の負担やリスクなく実施できる
- 集団リハビリと異なり、1対1でのきめ細かい支援を受けられる
- リハビリや介助の仕方について家族からの相談に応じることができ、介護者の支援にも繋がる
・訪問リハビリの提供元による違い
訪問リハビリをおこなう理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、主に訪問リハビリテーション事業所または訪問看護ステーションに所属することになります。
訪問リハビリテーション事業所は、「訪問リハビリサービス」を提供する指定を受けた病院やクリニック、介護老人保健施設(老健)などが該当します。
一方、訪問看護ステーションは「訪問看護サービス」を提供する事業所であるため、厳密には“訪問看護サービスの一部として”リハビリを提供します。訪問リハビリテーション事業所とは制度上の位置づけが異なるため、サービス実施のために必要な手続きや資料などにも違いがあります。
訪問リハビリの提供元による違い
|
訪問リハビリテーション事業所 (病院・クリニック、老健など) |
訪問看護ステーション |
|
|
適用保険 |
医療保険 介護保険 ※老健は介護保険のみ |
医療保険 介護保険 |
|
医師による指示書 |
同機関医師の訪問リハビリ指示書が必要* |
主治医の訪問看護指示書が必要 |
|
リハビリの計画書 |
リハビリテーション実施計画書 |
訪問看護計画書 |
*主治医が他機関に所属する場合、主治医による「診療情報提供書」が別途必要
この通り2つの事業所では制度上の違いはあるものの、実際に利用者が受けるリハビリの内容としてはほとんど違いはありません。
・訪問リハビリの指示書・計画書とは
訪問リハビリは、必ず医師の指示のもとおこないます。訪問リハビリテーション事業所の場合は、事業所の医師が作成する「訪問リハビリ指示書」が必要です。ただし主治医がほかの医療機関にいる場合は、「診療情報提供書」を別途発行してもらう必要があります。訪問看護ステーションの場合は、主治医が発行する「訪問看護指示書」が必要です。
医師からの指示書を受け取ったリハビリ職は、利用者の既往歴や心身機能の状態、これからおこなうリハビリの目標や実施内容などを記した計画書(リハビリテーション実施計画書または訪問看護計画書)を作成し、医師に提出します。なお訪問看護ステーションの場合、リハビリ職は看護師と連携して計画書を作成する必要があります。
リハビリテーション実施計画書の様式例
それぞれの計画書は定期的に見直し再発行します。ケアマネジャーをはじめ、関係する居宅サービス事業者にも適宜情報を共有するようにしましょう。
▼訪問看護指示書・計画書についてはこちらでも解説
訪問看護ってどんな仕事? 在宅生活を支える訪問看護師の仕事内容・給料・必要な経験・働く場所・服装や持ち物など
・訪問リハビリの利用状況
訪問リハビリの需要は毎年増え続けており、2009年から2019年の10年間で利用者数は約5.7万人から約11.5万人と、およそ2倍に増加しています。
とくに増加率が高いのは要支援認定を受けた利用者であり、2007年と2019年の増加率を比較すると、要介護1〜5は2.1〜3.8倍増だったのに対し、要支援1・2はそれぞれ4.9倍、5.4倍でした。

訪問リハビリが必要となった原因の傷病としては、「脳卒中」「骨折」「廃用症候群」の順で多くなっています。介護度別に見ると、要支援1・2は「関節症・骨粗しょう症」、要介護1・2は「認知症」「骨折」、要介護3〜5は「脳卒中」「廃用症候群」の割合が比較的高い傾向があります。

訪問リハビリの診療時間は、1単位20分で設定されています。訪問1回あたりの診療時間は、介護度に関わらず約8割が「40分」で最多でした。

訪問頻度は2019年の介護保険総合データベースでの集計によると、月8回(31.3%)が最多のボリュームゾーンとなりました。短期集中リハビリテーション実施加算の算定がある場合においては、最も多い回答が月16回(25.6%)でした。訪問リハビリの利用上限は原則として週6回(月24回)ですが、ほかの居宅サービス併用との兼ね合いもあり、上限回数まで利用できる人は少ないのが現状です。
一人あたりの訪問頻度でいうと、制度上訪問リハビリは1回20分で最大週6回まで(1日2回まで)入れます。ただ、訪問介護とか看護とかほかのサービスも併用しているとすぐに介護保険の限度額になってしまうので、週1日で2回分(40分)リハビリするのが現実的って感じです。
・訪問リハビリテーション事業所の施設数・職員数
利用者の増加に伴う形で、訪問リハビリテーション事業所の数も増加が続いています。とくに2018年から2019年の1年間は大きく伸び、約500事業所の新規申請がありました。施設形態の内訳としては、病院・クリニックが約8割、介護老人保健施設が約2割となっています。

また、訪問リハビリテーション事業所におけるリハビリ職の平均人数(常勤換算数)は、理学療法士が2.9人、作業療法士が1.2人、言語聴覚士が0.4人です。
2.訪問リハビリで働く
・訪問リハビリで必要な資格・経験
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として訪問リハビリで働くには、当然それぞれの国家資格が必要になります。移動手段が車やバイクの場合は運転免許証が求められますが、そのほかに必要な資格はありません。訪問リハビリをおこなう病院・クリニックや介護老人保健施設、または訪問看護ステーションに所属することで、訪問リハビリを担当することができます。
訪問リハビリの求人募集を見ると、新卒で応募可としている事業所は存在するので、資格を持っていれば未経験でも働くことは可能です。ただし訪問リハビリはその性質上、単独で訪問先に出向きひとりで診療にあたることがほとんどです。病院や施設のように常時近くに頼れるスタッフがいないので、訪問リハビリを担当する前に病院などで経験を積んだほうがいいと考える先輩リハビリ職は少なくありません。
経験が浅くても訪問リハビリに挑戦したい人は、研修制度や先輩の同行訪問があるかなど、サポート体制が整っているか確認してみると良いでしょう。
・訪問リハビリの仕事内容
訪問リハビリでおこなう仕事内容は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のそれぞれの専門分野によっても異なりますが、主に次のようなものがあります。
訪問先での主な仕事内容
- 健康管理(バイタルチェック、問診など)
- 機能評価(病状や身体機能の把握など)
- 生活動作訓練(歩行、食事、排泄、着替え、座位保持など)
- 摂食嚥下訓練(口腔ケア、口腔体操、食事内容のアドバイスなど)
- マッサージ(麻痺や褥瘡予防のため)
- 環境整備のサポート(利用者の状態に合った住宅改修のアドバイスなど)
- 福祉用具の選定(身体に合わせた福祉用具の利用支援など)
- 家族への指導(介助方法のアドバイスなど)
訪問先以外での主な仕事内容
- 退院前カンファレンスへの出席
- サービス担当者会議への出席
- リハビリテーション実施計画書の作成・報告作業
- リハビリテーション実施報告書の作成・報告作業
- 医師との報告・連絡・相談
- 担当ケアマネジャーとのスケジュール調整
- その他関係者との報告・連絡・相談
・訪問リハビリの一日のスケジュール
ジョブメドレーが以前話を伺った、在宅医療専門のクリニックで働く言語聴覚士の男性の一日の過ごし方を見てみましょう。

この男性の場合、一日あたりの訪問リハビリの件数は4件でした。1訪問あたりの診療時間がおおむね40分だとすると、準備・移動時間も加味して一日あたりの訪問件数は4〜8件程度だと考えられます。
・訪問リハビリの給料
ジョブメドレーに掲載されている求人から、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の賃金相場を各職種全体と訪問リハビリのみの求人で算出し比較しました。なお、残業手当などの月によって支給額が変動する手当は集計対象外のため、実際に支払われる金額はこれより多くなる可能性があります。
|
職種 |
雇用形態 |
全体 |
訪問リハビリ |
|
理学療法士 |
正職員(月給) |
28万4,314円 |
30万2,433円 |
|
契約職員(月給) |
25万5,406円 |
29万1,860円 |
|
|
パート(時給) |
2,085円 |
3,007円 |
|
|
作業療法士 |
正職員(月給) |
27万7,653円 |
30万518円 |
|
契約職員(月給) |
25万2,466円 |
29万4,733円 |
|
|
パート(時給) |
1,812円 |
2,109円 |
|
|
言語聴覚士 |
正職員(月給) |
27万6,590円 |
30万1,512円 |
|
契約職員(月給) |
25万3,820円 |
31万6,000円 |
|
|
パート(時給) |
1,794円 |
2,018円 |
※2021年6月時点のデータ
比較すると、3職種すべてでどの雇用形態においても、訪問リハビリのほうが賃金が高いことがわかりました。中には訪問件数に応じたインセンティブを設定している事業所もあります。
なお、ジョブメドレーがインタビューした総合病院で働く作業療法士の女性は、訪問リハビリでの給料面について次のように話していました。
いずれは訪問リハビリに携われたらいいなと思ってます。
(中略)
今は病院の数が減って在宅を重視するようになって、お給料も訪問のほうが高いみたいです。周りでも、訪問リハビリに転職したり独立したりする人が増えてきてます。
3.訪問リハビリの今後
利用者の生活の場に直接介入して機能訓練や環境面からサポートできることが、訪問リハビリならではの利点であり効果だと言えるでしょう。一般社団法人全国デイ・ケア協会によると、訪問リハビリの利用開始から6ヶ月後のADL(日常生活動作)をみると、要支援・要介護の平均で約4割の改善が見られたとの調査結果が出ています。実際に訪問の現場で働くリハビリ職からも、生活に寄り添った支援にやりがいを感じているという声を聞きます。
日本の高齢化は今後も進行し続け、2042年にピークを迎えると言われています。医療費抑制の観点からも多くの高齢者を支えるには在宅医療が不可欠とされており、近年の訪問リハビリテーション事業所の増設にもそれは表れています。病院や施設では対応しきれないニーズに応えたいと考える方は、訪問リハビリ職として働くことを選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
訪問リハビリの求人を見る