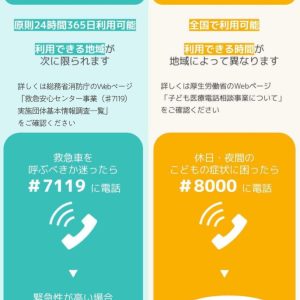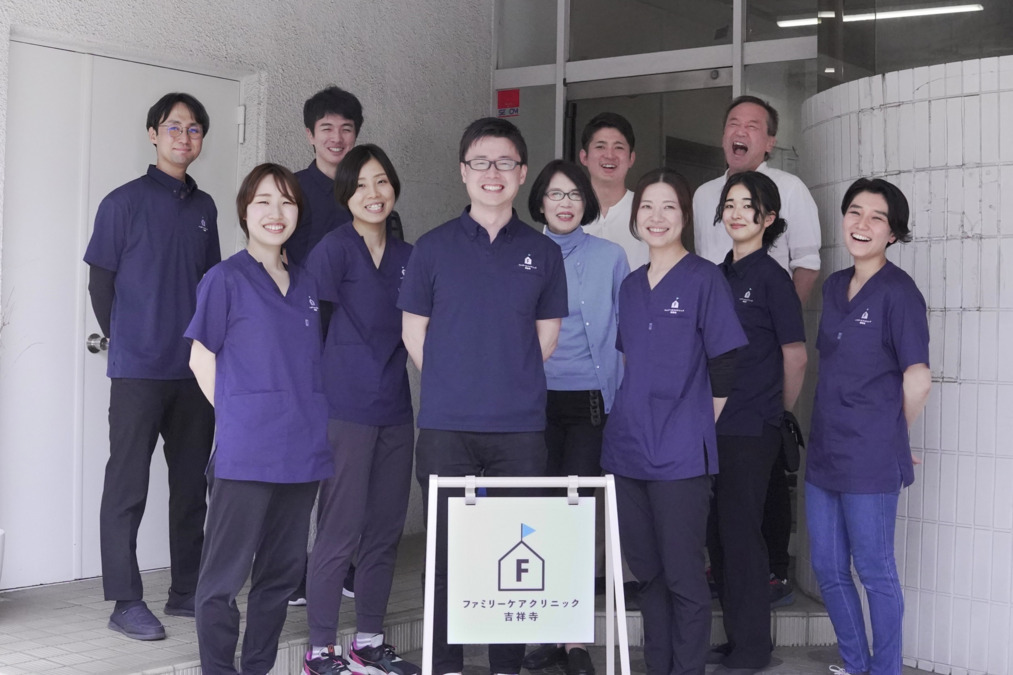目次
1.救急救命士の仕事内容
重度傷病者の救急救命処置をおこなう
救急救命士は、医師の指示のもと、重度傷病者が病院に搬送されるまでの間、医行為を含む救急救命処置をおこなう有資格者です。主に消防署勤務の救急隊の一員として救急車または消防車に乗務し、救急搬送で出動します。
119番通報を受け現場に到着した救急救命士は、傷病者の状態を確認し、必要に応じて医師の指示を受けながら気管確保や輸液、心臓マッサージなどの救急救命処置をおこないます。病院に到着したら傷病者を病院側に引き継ぎ、医師に処置内容を報告するまでが救急救命士の役割です。
いつでも緊急の出動に対応できるよう、勤務体系は三交代制がとられることが一般的です。救急搬送以外の時間は、医薬品や器具の点検、救急救命の講習や訓練の受講、事務作業などの業務に従事します。
tips|救急救命士法改正による業務の場の拡大
2021年の救急救命士法改正により、それまで救急搬送中(病院前まで)に限られていた救急救命処置の対応範囲が、救急外来まで拡大されました。これにより重度傷病者が病院や診療所に到着して入院するまで、または医師に引き継がれるまでの間、救急救命士が処置を続けることができるようになりました。
救急医療におけるタスクシフト・シェアによる医師の働き方改革の後押しや、病院における救急救命士の雇用増加などが期待されています。
救急救命士ができる特定行為とは
本来、医師以外の人が医行為(≒医業)をおこなうことは禁止されていますが、救急救命士や看護師など一部の職種には、一定の条件下で医行為をおこなうことが認められています。
救急救命士が実施できるのは、医師の直接指示(具体的指示)を受けておこなう特定行為5項目と、事前にまとめられた指示(包括的指示)でおこなう医行為28項目です。
救急救命士が医師の具体的指示のもとおこなえる特定行為
- 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液
- 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスクまたは気管内チューブによる気道確保
- 薬剤(アドレナリン)の投与
- 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保および輸液
- 低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
救急救命士が医師の包括的指示でおこなえる救急救命処置
- 精神科領域の処置
- 小児科領域の処置
- 産婦人科領域の処置
- 自動体外式除細動器による除細動
- 自己注射が可能なエピネフリン製剤によるエピネフリン投与
- 血糖測定器を用いた血糖測定
- 聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取
- 血圧計の使用による血圧の測定
- 心電計の使用による心拍動の観察および心電図伝送
- 鉗子・吸引器による咽頭・声門上部の異物の除去
- 経鼻エアウェイによる気道確保
- パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定
- ショックパンツの使用による血圧の保持および下肢の固定
- 自動式心マッサージ器の使用による体外式胸骨圧迫心マッサージの施行
- 特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持
- 口腔内の吸引
- 経口エアウェイによる気道確保
- バッグマスクによる人工呼吸
- 酸素吸入器による酸素投与
- 気管内チューブを通じた気管吸引
- 用手法による気道確保
- 胸骨圧迫
- 呼気吹き込み法による人工呼吸
- 圧迫止血
- 骨折の固定
- ハイムリック法及び背部叩打法による異物の除去
- 体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔色の観察
- 必要な体位の維持、安静の維持、保温
救急隊員や消防士との違い
消防署勤務の救急救命士と、救急隊員や消防士との違いは救急救命士資格の有無であり、身分はいずれも地方公務員です。なお、消防士・消防官は消防活動にあたる消防職員の一般的な呼び方で、とくに違いはありません。
救急隊は3名で編成され、そのうち1名は救急救命士である必要があります。救急隊と消防隊は状況に応じて連携して出動するほか、消防士が実務経験を積み救急救命士を取得する場合もあり、救急救命士と消防士は密接な関係にあります。
2.救急救命士になるには
国家試験に合格し消防職員として採用される
消防署で救急救命士として働くには、地方公務員試験と救急救命士国家試験の両方に合格しなければなりません。受験する順番は先に国家資格を取得してから消防職員になる方法と、消防職員になってから国家試験を受ける方法の2通りがあります。

先に国家試験を受ける場合
先に国家資格を取得した場合、消防職員として採用されたあと、救急隊に配属されると救急救命士として働くことができます。ただし、救急現場で求められる高い専門性と対応力を身につけるために、一定期間救急隊員や消防職員としての経験を積むこともあるようです。
大学、養成所などの履修条件を満たすと救急救命士国家試験の受験資格が得られます。具体的な条件は以下のとおりです。
救急救命士の受験資格となる履修条件
- 救急救命士養成所(専門学校、大学など)で2年以上専門知識および技能を学んだ人
- 大学や高等専門学校で公衆衛生学など指定の13科目を1年以上履修し、かつ救急救命士養成所で1年以上専門知識および技能を学んだ人
- 大学で指定の科目(公衆衛生学、解剖学、生理学、薬理学、病理学、生化学、微生物学、内科学、外科学、小児科学、産婦人科学、整形外科学、脳外科学、精神医学、放射線医学、臨床実習)を修了した人
全国では61ヶ所の救急救命士養成所が指定されており、そのうち専門学校29校、大学18校となっています。救急救命士を目指す人は、近くに通える学校があるか確認してみましょう。
先に公務員試験を受ける場合
この場合は卒業した学校でどの科目・課程を修了していても問題ありませんが、まず地方公務員試験に合格し消防職員として採用される必要があります。
消防職員として一定の実務経験を積み、講習を受けることで受験資格を得られます。
救急救命士の受験資格となる実務経験
- 救急業務に関する講習の修了
- 5年以上または2,000時間以上の救急業務経験
- 自治体の救急救命士養成所で6ヶ月または一般の救急救命士養成所で1年以上の履修
なお、消防署以外の病院や福祉施設、民間救急などで救急救命士として働く場合は、資格取得後それぞれの施設で採用選考を受けることになります。
3.救急救命士の給与・データ
救急救命士の平均年収は600万円台
令和4年地方公務員給与実態調査によると、救急救命士を含む全国の消防職の平均月収は40万3,520円で、平均年収は636万3,404円(給与月額合計12ヶ月分+期末手当+勤勉手当)でした。消防職全体の平均年齢は38.4歳です。
また、消防職が所属する自治体・組合ごとの平均給与は以下のとおりです。
| 職員数 | 月収 | 年収** | |
|---|---|---|---|
| 全地方公共団体 | 16万2,589人 | 40万3,520円 | 636万3,404円 |
| 都道府県 | 1万8,617人 | 49万1,043円 | 765万6,616円 |
| 市区町村組合* | 14万3,972人 | 39万2,202円 | 619万6,813円 |
| 指定都市 | 2万9,041人 | 43万377円 | 674万140円 |
| 一部事務組合等* | 5万2,030人 | 37万2,058円 | 588万8,777円 |
*消防は必ずしも一つの自治体が一つの組織を有するわけではなく、広域の複数自治体が組合を結成し、そのエリア内で勤務することがある
**年収は給与月額合計12ヶ月分+期末手当+勤勉手当として試算
救急救命士にまつわるデータ

4.救急救命士のさらなる活躍に期待
1991年に救急救命士法が制定されてから、救急救命士の登録者数は年々増加し、近年では救命処置の範囲も広がりつつあります。災害救助や医療現場のタスクシフトへの貢献、救急搬送と病院での治療をつなぐスペシャリストとして、今後もさらなる活躍が期待されています。