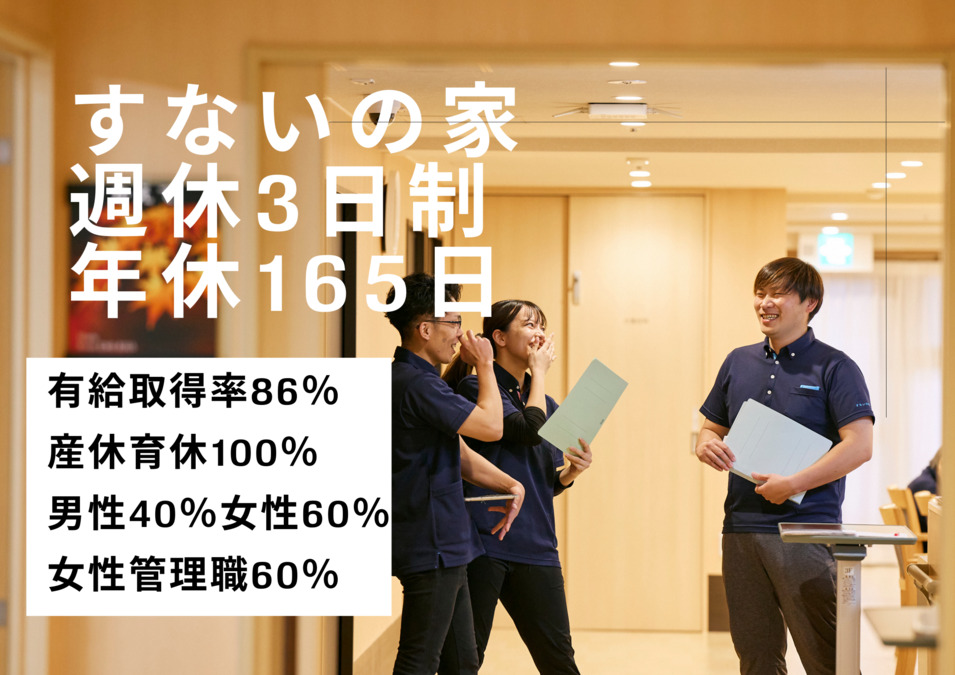はじめに
介護現場では朝から大きな声が聞こえます。
A施設「〇〇さんおはよう!今日もいい天気だよ!」
B施設「〇〇さんおはようございます!今日もいい天気ですよ!」
……あれ?施設によって敬語の施設もあればため口の施設もありますね。施設によって考え方が異なるため、このような違いがあります。では敬語とため口、どちらが介護現場にふさわしいのでしょうか。
介護現場における敬語とは
そもそも“敬語”って何でしょうか?
敬語の歴史は古く、古代にまでさかのぼります。身分制度があった時代、上位の方々を敬う意味合いで敬語が作り上げられています。敬語には「尊敬語」「謙譲語」「丁寧語」の大きく3種類があります。それぞれの違いはこちらです。
相手を立てる言葉
例)
・家族が来る
⇒ご家族がいらっしゃる
・ご飯を食べてください
⇒ご飯を召し上がってください
【謙譲語】
自分がへりくだり、相手を立てる言葉
例)
・看護師の〇〇さんに言っておく
⇒看護師の〇〇さんに申し伝えます
・うん、わかった
⇒はい、かしこまりました。
【丁寧語】
相手を問わず丁寧に述べる言葉
例)
・テレビ見る?
⇒テレビ見ますか?
・新聞読む?
⇒新聞読みますか?
最近の敬語は、相手を尊敬する姿勢を見せるという意味で敬語を使っていることが多いです。一部の高級有料老人ホーム等では謙譲語を使っていますが、ほとんどの介護現場では丁寧語が使われていますね。利用者さまに対して尊敬の気持ちを表現する。これが敬語を使う目的です。
介護現場におけるため口とは
とある介護施設の施設長から、「介護施設で敬語? いやいや、敬語なんて使っていたら利用者さんがお客さまみたいな感覚になってしまい、帰宅願望が強くなって困ったのよ!」と言われたことがあります。
たしかに家族で一緒にいる時に敬語は使わないですもんね。「私たちは利用者さんを家族としてお迎えします」というコンセプトの場合は、家族同様ため口で接するのも大切なコミュニケーションテクニックだとも言えます。
ため口の「ため」は元々、博打用語なのだそうです。「同じ目(ぞろ目)」のことを「ため」という隠語で表したのだそうです。そこから言葉が流行となり、同じことを「ため」と呼ぶようになり、同級生や同い年のことを「ため」と少し意味合いが変化して定着しました。
介護現場におけるため口は、あなたのことを同じ仲間、同じ家族だと思っているよという姿勢の表れであって決して悪いことではないのかもしれません。
敬語・ため口のメリット・デメリット
敬語とため口にはそれぞれどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
・尊敬の気持ちを伝えることができる
・丁寧な印象を与えることができる
・適度な距離感を保つことができる
◆敬語のデメリット
・相手に必要以上に気を遣わせてしまう
・お客さま感覚を与えてしまう
◇ため口のメリット
・心の距離を近くすることができる
・仲間、家族のような安心感を与えられる
◆ため口のデメリット
・乱暴な印象を与えてしまう
・距離が近くなりすぎてしまう
・ご家族からの印象が悪く見える
言葉はあくまでもコミュニケーションツールです。ツールは使う側の使い方がとても重要です。敬語やため口を使うにしても、「何のためにこの言葉を使うのか」「どうしてこの言葉でないといけないのか」を常に考え、意識することが大切だと思います。
たとえば、百貨店の野菜売り場の店員さんはとても丁寧な言葉づかいで接客をしています。一方、商店街の八百屋さんはため口で接客していますが、悪い印象を持っている人は少ないと思います。結局は、「言葉を誰のために何のために使うのか」が重要だと思います。
また、敬語で丁寧に話しているのにいい加減な仕事をしていれば、丁寧な印象は与えることはできません。当たり前ですね。言葉だけでなく立ち振る舞いにも気をつけましょう。
言葉遣いにおけるクレーム例
敬語とため口の使い方を誤ってしまうと、利用者さまからのクレームにつながることも。以下にクレーム例をいくつかご紹介します。
*利用者の家族からのクレーム
・「食事の風景を見ていたら、職員さんが『〇〇さん、お口をアーンと開けて』と言っている風景を見てしまいました。父は元大学教授で多くの生徒の前で教鞭をとっていました。その父がアーンしてと言われているなんて、とてもショックでした」
・「母の膝に青あざができていたので、『あざができているんですがどこでぶつけました?』と聞くと、職員さんが『こんなんあざのうちに入らないわよ。つばでもつけといたら?』と笑いながら言われました」
・「父の爪が伸びていたので『爪を切ってください』とお願いしたら、『あーはいはい。ちょっと待っててくださいね』と言われたので2時間待っていたのに、結局職員は来ませんでした。事務所に行くとその人はお弁当を食べていて、怒る気力も失せました。『ちょっと待ってね』と言って父もずっと待たされていると思うと不憫でたまりません」
・「施設に入所している母に久しぶりに会ったら元気がなくなっていたので、職員の方に母の様子を聞こうと思って声をかけたら、『あ、僕担当じゃないので知りません』と言われました。担当じゃなくても毎日会ってたらその様子を教えてくれたらいいのに…」
・「施設から帰ろうと駐車場に行くと職員がタバコを吸っていて、母のことを『〇〇ちゃん超おもしろいよな』と「ちゃん」呼ばわりしていました。しかも『超おもしろいって何?』と思って腹が立ったので声かけようと思ったけど、ここでクレームを言ってあとで虐待されたら怖いから黙って車で帰りました。母が心配でなりません」
一方で、現場で働く職員同士も言葉のコミュニケーションに不満を抱えていることもあるようです。
*現場の職員からのクレーム
・「オムツ交換が終わったら『あいつの排泄物くっせーんだよ』と言いながら舌打ちをする職員がいてとても不愉快です」
・「『よくできたね、よしよし』と頭をなでる同僚がいるが、これって失礼ですよね?」
・「うちの施設のリーダーは『〇〇ちゃんは適当に言っておけば大丈夫。どうせ忘れるんだから』と利用者さまをバカにした発言をする。その場ではそうですねと合わせていますが、耐えられません」
・「お化粧が好きな利用者さまに口紅を塗らせていただいた。他の職員の方にお見せしようと車いすを押していたら『あらー〇〇ちゃん、唇だけきれいね』とニヤッと笑う職員がいた」
「4月入社の新人職員から『了解っス』『そうッスね』と言われる。『ッス』は敬語ではない」
介護における真のコミュニケーションとは
極端なことを言うと、敬語だろうがため口だろうが、相手の状況を理解して心を込めて言葉を選べば誰も嫌な思いをすることはないと思います。結局は心を込めて接することが大切です。
コミュニケーションとは、日本語で「通信」のこと。心を通わせ、相手を信じて対話をしていく。これがコミュニケーションの本当の意味だと思います。また、そのためには言葉だけでなく以下のような非言語のコミュニケーションが重要です。
介護現場で有効な非言語コミュニケーション
・笑顔で声をかける
・手をさすりながら話しかける
・目線の高さを合わせて話しかける
・手を拡げて受容の姿勢を見せる
・相手が話している時に大きくうなずき共感する
このように言語的なコミュニケーションと非言語コミュニケーションを適切に組み合わせて、利用者さまに合わせたコミュニケーションを取ることにより、利用者さまからの信頼を得ることができ、円滑なコミュニケーションを取ることができると思います。
利用者さまから「失礼」「上から目線」などと言われないようにするためには、言葉遣いとともに介護職員自身の姿勢を正すことが大切です。
最後に
みなさんに知っていただきたい言葉をご紹介します。
言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。
行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。
習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。
性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。
(マザー・テレサ)
言葉に気をつけることがみなさんの運命を左右することになるかもしれません。敬語、ため口に関わらず、言葉の内容にも十分気をつけましょう。