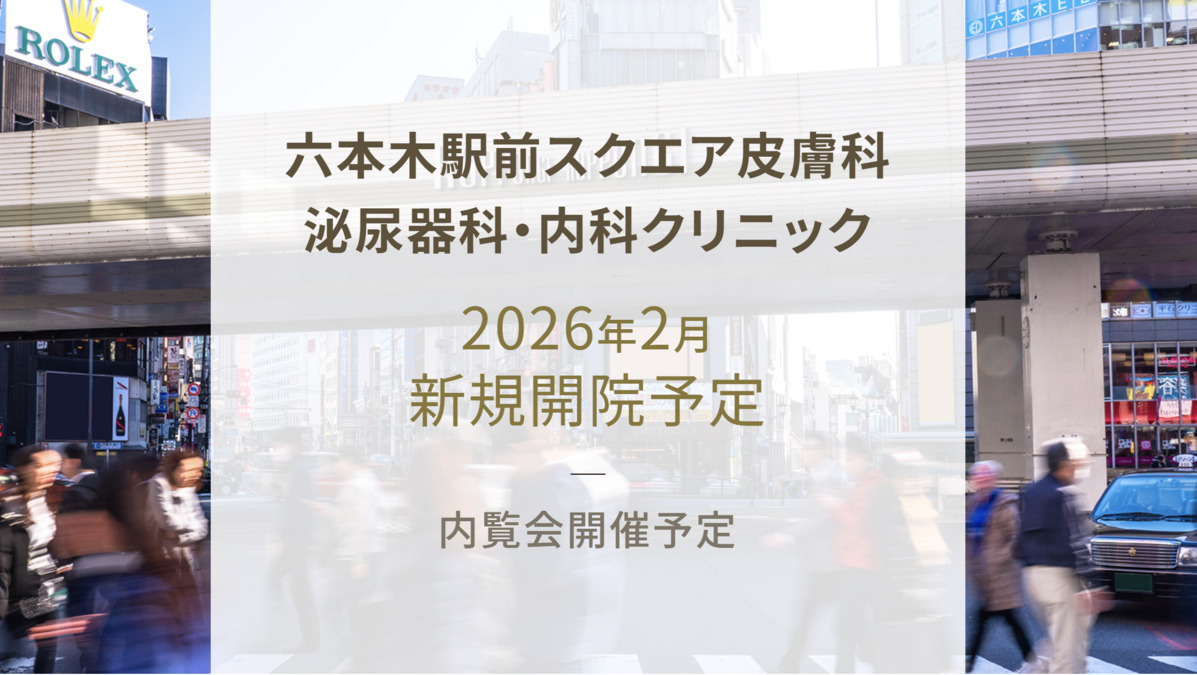1.代表的な診療科ごとの仕事内容や特徴
・外科
・整形外科
・内科
・小児科
・眼科
・産婦人科
・耳鼻咽喉科
・皮膚科
・精神科
・救急科
・放射線科
・麻酔科
2.医師になるには
2-1.医師免許の取得までは6年
2-2.医師国家試験の概要・合格率など
2-3.医師臨床研修制度とは
3.医師の給与
4.最後に

1.代表的な診療科ごとの仕事内容や特徴
医師が診察する身体の部位や疾病は、診療科ごとに大きく異なります。ここでは代表的な診療科とその特徴についてみていきましょう。
<外科>
主に手術によって病気や怪我の治療をおこなう診療科です。「外科」と一口に言っても様々な分野に分かれており、消化器外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科・気管食道外科など多岐に渡ります。
医師数 35,295人
おおよその男女比 7:3
※厚生労働省:「医師・歯科医師・薬剤師調査(2020年)」より算出(以下同様)
<整形外科>
骨や関節、またはその周囲の筋肉などの「運動器」の機能改善を目的とした治療をおこないます。背骨や骨盤など、身体の中心となる部位や四肢が主な治療対象部位です。
診療対象となる症状は外傷全般、打撲、捻挫、骨折、脱臼、関節痛、四肢のしびれなど様々です。
医師数 22,520人
おおよその男女比 8:2
<内科>
身体の内側(内臓・血液・神経など)の疾患を扱う診療科です。手術をおこなわず、主に投薬による治療をおこないます。
外科同様に、消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・神経内科など様々な専門分野に枝分かれします。
医師数 117,767人
おおよその男女比 6:4
<小児科>
小児科は子どもの総合的な疾患を扱う診療科です。対象とする年齢と扱う疾患が幅広いため、相応の知識が必要とされます。日本小児科学会では「0歳から成人するまで」が対象となっていますが、医療機関によっては「15歳まで」など上限を決めている場合もあります。
医師数 17,997人
おおよその男女比 3:7
<眼科>
目を専門的に診療する眼科は、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層を対象とします。目に関連する疾病であれば手術もおこなうため、精密な技術も要します。
医師数 13,639人
おおよその男女比 3:7
<産婦人科>
産婦人科は、産科と婦人科の両方を兼ねた診療科です。産科は妊婦の検診や出産、母体と新生児のケアなどをおこない、婦人科は子宮や卵巣などに関わる女性特有の疾患を扱います。
医師数 13,673人
おおよその男女比 3:7
<耳鼻咽喉科>
耳鼻咽喉科は耳・鼻・のど等の疾患を中心に診療します。めまい、耳鳴り、アレルギーなどの内科的な治療のほか、副鼻腔(鼻腔に隣接した骨内に作られた空洞)や耳の内部(内耳・中耳)、咽頭・扁桃などの外科的手術をおこなうこともあります。
医師数 9,598人
おおよその男女比 5:5
<皮膚科>
皮膚科では全身の皮膚や爪に関する症状を診療します。虫刺されから、皮膚がんや美容医療まで、皮膚に関する疾患はすべて扱います。男性が非常に多い医師業界ですが、皮膚科医は半数以上を女性が占めています。
医師数 9,869人
おおよその男女比 2:8
<精神科>
精神科では不安やイライラなどの気分症状から、統合失調症やうつ病、発達障害、認知症などのケアを実施します。また、アルコールなどの依存症も診療範囲内です。生物学的な指標では症状を判断しづらいため、患者さんとのコミュニケーションが重要となります。
医師数 16,490人
おおよその男女比 5:5
<救急科>
緊急度・重症度の高い救急患者を24時間体制で対応する救急外来です。ときには他科や救急隊とも連携しながら、限られた時間の中で迅速な判断と処置を施します。災害拠点病院に勤務している医師は、病院内で選抜されることでDMAT(災害派遣医療チーム)の一員として活躍することも可能です。
▼DMATについてはこちらの記事もチェック!
“避けられた災害死”を未然に防ぐ 災害派遣医療チーム「DMAT」の仕事内容・資格・待遇など
医師数 3,950人
おおよその男女比 6:4
<放射線科>
放射線科で働く医師は、X線写真・CT・MRIなどの画像検査によって病気を見つけ出し、病変に対して放射線を照射することで、患者さんを切らずに治します。放射線療法は手術療法と化学(薬物)療法に並ぶ、がんの三大治療法のひとつとして数えられます。
医師数 7,112人
おおよその男女比 5:5
<麻酔科>
麻酔科では手術や治療における痛みを取り除くだけでなく、手術中の患者さんの安全を確保するための全身管理もおこないます。またペインクリニックにおいては、あらゆる痛みを緩和するための治療をおこない、患者さんのQOLの向上に努めます。
医師数 10,277人
おおよその男女比 3:7
2.医師になるには
2-1.医師免許の取得までは6年
医師になるためには、まず医師国家資格に合格する必要がありますが、誰でも受験できるわけではありません。
医師国家試験の受験要件として、基本的には大学の医学部へと進学し、6年間のカリキュラムを修めて卒業(見込みも含む)する必要があります。
受験資格についての詳細は厚生労働省HPをご覧ください。
2-2.医師国家試験の概要・合格率など
医師国家試験は毎年2月上旬~中旬に2日間に渡って実施されます。問題数は計400問出題されます。
2025年(令和7年)2月8日(土)・9日(日)に実施された第119回医師国家試験の合格者数および合格率は下記の結果でした。
合格発表:2025年3月14日(金)
受験者数:1万282人(9,507人)
合格者数:9,486人(9,029人)
合格率:92.3%(95.0%)
※()内は新卒者のみの割合
直近5年間の合格率は横ばいで、約91%〜92%で推移しています。
2-3.医師臨床研修制度とは
国家試験に合格することで医師としてのスタートラインに立つことができますが、臨床医として活動するためには、さらに2年間の初期臨床研修が必要になります。一般的に「研修医」と呼ばれる期間です。
研修は実際に病院で勤務しながら実施され、各病院のプログラムに沿った期間で様々な診療科を回ります。
研修をおこなう病院は、医学部の6年次に実施される「医師臨床研修マッチング」というシステムにより決定されます。研修希望者は医療機関を第1希望・第2希望・第3希望という形で登録し、医療機関側も受け入れたい人材を希望順位付きで登録。互いにマッチした医療機関にて研修をおこないます。
3.医師の給料
厚生労働省が発表した令和5年賃金構造基本統計調査によると医師の男女別平均給与は次のようになりました。
| 毎月決まって支給される給与 | 年間賞与・その他 | 平均年収 | |
|---|---|---|---|
| 男性医師 | 115万4,200円 | 136万5,900円 | 1,521万6,300円 |
| 女性医師 | 87万5,900円 | 97万2,700円 | 1,148万3,500円 |
| 男女計 | 109万700円 | 127万6,300円 | 1,436万4,700円 |
金額は地域や経験年数などによってもバラつきが出るため、あくまでも全体の平均として参考程度にとらえておきましょう。
4.最後に
地域や診療科による医師の偏在問題が取り合げられてしばらく経ちます。政府は2008年度以降、医学部定員を大幅に増員するなどの対策に乗り出しており、多くの診療科で医師は増加傾向にあるものの、依然として偏在は解消されておらず、厚生労働省は「地域や診療科によっては医師不足である」と指摘しています。
人口10万人当たり医師数が最大・最小の二次医療圏の比較

診療科別医師数の推移(平成6年を1.0とした場合)

引用:厚生労働省/医師偏在対策について
医師の地方勤務について注目してみると、厚生労働省の発表した医師・看護師等の働き方ビジョン検討会の調査資料では医師の44%が「地方で勤務する意思あり」と回答しています。特に20代では60%、30代では52%と、若手医師の半数以上が地方で働く意欲があることがわかります。
では、なぜ地方における医師不足が起きるのか。同様の調査によると、20代医師の「地方勤務する意思がない理由」として最も多かったのは「労働環境への不安」、次いで「希望する内容の仕事ができないこと」でした。
いまの日本では、多くの団塊世代が退職するとみられる2025年問題が差し迫っており、地方の医師不足がさらに加速するのではという懸念があります。「医師が不足している中では、労働環境を整えることは難しい」という見方もできますが、今後の医師確保のためにも、医師が地方でも働きやすくなるよう何らかの対策を打ち出す必要があるでしょう。

 参考:厚生労働省|医師国家試験の合格発表(
参考:厚生労働省|医師国家試験の合格発表(