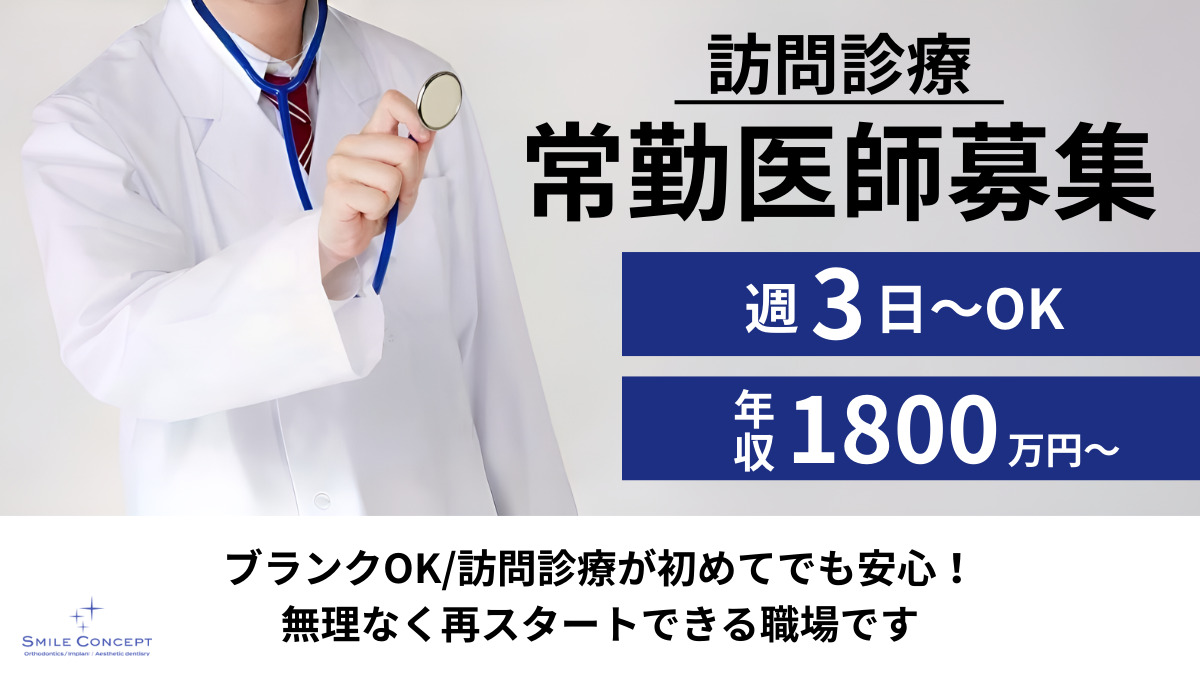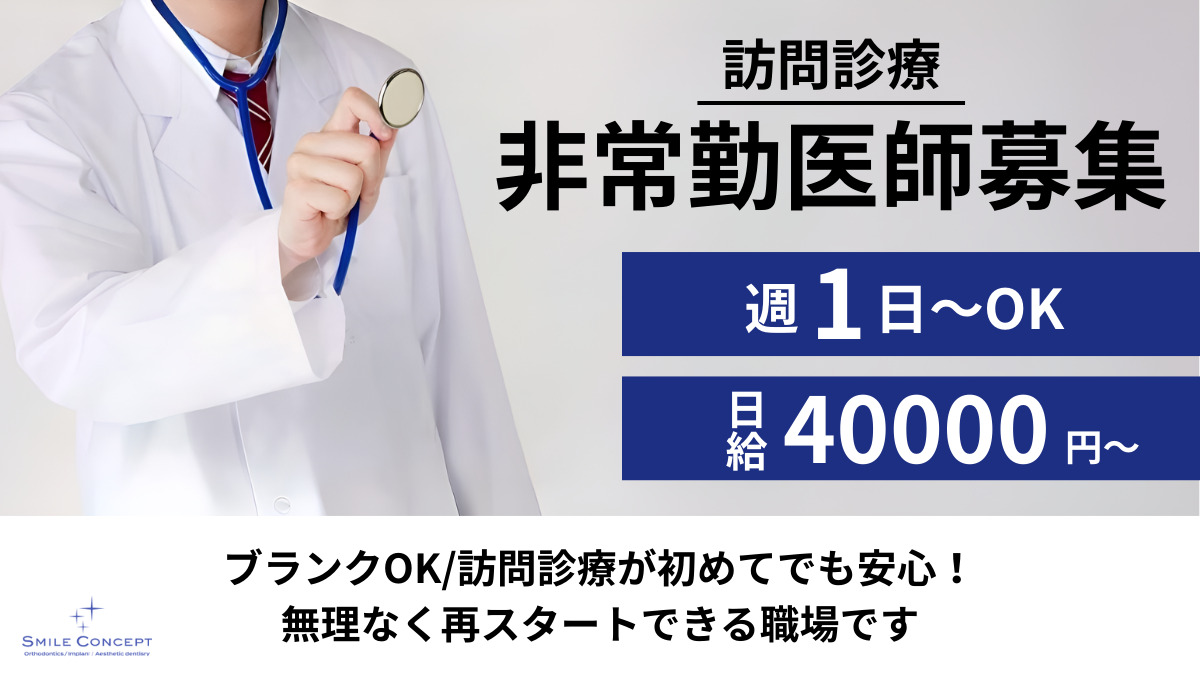1.ポリファーマシーとは
ポリファーマシーとは、「複数」を意味する「poly」と「調剤(薬局)」を意味する「pharmacy」からなる、「害のある多剤服用」を意味する言葉です。
重要なのは「害のある」という部分。単純に「服用する薬の数が多い」ということではありません。
必要とする以上の薬や不要な薬が処方されていることによって、有害事象のリスク増加や、誤った方法での服薬(服薬過誤)、服薬アドヒアランス低下などの問題に繋がる状態を指します
用語解説
患者が自分の病気を理解し、医師の治療方針に積極的に協力しながら正しく服薬すること
■ ポリファーマシーの定義
患者さんの症状や病態、生活環境などによって、薬の適正な処方も変化します。
そのため「何種類の薬を併用していたらポリファーマシーに該当するのか」、という厳密な定義は存在していません。
しかし、薬による有害事象(薬物有害事象)は処方された薬の数に比例するとされ、薬の数が6種類を超えると発生頻度が大きく増加というデータを、日本老年医学会が「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」で発表しました。
一方で、治療に適正な薬の数が6種類を超えることも当然ありますし、処方された薬の数が少なくても問題が発生することもあります。
一番大切なのは処方された薬の数ではなく、その処方内容が適正かどうかという点であることを覚えておきましょう。
point
副作用:薬の使用により生じた、薬との関連を否定できない有害な反応
薬物有害事象:薬の使用後に発生する有害な症状で、薬との関連を問わない事象
2.ポリファーマシーの背景と現状

ポリファーマシーが発生してしまう背景として、急速に進む日本の高齢化があげられます。
高齢者はさまざまな疾患を抱えていることが多く、複数の医療機関にかかっていることは珍しくありません。
この場合、それぞれの医療機関で処方されている薬は2〜3種類だとしても、受診先が増えるごとに薬も足されていくため、結果的にポリファーマシーが発生しやすい環境となります。
2015年に日本調剤株式会社が実施した「シニア世代の服薬の実態と意識」の調査では、高齢者の約半数が2ヶ所以上の医療機関に通っており、5種類以上の薬を処方されている人が最も多いことがわかりました。
定期的に通院している医療機関数
| 回答者数 | 割合 | |
| 1ヶ所 | 497 | 47.5% |
| 2ヶ所 | 369 | 35.3% |
| 3ヶ所 | 138 | 13.2% |
| 4ヶ所 | 33 | 3.2% |
| 5ヶ所以上 | 9 | 0.9% |
処方されている薬の数
| 回答者数 | 割合 | |
| 1種類 | 242 | 23.1% |
| 2種類 | 242 | 23.1% |
| 3種類 | 176 | 16.8% |
| 4種類 | 127 | 12.1% |
| 5種類以上 | 259 | 24.8% |
参照:日本調剤株式会社 2015年 「シニア世代の服薬の実態と意識」
また、薬の副作用や有害事象を抑えるために新たな薬を処方し、その新たな薬の副作用を抑えるためにまた別の薬を処方……というように、薬物有害事象を新たな薬で対処し続ける「処方カスケード」も、ポリファーマシーを形成する可能性が高いとして問題になっています。
処方カスケードの例

3.ポリファーマシーの何が問題なのか
ポリファーマシーが問題視されている大きな理由として、これまでにも述べているように「患者さんにとって有害だから」という点がまずあげられます。
薬物有害事象には、軽いめまいやふらつきから、肝機能障害や低血糖を引き起こすもの、果ては死亡にいたるものまであります。ふらつき程度のものでも、転倒し骨折するなどして今後のQOLに大きく影響することもありえるでしょう。
また、多くの薬が処方されるということは、国民医療費の増大にも繋がります。
そのなかでも調剤医療費に注目してみると、2000年から2018年にかけて2.5倍以上にも増え、2018年度には国民医療費全体の17.6%を占めています。
なお、調剤医療費は薬剤料+技術料で構成されています。

参照:厚生労働省 /医療費の動向」
4.ポリファーマシーの対策
ポリファーマシーを回避するには、まず多剤併用を避けるよう医師をはじめとする医療スタッフの心がけが大切です。
だからといって、本来処方されるべき適切な薬の数を減らしてしまっては本末転倒。
日本老年医学会が発行した「高齢者の安全な薬物療法 ガイドライン2015」では、多剤併用を避けるために、各薬剤の適応について次の点を見直すよう喚起しています。
・予防薬のエビデンスは妥当か
・対症療法は有効か
・薬物療法以外の治療手段はないのか
・優先順位は適正か
また、高齢者は加齢による生理的な変化(例:肝機能や腎機能の低下など)によって一般の成人とは薬物の反応や効果の度合いが異なる場合がある点や、生活習慣病をはじめ複数の疾患に罹患していることでそもそも服用する薬が多い点などから、薬物有害事象のリスクが高いといえます。
そのため高齢者に対して、有害事象を起こしやすい薬剤の選択は最適とはいえず、投与を控えたり、少しづつ慎重に投与したりすることが望ましいとされています。
有害事象のリスクが高い薬剤は「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」 において、「特に慎重な投与を要する薬物のリスト」としてまとめられています。
また薬剤師ができる取り組みとして、お薬手帳の適正使用の呼びかけ(医療機関ごとに手帳を分けずに1冊の手帳で管理するよう促すなど)、必要に応じた減薬の提案、服薬管理による残薬解消、処方箋の疑義照会などがあります。
5.ポリファーマシーを解決するために
前章でも述べているとおり、ポリファーマシーを解決するには、ただ処方する薬の数や量を減らせばいいというわけではありません。
薬を処方する医師、患者さんをケアする看護師、調剤をおこなう薬剤師などをはじめとし、医療に関わるそれぞれの専門家が協力し合い、患者さんの情報を共有し、適正処方を心がけていくことが重要です。
また患者さん自身も、受診の際にお薬手帳を忘れずに持参する、かかりつけ薬局を持つことで複数の医療機関を受診していても薬の管理を一元化してもらうなど、使用している薬について積極的に医療従事者との情報共有をおこなうことが重要です。
ポリファーマシーの解決には、医療従事者と患者さんが一体となり、互いに協力して取り組むことが何よりも大切です。