大学院修了後、特別養護老人ホームに介護職として入職したMさん。しかし、当時は業務にも職場にもなかなか馴染めず、1年半ほどで退職してしまいました。
その後は翻訳の道に進み、特許翻訳者として13年間勤務。「自分に合っている」と感じていた仕事でしたが、3年前、再び介護の世界に戻る決断をしました。
オフィスワークと介護現場という異なる環境を経験したMさんに、これまでのキャリアや介護職に戻って感じること、今後の展望を聞きました。
話を聞いた人

介護福祉士 Mさん
大学卒業後は学習塾で勤務したが、言語学の道を諦めきれず、退職して大学院に進学。イタリア語の文法研究に取り組んだのち、特別養護老人ホームに就職した。1年半で退職したあとは、英語力を活かして13年間、特許翻訳の仕事に従事。3年前に特別養護老人ホームへ転職し、現在は10人の入居者の介助を担当している。
「私には介護をする資格がない」
──まずは、大学院を出るまでの経歴について教えてください。
大学卒業後、1年だけ学習塾で講師をしていました。学部の専攻は法学部だったんですが、在学中に抱いた言語学への興味を捨てきれず、塾を退職して大学院に進学したんです。大学院ではイタリア語の文法研究をしていました。でも、文系の研究職は本当に狭き門で、研究室の先輩が何年も空きポストを待ち続けている姿を見て、修了後は就職しようと決めました。

──大学院から特養に就職したのはなぜですか? 経緯を教えてください。
そのまま大学に残って職員になろうかとも考えたのですが、前年に私の研究室から内定辞退者が出たことで、当分採用しないという話になってしまって。それで、慌てて就職活動を始めたんです。ほかの大学の職員や学習塾を中心に受けたんですが、修士課程は敬遠されることもあって、なかなか書類も通りませんでした。
家族が医者をしていたので、医療や福祉の仕事は小さいころから身近でした。それで、就職先としても自然と病院や施設に目が向いていったんです。新卒を募集している特別養護老人ホームが家の近くにあったので、そこに応募して就職しました。
──最初から高齢者福祉に関心があったわけではなかったんですね。実際に介護の仕事を始めてみていかがでしたか?
もう、見るものすべてが新しく感じました。それまで、認知症の方に接したこともなかったですし、食事介助から担当し始めたんですが、入居者さんが口を開けてくれるタイミングが全然わからなくて。スプーンを近づけても口を開いてもらえないし、「どうしたらいいんだ」と困った記憶があります。
──新卒でいきなり現場に入ると、やはり大変ですよね。
本当に毎日が修行でした。同期が何人かいたんですが、私が一番出来が悪かったんです。食事の介助もうまくいかないし、おむつ交換も遅いし。何ヶ月かすると夜勤に入るんですが、私一人だけ任せてもらえない状態がしばらく続きました。
──同期と差がついてしまうと精神的にもきつかったのでは?
社会人としてどんどん自信がなくなってしまいました。自信のなさは入居者さんにも伝わってしまうもので、余計に信頼が得られなくなるという悪循環でした。
当時は業務を時間内にこなすことで精一杯でした。時間にとらわれてしまって入居者さんの気持ちをくみ取ることができなかったんですね。
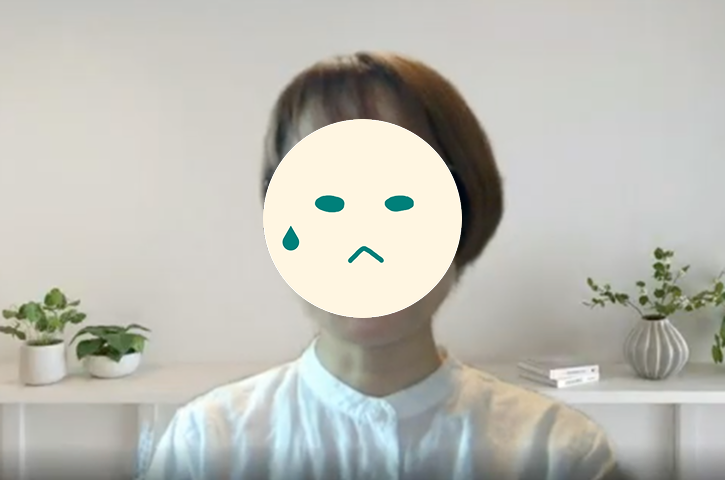
──先輩に相談はしましたか?
いえ、できていませんでした。わからないことがあっても自分で解決しようとしてしまって……。いま思えば、人に聞く姿勢が足りていませんでした。先輩に「どうしたらいいんでしょうか」とちゃんと言葉にして聞くことができていなかったと思います。
先輩たちからすれば、「この新人は何も聞いてこない、いつまで経っても成長しない」という印象だったと思います。
──なかなかなじめないなかで、具体的に退職を考え始めたのは何かきっかけがあったんですか?
夜勤明けに入居者さんを介助しているとき、足を踏んで出血させてしまったんです。結局大きなケガではなかったんですが、そのときは本当にショックでした。帰ってきてからずっと泣いてしまって、「私には介護をする資格がないんだ」「このままで続けたら人を殺してしまうんじゃないか」とまで思いました。
体力的にもきつくなっていました。夜勤は16時間勤務だったのですが、仮眠時間もぜんぜん気が休まらなくて。結局、入職から1年半で退職してしまいました。
特許翻訳という“居場所”を見つけた
──次の仕事はどのように見つけたんですか?
本当に偶然なんです。漠然と「何かいい仕事ないかな」と求人サイトを見ていたら、「英語ができる人募集」という特許事務所の翻訳の求人が出ていたんです。家からは少し距離がありましたが、大学院では文献が基本的に英語だったので、「これならできるんじゃないか」と思って応募したら、1ヶ月くらいで決まりました。

──特許翻訳とはどんな仕事ですか?
発明を特許として認めてもらうためには、技術の内容を書いた「明細書」という書類を特許庁に提出する必要があります。さらに、特許を国際的に認めてもらうために、この明細書を英語に翻訳して外国の特許庁に提出するのが、特許翻訳の仕事です。
明細書の翻訳は型がある程度決まっているので、過去に提出した文書を参考に作成できます。ゼロから全部考えるわけではないので、覚えやすい仕事でした。
──介護の仕事とは違うデスクワークですよね。すぐに慣れましたか?
朝から晩まで基本的に1人でやる仕事なので、気持ちが楽でした。介護の現場とは180度違って、決まった日程に向けて自分で準備していくという感じで、自分のペースで仕事ができるのが合っていたんですね。
特許翻訳の仕事は自分に向いていると感じていましたし、評価もいただいていたので、13年間楽しく仕事ができました。環境が変わらなければ、このまま続けても全然良かったんですけどね……。
AIに代替されない仕事を探して
──仕事に満足しているなかで、慣れ親しんだ職場から転職を考えたのはなぜですか?
特許事務所へは数時間かけて通っていたのですが、家族の事情で地元で働きたいという気持ちが強くなったことがきっかけですね。年齢も30代半ばを迎え、将来の親の介護のことも考えると、そろそろ戻るタイミングだと思ったんです。
それとコロナ禍以降は、バスの便数がすごく減って、通勤がかなりきつくなってきたことも転職につながりました。朝のバスは混雑するし、渋滞で遅れることもある。帰りのバスに乗り遅れたこともあって、この先長く通い続けるのは厳しいと感じ始めたんです。
それと、この10年でAIの精度がすごく上がって、人がゼロから翻訳する必要がなくなってきたんです。お客さんからも機械翻訳を使って、その代わりに単価を下げて欲しいという依頼も出てくるようになり、AIに仕事を奪われる危機感を感じました。
──ほかの翻訳の仕事などでなく、介護に戻ろうと考えた理由は?
「AIができない仕事は何だろう」と考えたとき、私が定年するまで、介護の仕事はまずなくならないだろうと思ったんです。
それに、介護にはデイサービスとか訪問介護とか、いろいろなスタイルがあるじゃないですか。年齢の変化に伴って働き方も変えられそうだと思いました。
──介護業界は10年以上のブランクがありますが、転職活動はスムーズでしたか?
求人サイトからスカウトが来るので、自分の希望条件と合うところに絞って面接を受けました。勤務地が地元で家から近いこと、お給料、福利厚生が充実しているかなどを重視しました。
面接でも「どうして介護に戻ってこようと思ったんですか」と聞かれたので、AIのことや、この先も続けていける仕事に就きたいということを、正直に答えました。
社会人経験で生まれた心のゆとり
──転職した特養の特徴や働き方を教えてください。
今の地元の職場はユニット型の特養で、10人の入居者さんを担当しています。早番・遅番・夜勤のシフトで、夜勤は22時から朝7時までの9時間です。新卒のころの16時間の夜勤勤務とは全然負担が違いますね。
──働きやすい職場なんですね。新卒では“挫折”も経験した介護の仕事ですが、そのころと比べてご自身にも変化はありますか?
一番大きいのは、心のゆとりだと思います。想定外のことが日常的に起こるし、入居者さんが自分の業務スケジュールどおりに動いてくれないのも当たり前だと思えるようになりました。
ユニット型で人数が少なく、一人ひとりに合わせて介護できるということもうれしいですね。今では突発的な事態も含めて、1日の業務を楽しめるようになりました。
──具体的にはどんな場面でやりがいを感じますか。
意思疎通が取れない方も多いんですが、日々観察しているなかで「この様子のときはトイレに行きたいんだな」というように、入居者さんの気持ちがわかってくると、すごくやりがいを感じますね。
それと、今はちゃんと周囲に「ここがわからないんです」と伝えられるようになりました。先輩たちも本当に親切にしてくれて、休憩中でも教えてくださったり、さりげなく終わっていない仕事を手伝ってくれたりと、本当に恵まれた環境です。

──今振り返ると、新卒のときは何がうまくいかなかったと思いますか。
業務をこなそうとするあまり、入居者さんの声を聞くということができていませんでした。
そもそも社会人としての経験も足りなかったとも感じます。特許事務所で働いてきたなかで、わからないところはちゃんと聞くとか、人に相談するとか、そういうことが身につきました。また、誰でも得意なこと、苦手なことがあるということを学んだ13年間だったと思います。
──今の職場では資格も取得されたんですよね。
はい。入職から1年後に実務者研修を受講して、今年1月に介護福祉士の試験を受けて合格しました。
試験勉強は得意だったので、薄いテキストから勉強し始めて、過去問や分厚い参考書に取り組むという感じで進めました。夜勤中も勉強して、試験の準備をしていました。同僚も応援してくれていたので、一回で合格できて良かったです。
──一発合格なんですね! 介護福祉士の資格や勉強した内容は、日々の業務にも役立っていますか?
移乗や着脱などの介護技術、高齢者に多い病気など、細かい知識は業務に役立っています。資格手当もありますし、キャリアアップという点でも本当によかったと思っています。
それにもしこの先、年齢を重ねて施設を変えたり、転職したりするときも、介護福祉士を持っていると有利になるかなという気持ちもあります。
介護にはどんな経験も活きる
──介護職とオフィスワークの両方を経験したうえで、それぞれの良さはどう感じますか?
オフィスワークのほうが楽だと思う人もいるかもしれませんが、1日8時間トイレに行く以外ほとんど座って、パソコンを見続けるという大変さもありますよね。それに比べて、体を動かして汗をかいて働く介護の仕事って、結構気持ちいいなと思うようになりました。
あとは人との関わりですね。黙々と翻訳をするのも好きですが、人とコミュニケーションを取りながら過ごすのもいいなと感じています。私、家ではテレビを見ないんですが、現場ではずっとテレビがついているんです。それを眺めながら入居者さんとおしゃべりする、そんな何気ない時間も好きですね。
──体力面ではいかがですか?
新卒当時よりも15歳くらい年を取っているので体力は落ちているはずなんですが、意外と平気ですね。社会人経験を積んだおかげで、気持ちにゆとりが生まれたからかもしれません。
地域に根を張って介護の道を進む
──今後のキャリアについてはどう考えていますか?
今のところは、とにかく投げ出さずに続けていくというのが一番大事だと思っています。5年経ったらケアマネの資格取得も目指したいなとも考えています。
それと、夜勤を何歳まで続けられるかわからないので、デイサービスなどもう少し介護度の低い方がいらっしゃる施設にも興味があります。いろんな方と触れ合ったほうが、スキルを磨くという意味でもいいのかなと考えています。
──介護職として働き続けるイメージができているんですね。新卒で悩んでいたころの自分に言葉をかけるとしたら、何を伝えたいでしょうか。
「どうしても無理だったら、一回辞めてほかの仕事してもいいんだよ」と言ってあげたいですね。当時は本当に自信をなくしていたので。13年間特許翻訳をやって、自分にも適性のある仕事があるんだと思えて、社会人としての自信を取り戻せました。だから、諦めなくて大丈夫だよと伝えたいです。
──最後に介護の仕事を辞めようか悩んでいる方や、復職に関心がある方にメッセージをお願いします。
介護の仕事は本当に大変だというイメージがあると思います。年齢が上がると体力的に厳しくなるんじゃないか、ハンデになるんじゃないかと感じる方が多いのではないでしょうか。私自身は13年ぶりにやってみて、年齢はハンデになるどころか、これまでの人生経験が全部役に立ってくる仕事だなと感じています。
どんな経験をされてきた方でも、それぞれの強みを活かせる場面が絶対あると思います。例えば、子育てをされてきた方はレクリエーションが上手だったり、元営業職だった方は気難しい入居者さんの説得がすごく上手だったりします。本当にどんな経験をしてきても、介護の仕事では役に立つんだなと感じています。
介護を辞めたいと思っている方がいたら、一度辞めてほかのことをやってみるのもいいと思います。そして、もし再挑戦したいと思ったら、それまでやってきたことは絶対役に立つので、ぜひ介護の仕事に戻ってみてくださいと伝えたいです。














