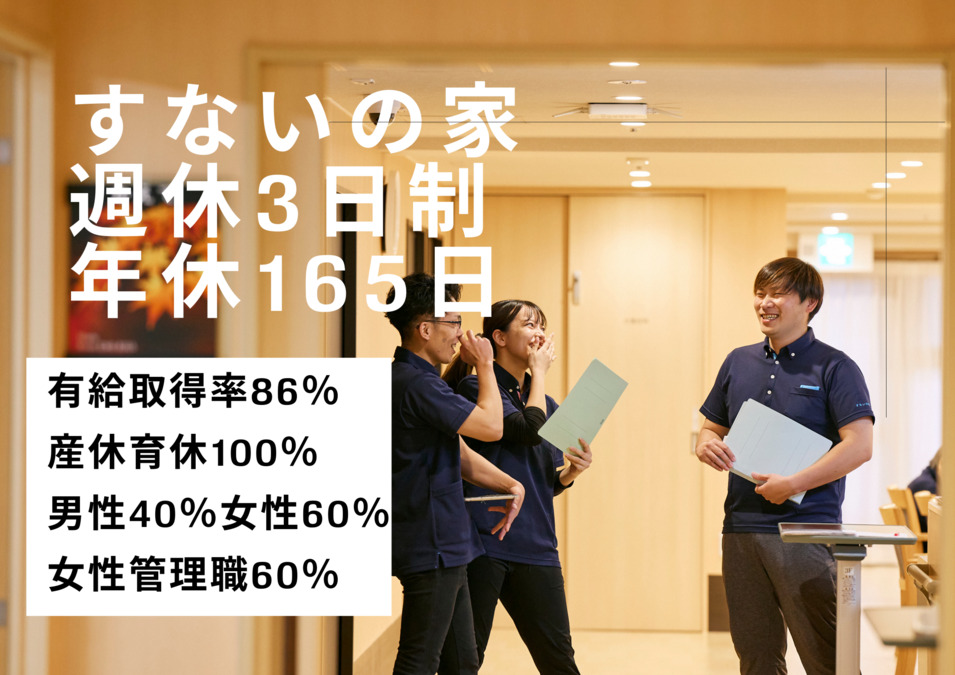超高齢社会を迎えた日本がこれから向かう先は、多死社会と言われています。医療や介護の世界で働く以上、“死”を避けて通ることはできません。容易に消化できない出来事に、自分の感情とどう向き合えばいいかと葛藤する人は少なくないと思います。
今回は介護職歴約18年の介護福祉士・中浜さんから、友人でもある納棺師の木村さんに「看取りにおいて大切なこと」をテーマにインタビューを実施。日々、人の死と対峙している木村さんは、医療や介護現場における看取りについてどのような考えを持っているのでしょうか。
話し手

木村光希(きむら こうき)さん
1988年北海道生まれ。納棺師である父親の影響を受け20歳の頃から納棺師として働く。2013年に納棺師養成学校「おくりびとアカデミー」、2015年に納棺師による葬儀会社「おくりびとのお葬式」をそれぞれ創立。
聞き手

中浜崇之(なかはま たかゆき)さん
1983年東京都生まれ。学生時代の一日デイサービス体験をきっかけに介護の世界へ。介護福祉士として施設長やデイサービス立ち上げを経験するほか、全国での講演活動やイベント主催など多方面で活躍中。
納棺師の一家に生まれ育ち、見つけた使命

中浜さん:木村くんとは5年以上前からの付き合いで、一緒にイベントを主催したり木村くんにも登壇してもらったりしているから、改めてこういう形で対談するなんて変な感じがするんだけど(笑)。
木村さん:なんかこっ恥ずかしいよね(笑)。
中浜さん:まず最初に、木村くんのことをよく知らない人のために、どうして納棺師として働くことになったのか、きっかけを教えてもらってもいいですか?
木村さん:もともと父親や親戚に納棺師が数名いたんです。僕が幼い頃は実家や自家用車には無線が設置してあって、納棺や葬儀の依頼が入ったら父親がすぐに飛んでいくような環境で。僕も兄弟も小さい頃から納棺の真似事をしていたので「自分も将来は納棺師になるんだろうな」と自然と思ってたんですよね。
納棺師の仕事を本格的に始めるようになったのは20歳くらいのときから。大学生だったので昼間は学業、夕方はサッカー、夜は納棺の仕事でほぼ寝ないみたいな、若さに頼ったハードな生活を送ってましたね(笑)。

中浜さん:その頃でしたっけ、映画『おくりびと』でお父さんが納棺師の技術指導をされたのは?
木村さん:そう、映画のヒットで納棺師が注目されるようになって、アジアの国々からも納棺の技術指導をしてほしいと依頼をいただくようになった。それがきっかけとなって2013年に独立して立ち上げたのが「おくりびとアカデミー」という、納棺師の養成学校です。
納棺師はもともと師弟間の継承が一般的だったんですよね。誰を師として教わるかによって技術や仕事観に大きな差が出てしまうし、担い手も増えていかない。この課題意識から、確かな技術水準を持つ納棺師を輩出できる養成校を作ったんです。
そこで当時からやっていて今も続いているのが、看護師さんや介護職員さんなどを対象に開催している「納棺師によるセミナー」です。今日はその講義の内容にも近いお話になるかもしれません。
看取りケアが「看取り後まで」続いてほしい
中浜さん:医療や介護現場で働いていると、看取りに関わる機会がある。そこでずばり、木村くんが医療職や介護職の人に一番知っておいてもらいたいと思うことは何ですか?

木村さん:「お看取り後まで看取りだと思ってほしい」……ということですね。いわゆる“エンゼルケア”の部分です。看護師さんや介護職員さんたちは、亡くなる直前までなるべく痛みや不快さがないよう、丁寧に丁寧にケアをされますよね。でも亡くなってしまうと、そこから先の処置のクオリティが担保されていないケースが多いと感じています。
僕たち納棺師が亡くなられた方のもとに着くのは死後数時間経ってからなんですが、髪が乱れていたり口が閉じていなかったり、つらい表情をされたままということも少なくありません。もちろんそこからお身体を整えるのが納棺師の役割なんですが、到着するタイミングが遅いと処置が間に合わなくなる場合もあります。
中浜さん:亡くなられたあとすぐの対応が重要だと。
木村さん:とくに重要なのは“保湿”です。乾燥してしまうと肌がガサガサになったり変色したりしてしまうので、そのあとのお化粧などでカバーするにも限界がある。なので肌の見える部分だけでもアルコールを含んでいない保湿剤──ワセリンやニベアなどをたっぷり塗布してもらいたいです。
中浜さん:施設によっては、止血剤や脱脂綿で処置するところもありますよね。
木村さん:そう、ご遺体から出る体液などを留めるために止血剤や脱脂綿などを入れる処置があります。ただこれはちょっと言いづらいんですが……正しい処置が難しければ、手を加えずに待っていてほしいです。
止血剤や脱脂綿などを入れる場合、適切におこなわないと止血剤が漏れてきたり脱脂綿が見えてしまったりして、故人やご遺族にマイナスな影響を与えてしまう可能性があります。例えば肛門についても、詰め物はせずに拭き取っていただいておむつ交換だけでも十分ありがたいです。
中浜さん:ちなみに、亡くなられたあとだいたい何時間以内に納棺師が処置に入るのが理想なんだろう?
木村さん:理想は3時間以内、遅くても6時間以内には処置できると良いです。
納棺師ができるだけ早く処置に入ることは、残されたご遺族の感情面を考えても大切な部分だと思います。ご遺族が故人に会う際、亡くなられたときのつらいお顔のまま対面するのはショックが大きいですから。
だからこそ、医療機関や介護施設の職員さんたちと葬儀会社側が普段から連携を取って、迅速にバトンタッチできることが重要なんです。

中浜さん:そう言われると、葬儀や納棺については、介護職の僕らは結構疎いところかもしれないな……。
木村さん:まだまだ「営業に来てくれたから」みたいな感じでなんとなく葬儀会社を選んだり、ご遺族任せにしてしまうところが多いと思います。でも医療や介護現場において“死”は切っても切り離せないものだから、施設側がお看取りのあとをしっかり任せられる葬儀会社さんを見極めて、日頃からコミュニケーションを取っていくべき時代になってきていると思います。
具体的には、お看取りの研修や葬儀に向けた情報共有などを通じて「亡くなられた際にどう対応するのか」「どういったケアをしてほしいのか」といった点を、日頃からすり合わせておく。
そうすることで適切な処置がおこなわれて、亡くなられた方の尊厳を守ることに繋がると思うし、ご遺族の方の気持ちに寄り添えるんじゃないかと。
より良い納棺・葬儀のために、職員からの「情報」がほしい
中浜さん:僕は介護の専門性の一つとして「看取りケア」があると思っていて。その方の生活を間近でずっと支えてきたからこそ、最期を大事にしてあげたい。そうなったときに、僕たち介護職や医療職にできることには何があると思う?

木村さん:直接的に助かるのは、亡くなられた方の情報を教えてもらうことですね。状況によってはご遺族からのヒアリングが難しいことも少なくないので、代わりに教えてほしいです。
その方の身体的な情報──傷がどこにあるとか、性格や趣味、好きな食べ物など何でもいいです。そういった情報をもとにお身体を整えたり、棺の中に入れるものを用意できたりするので。
中浜さん:趣味や好きな食べ物まで?
木村さん:僕らの場合だと、納棺師が納棺から葬儀まで一貫して担当する「おくりびとのお葬式」をやっていて、担当する納棺師が故人一人ひとりに合わせて用意するんです。例えばお寿司が好きな方だったら、粘土でお寿司を作って棺の中に一緒に入れたりだとか。
中浜さん:すごい! そんなことまでしてるとは。
木村さん:僕らは毎日人の死に携わるので、死が当たり前にならないように意識していて。今日の葬儀は「プランAの葬儀」ではなくて「山田太郎さんの葬儀」にしなくちゃいけない。納棺師がその意識を保ち続けるためには、そのお相手一人ひとりのことだけを考えて何かを作るという時間を大切にしてるんです。時にはご遺族にも手伝ってもらいながら。

木村さん:些細なことでもいいので、情報提供してもらえるとすごく助かります。場合によっては、離れて暮らしていたご家族よりも、毎日身近でケアしていた看護師さんや介護職員さんのほうがその方のことをよく理解しているケースもありますから。
グリーフケアは、医療・介護職員にとっても大切
中浜さん:僕の周りの介護職の人を見ていると、看取りを経験したあとの喪失感や無気力感、「もっと何かできたんじゃないか」と後悔を感じている人が多いと思っていて。医療や介護職で働く以上避けては通れないことかもしれないけど、こういった気持ちにはどう向き合ったらいいと思う?
木村さん:難しい質問だけど……一つは死を意識して、受け入れる準備をしていくことかな。「その人らしい看護や介護の実現」をするためには、ご本人やご家族の意向をしっかりヒアリングすることと、関係者たちが連携することが大事じゃないですか。お看取りもその延長線上にあるので、同じだと思います。
ご本人やご家族と密にコミュニケーションを取ったり、関係者や葬儀会社ともそのときが来たときのための連携を取っておくこと。そうやって少しずつ、死に向かっていく心の準備をしていくしかない。

木村さん:あと僕らが大切にしているのは、死別を経験した人の心を癒やす「グリーフケア」の考え方で。納棺や葬儀は亡くなられた方のためにおこなうものだけど、同時に残された人たちのグリーフケアでもあります。そしてグリーフケアは、残されたご遺族だけじゃなく、医療や介護職の人にとっても大切だと思っているんですよね。
とくに亡くなられた直後は、眠っているようにしか見えなくて実感が持てないこともあると思います。でも一緒に身体を拭いてもらうことで、冷たさから亡くなってしまったことが嫌でも感覚として伝わってくる。ご遺体をみんなで持ち上げて棺の中に入れるという体験をすることで、これが最後のお別れなんだとやっと実感できる。一見残酷なんですけど、現実を受け止めるためには必要な行いなんです。
中浜さん:でも葬儀の場となると、なかなか職員は立ち会えないですよね。
木村さん:そう、そこはやっぱり施設側の判断になってしまうから難しいところなんですけどね。でも中には僕たちがおこなう葬儀内容を知って「職員たちを立ち会わせたい」と言ってくれる施設もいて。
葬儀場に看護師や介護職の方たちが参列しているところをご遺族が見つけて「来てくれたの……! 本当にお世話になりました」ってやり取りしているところを見るのが、僕すごく好きなんですよね。いや、好きって表現は不適切なんですけど……必要な時間だなって思うんです。

コロナ禍での変化と、葬儀業界のこれから
中浜さん:新型コロナウイルスの影響で、葬儀の中止やそもそも故人と会うことすらできないと報じられています。木村くんの周りではどんな状況になってるんだろう?
木村さん:僕らもコロナ患者さんを何人も送っているんですが、やっぱり立ち会いや葬儀ができないと現実を受け止めきれないご遺族の方は多いです。そういった状況下でなにか少しでもできることはないかと、納骨前などに「お別れ会」を提案するようになりました。
あと最近では、透明度の高い「ご遺体袋」を用意して、袋越しにご遺族と対面できるような対策も始めたところです。
中浜さん:今まで通りの葬儀が難しい状況でも、できるだけのことを模索してるんですね。最後に、これからの医療や介護、そして葬儀業界がどうなっていくと思うか、木村くんの考えを聞かせてください。

木村さん:これからは、介護施設が葬儀まで一貫して担う時代になっていくんじゃないかと考えています。ご家族にとっても、ずっとお世話になっていた顔なじみの施設で看取りから葬儀までお願いできるのは安心感がありますから。
実際、今まさに僕らが介護施設と提携して葬儀をおこなう新しいプロジェクトの準備をしているところなんです。今後は医療・介護と葬儀がより近い関係性になっていく。僕はそう考えてますね。