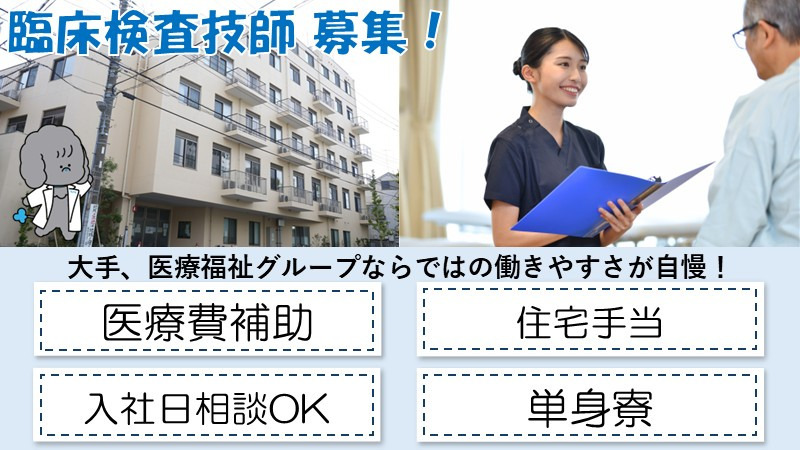臨床工学技士と臨床検査技師はそれぞれどんな職種?
間違えてしまいやすい両職種ですが、臨床工学技士と臨床検査技師の仕事は、働く場所や業務そのものが違っており、それぞれが専門的な知識や技術を生かすことでチーム医療として患者さんの治療に貢献しています。
臨床工学技士とは
臨床工学技士は、医師の指示のもとに「生命維持装置」と呼ばれる人工呼吸器、血液透析装置、人工心肺装置などの高度医療機器を操作し、治療のサポートをおこなっている人のことを指します。
また、院内の医療機器を使用するスタッフが、トラブルなく治療がおこなえるように医療機器の保守点検・管理をおこなっています。
臨床工学技士が勤務する場所は、主に透析室やオペ室、機器管理室、ICU、心臓カテーテル室などです。委員会や勉強会に参加し、医療機器の正しい使い方を指導するなど「医療機器のスペシャリスト」として医療機関などに従事しています。
臨床検査技師とは
臨床検査技師は、医師の指示のもとに、厚生労働省が定める検体検査や生理機能検査の臨床検査をおこなう人のことを指します。
検体検査は患者さんの血液や尿、喀痰(かくたん)、組織、細胞、体腔液などの検体を調べる業務で、検査の説明や採血、採取をおこない、精度の高い正しい検査結果を提供しています。
生理機能検査は、超音波検査、心電図検査、脳波検査、呼吸機能検査、聴力検査など多くの検査があり、患者さんの体から直接情報を医療機器で記録することで患者さんの状態を調べます。
さまざまな疾患の特定には詳しい検査を欠かすことができません。また、医師は検査技師による検査結果をもとに治療方針の決定や診断をおこないますので、臨床検査技師がおこなう業務は重要な仕事といえます。
勤務先・勤務時間・年収の違い
臨床工学技士と臨床検査技師の仕事は、医療者にも混同されがちですが、それぞれ医療チームの一員とし専門性を活かして働いています。
では、働き方にどのような違いがあるのでしょうか?勤務先の違いや勤務時間、給与の違いを見ていきましょう。
臨床工学技士の勤務先・勤務時間・年収
臨床工学技士は、病院や透析クリニックなどが主な勤務先で医療機器メーカーや治験コーディネーター(CRC)としての働き方も注目を集めています。
正職員の基本的な就業時間は8時間です。病院勤務で、手術室や心臓カテーテル室、ICUなどの業務に従事する臨床工学技士の場合は、当直やオンコールと呼ばれる待機を受け持つのも臨床工学技士の働き方の特徴です。
病院の場合は、日勤のフルタイム勤務が主で、当番制で待機や当直を受け持ちます。透析クリニックの場合は、残業や遅番はありますが当直やオンコールはありません。
臨床工学技士の平均年収は約400万円といわれています。
厚生労働省が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」の同じ医療職である看護師と比較すると、看護師は約453万円となり、平均年収に若干の開きがあることがわかります。これは、看護師は臨床工学技士に比べると夜勤が多いことなどが理由に挙げられます。
臨床検査技師の勤務先・勤務時間・年収
臨床検査技師は、臨床工学技士と同じく病院やクリニックが主な勤務先です。臨床検査技師がおこなう検体検査や、エコーや心電図検査などの生理機能検査は、診療科に関係なくおこなわれますので、検診センターや臨床検査センターといった施設も勤務先になります。
その他に、臨床工学技士と同様に、医療機器メーカーや治験コーディネーター(CRC)としても働いています。
正職員の基本的な就業時間は8時間です。病院で働く臨床検査技師は、急患対応がある病院では夜勤や当番制でオンコールを受け持ちます。また入院患者さんがいる場合は休日出勤になる場合もあります。
クリニックや検診センターは臨床工学技士と同じくオンコールや夜勤はありません。検査センターの場合は、24時間稼働のセンターであればシフト制になるため夜勤もあります。
臨床検査技師の平均年収は約400万円といわれており、臨床工学技士とほぼ同額になっています。
臨床工学技士と同じく、厚生労働省が毎年発表する「賃金構造基本統計調査」の同じ医療職である放射線技師と比較すると、放射線技師は約490万円となり、平均年収に若干の開きがあることがわかります。これも、放射線技師のほうが夜勤が多いことなどが理由に挙げられます。
資格の取り方の違い
臨床工学技士は資格ができて31年、臨床検査技師は64年になる資格です。それぞれどのように資格を取るのでしょうか?また、ダブルライセンスについてもご紹介します。
臨床工学技士の資格の取り方
臨床工学技士になるには、高校卒業後に3年制の短期大学・専門学校または4年制の大学に進学し、厚生労働省が定めるカリキュラムの条件を満たすことで国家試験の受験資格を得ることができます。
その他に、1年制の専攻科を設けている学校もあります。入学には厚生労働省が指定する履修科目を満たしている必要がありますが、すでに医療資格を持っている人や工学系の学校を卒業している人などであれば最短で臨床工学技士を目指すことができます。
臨床検査技師の資格の取り方
臨床検査技師になるには、高校卒業後に3年制の短期大学・専門学校または4年制の大学に進学し、厚生労働省が定めるカリキュラムの条件を満たすことで国家試験の受験資格を得ることができます。
臨床工学技士の場合は、要件を満たす場合には1年制の専攻科でカリキュラムを終えることで臨床工学技士の国家試験の受験資格を得ることができましたが、臨床検査技師の場合は、専攻科はありません。
最短で臨床検査技師を目指す場合は、3年制の学校を卒業し国家試験に合格することが資格取得の近道です。
臨床工学技士と臨床検査技師のダブルライセンス
大学によっては、臨床工学技士と臨床検査技師の両職種の資格取得(ダブルライセンス)を目指すこともできます。
1年生の頃から、両方のカリキュラムを受けることになりハードに思えますが、実際は同じ履修科目も多く、両方の知識をしっかりと身に着けて現場で働きたいと考える人にお勧めです。
しかし、入職して両方の仕事に従事することはなく、どちらか一方の資格で医療に従事することになります。
それぞれどんな人に向いている?
臨床工学技士と臨床検査技師は業務に違いがありますが、それぞれどのような人に向いているのでしょうか?また、共通して向いている人はどんな人なのでしょうか?
臨床工学技士の適性
臨床工学技士は「医療機器のスペシャリスト」とも呼ばれ、医療の進歩に伴って高度化する医療機器の操作や保守点検に欠かせない役割をしています。
機械に興味がある人や説明書を読むのが好きな人、積極的に情報取集することが好きな人に向いている仕事です。
臨床検査技師の適性
臨床検査技師は、心電図やエコーなどの検査をおこなうほかに、患者さんの検体を使って検査をします。
検体は必ずしも十分な量が採取できるわけではなく、限られた量から検査しなければならないこともあります。そんな時、細かい作業が苦にならない人には向いている仕事です。
共通する適性
両職種とも、医療従事者として責任感のある人や、他職種や患者さんと関わる際に円滑なコミュニケーションを取れる人も医療者として向いている人といえるでしょう。
チーム医療の一員として、スムーズなコミュニケーションは欠かすことができません。今は得意でなくとも、意欲的に取り組む姿勢を持っている人も共通して向いている人です。