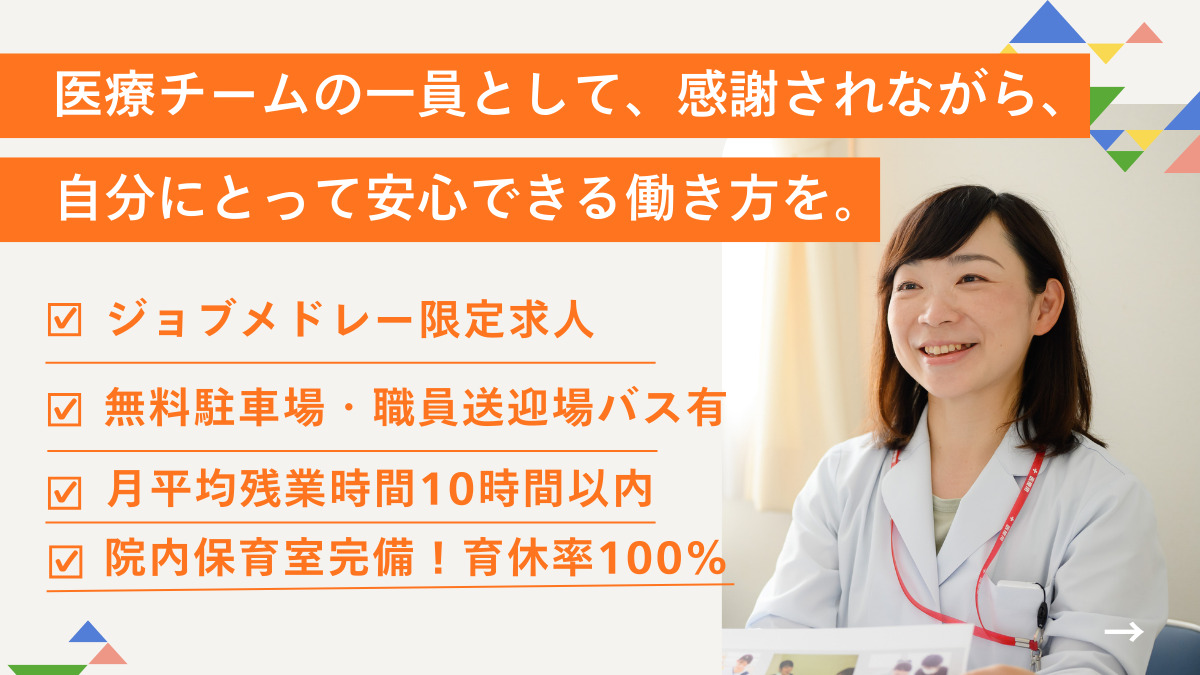医療ソーシャルワーカーに興味を持った学生時代

—医療ソーシャルワーカーになったきっかけを教えてもらえますか?
森口さん:わたしは母親が看護師だったので、もともと病院というものがかなり近い存在でした。でも、母親が日勤・準夜勤・夜勤の3交代制で働いていて、大変そうな姿を見ていたので「わたしには無理かもしれない」と思っていました。
ただ、病院で働きたい気持ちはあったので、高校生の頃に「何かないかな?」と母親にきいてみたら「人の役に立てるソーシャルワーカーという仕事があるよ」と教えてもらいました。
当時はソーシャルワーカーの仕事をよくわかってなかったんですけど、「病院にいる相談員さんだよ」と言われて、「それだったらわたしでもできるかもしれない」と思ったのがきっかけです。
医療ソーシャルワーカーに資格は必要?
—医療ソーシャルワーカーになるまでの流れを教えてください。
まず高校を卒業後、福祉系の短大に入学しました。医療ソーシャルワーカーになるために、社会福祉士の資格を取ろうと思ったんですけど、2年制の短大の場合は卒業後に2年以上の実務経験が必要になるんですね。なので、卒業と同時に受験資格が得られる4年制の福祉系大学に3年次から編入しました。
(※医療ソーシャルワーカーになるために必須の資格はありませんが、実態として社会福祉士または精神保健福祉士の資格を採用条件としている病院が多いようです)
編入した大学では、医療ソーシャルワーカーを目指す人が集まるゼミに所属しました。ゼミでは授業の一環として、座学のほかに実習もおこないました。就職活動については自分で面接を受けに行って、4年生の夏頃に病院から内定をもらいました。
職場選びとしては、忙しいけどいろいろなことが学べて、やりがいがありそうな急性期病院を選びました。
希望の病院から内定をもらった後は、1月末におこなわれる社会福祉士の国家試験に向けて鬼のように過去問を解いてましたね(笑)。
社会福祉士の国家試験は比較的合格率が低くて、わたしが受けた年は30%を切っていたと思うんですけど、なんとか合格することができました。国家試験の合格後、入職するまでの間は教習所に運転免許を取りに行ったりして過ごしてましたね。
患者さんをサポートする仕事のやりがい
—入職後の仕事内容について教えてください。
入職後は医療ソーシャルワーカーとして、医療福祉相談室に配属となり、患者さんの治療後の退院や転院のサポートをおこなっていました。
ふだんの業務内容としては、病院のカンファレンス(会議)で医師や看護師さんに患者さんの様子・ご家族の意向を共有して、退院や転院など患者さんの今後について話し合います。
わたしの病院では、各病棟に医療ソーシャルワーカーが1人という体制だったので、ものすごくたくさんの患者さん・ご家族の相談にのっていました。
急性期病院だったので、急患の人が運ばれてきたり、治療費が払えない患者さんの対応があったりして毎日忙しかったんですけど、実務を通して生活保護や介護保険の適応基準がよくわかるようになりました。
その制度の知識を使って、経済的に困っている患者さんが病院で受診できるようになったり、治療費を払うことができるようになったりしたときは、「勉強してきてよかった」と思いましたね(笑)。
そういうお医者さんと患者さんの間に入って、納得のいくかたちで退院できるようにしてあげたり、問題解決の材料を提案できたりすることが仕事のやりがいだと思います。
—医療ソーシャルワーカーの適性についてはどう考えますか?
問題を多角的な視点でとらえて、解決に導くことを楽しめる人は向いていると思います。
ただ一方で、親身になって相談にのることはすごく大事なんですけど、患者さんの中にはさまざまな境遇の人がいます。なので、個人で抱え込んでしまうタイプの人はつらくなってしまうかもしれません。
入職後のアドバイス

—働いていたときに役に立ったことはありますか?
入職してから『早わかり 看護聞き言葉辞典(照林社)』という本を買ったんですけど、これはめちゃくちゃ便利でした。
病院では専門用語はもちろん略語や隠語がよく使われるので、わからない言葉をすぐ調べられてお医者さんや看護師さんとのやりとりもスムーズです。
—森口さん、ありがとうございました。