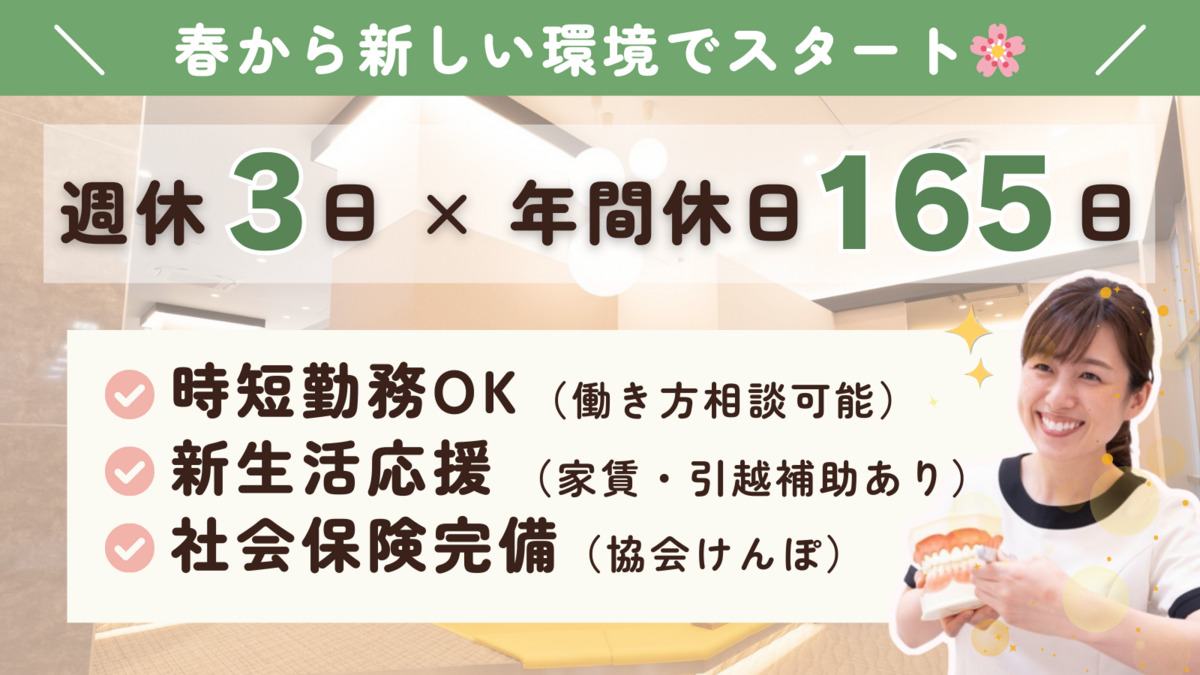1.小児歯科とは
歯科における診療科目の一つで、その名のとおり小児(子ども)に対して歯科診療をおこないます。子どもは乳歯から永久歯へ生え変わる時期にあるため、歯や顎の成長を見据え、健康な永久歯が正しい位置に生えるよう診療するのが特徴です。また子どもが診療を嫌がる場合には、「診療チェアに座る」「器具に触れてもらう」といったトレーニングから始めて、子どもの恐怖心を和らげます。
日本に7万近くある歯科診療所のうち小児歯科を標榜している──看板や入り口に記載している歯科診療所は約6割です。

歯科診療所は、法律に定められている診療科目(歯科・小児歯科・矯正歯科・口腔外科)であればどれを標榜して開業しても良いとされています(自由標榜制)。そのため、小児歯科を専門的に提供していない歯科診療所でも、診療科目に小児歯科を標榜している場合があります。
小児歯科の対象年齢は?
永久歯が生え揃って顎の成長が終わる時期には個人差があるため、明確な対象年齢は定められていません。
しかし、成長を見据えて治療をおこなう小児歯科の特性から、一般的に乳歯が生え始める頃から中学生くらいまでが対象と言われています。歯科診療所によっては「◯歳まで」と独自の制限を設けているところもあります。
2.小児歯科でおこなう処置
むし歯治療
大人と同様、むし歯の進行に応じた治療をおこないます。むし歯になりかけの初期段階であれば歯磨き指導やフッ素塗布、進行するに従いむし歯に侵食された部分を削って詰め物や被せ物をし、歯がほとんど溶けるまで進行している場合は抜歯します。
乳歯でもむし歯が進行しているときには、永久歯への影響を考えて抜歯をすることがあります。
乳歯の抜歯
乳歯は本来自然に抜けていくものですが、重度のむし歯や永久歯の生え方に支障が出る場合は抜歯することがあります。
〈重度のむし歯の場合〉
表面のエナメル質が柔らかい乳歯はむし歯の進行がとても早く、乳歯の奥にある永久歯に変色や凹みといった影響を与えることがあります。治療で治らないほどむし歯が進行している場合、永久歯を守るために抜歯をすることがあります。
乳歯には永久歯の位置を誘導する役割があるため、早い段階で乳歯を抜く場合は、永久歯が生えてくるスペースを保つ保隙(ほげき)装置を用いることがあります。
〈永久歯の生え方に支障が出る場合〉
何らかの原因で永久歯が乳歯の内側・外側・側面から生えてくることがあります。放置すると歯並びがデコボコになることがあるため、永久歯が正しい位置に生えるように抜歯します。
フッ素塗布
主にむし歯予防としておこなう処置です。フッ素には、むし歯になりかけた歯の再石灰化を促したり、菌の活動を抑制したりすることで、むし歯になりにくい歯にする効果があります。
とくに生えて間もない歯はフッ素を多く取り込みやすいため、乳歯が生え始めた時期や永久歯が生え始めた時期に塗布することが効果的とされています。
シーラント
むし歯予防としておこなう処置です。歯ブラシが届きにくくむし歯になりやすい奥歯の溝に専用の歯科材料を詰めて汚れが着くのを防ぎます。
シーラントをおこなうのは、乳歯の奥歯や生えて間もない6歳臼歯(6歳頃に乳歯の奥に生えてくる初めての永久歯。第一大臼歯のこと)です。
シーラントで使う歯科材料にはフッ素が含まれているため、生えたばかりで未成熟な歯の表面を強化する効果もあります。
歯磨き指導
むし歯や歯周病の原因となる歯垢(プラーク)を除去し、再付着を予防することをプラークコントロールと言います。歯磨き指導では、このプラークコントロールを上達させる方法を指導します。一般的な流れは次のとおりです。

定期健診
自分の歯を老後まで維持するためには、子どものうちから健康な歯を守り、むし歯を作らないことが大切です。定期的に健診を受けることで、むし歯や歯周病の予防・早期発見・治療に繋がります。
定期健診では口腔内の状態を観察し、フッ素塗布やシーラントなどの予防処置をしたり、歯磨き指導をしたり、治療が必要であれば今後の治療方針を決めます。成長期にある子どもは、年齢によって注目するポイントが変わります。
年齢を軸とした定期健診でのチェックポイント
| 年齢 | チェックポイント | ||
|---|---|---|---|
| 口腔機能 | むし歯の有無 | 歯周病の有無 | |
| 0歳 | ◎ | ◯ | △ |
| 3歳頃 | ◎ | ◎ | △ |
| 5歳頃 | ◎ | ◎ | △ |
| 6歳頃 | ◎ | ◎ | ◯ |
| 8〜9歳頃 | ◯ | ◎ | ◯ |
| 10歳頃 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 12歳頃 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 15歳頃 | ◯ | ◎ | ◎ |
| 17歳〜 | △ | ◯ | ◎ |
参考:仲野和彦・権暁成・田中晃伸(2020年)『歯科衛生士のための小児歯科のきほん』デンタルダイヤモンド社
小児矯正
骨格の土台を作る第一期治療と、歯列を整える第二期治療に大別されます。基本的に第一期治療と第二期治療を一貫しておこないますが、第二期治療のみで歯並びをきれいにできるケースもあります。
〈第一期治療〉
骨の成長を利用した骨格矯正をおこなうため、永久歯が生え揃う前から始めます。顎を広げてデコボコの歯並びを揃える床矯正(しょうきょうせい)などをおこない、永久歯が適切に生えるスペースを確保します。
顎の骨が柔らかい時期に骨格を整えておくことで、将来的に永久歯を抜歯せずに矯正できる可能性が高まります。骨格矯正と共に、歯並びを悪くする頬杖や指しゃぶりといった癖を直す指導もおこないます。
〈第二期治療〉
永久歯が生え揃ってからおこないます。大人の矯正と同じように固定式または取り外し式の矯正装置を使って歯列を整えます。
第一期治療で永久歯が正しい位置に生える骨格作りが済んでいるため、大人になってから矯正を始める場合と比べて手間をかけずに歯列を整えることができます。ただ、第一期治療と違って顎の骨が成長しきった段階のため、顎の骨の大きさに対して歯が多すぎたり大きすぎたりする場合には抜歯が必要になることもあります。
3.小児歯科で働く
小児歯科では、診療に携わる歯科医師、それをサポートする歯科衛生士や歯科助手、保育士などが働いています。
歯科医師
〈必要な資格〉
歯科医師免許が必要です。免許を取得するには、6年制の歯科大学や歯学部で必要なカリキュラムを修了し、国家試験に合格しなければなりません(歯科医師になるにはより)。
また、日本小児歯科学会が認定する小児歯科専門医や小児歯科認定医といった専門資格もあります。前述のとおり歯科診療所は自由標榜制であるため、治療にあたる歯科医師がどの領域のスキルをどの程度持っているのかがわかりにくいことがあります。それを解消するために生まれたのが専門資格であり、小児歯科に関する専門的な知識や経験を有する証となります。
〈仕事内容〉
歯科診療全般をおこないます。歯を削る、詰め物や被せ物を装着する、歯を抜くなどの行為は絶対的歯科医行為と言い、歯科医師でなければおこなうことができません。
また小児歯科の歯科医師には、子どもが前向きに治療を受けられるよう、不安や恐怖心を和らげる工夫が求められます。「この嫌な味は3秒経ったら洗うからね」「ちょっと痛いけどすぐ終わろうね」など、子どもに共感しながら治療の終わりを見せる対応が大切です。
〈給与〉
ジョブメドレーに掲載されている求人から賃金相場を抽出しました。2022年3月時点の全国の歯科医師の時給・月給・年収の相場は次のとおりです。
| 下限平均 | 上限平均 | 総平均 | |
|---|---|---|---|
| パート・アルバイトの時給 | 3,178円 | 5,140円 | 3,844円 |
| 正職員の月給 | 42万9,192円 | 104万2,462円 | 64万1,269円 |
| 正職員の年収* | 600万8,688円 | 1,459万4,468円 | 897万7,766円 |
歯科衛生士
〈必要な資格〉
歯科衛生士免許が必要です。免許を取得するには、歯科衛生士養成校で所定の課程を修了し、国家試験に合格しなければなりません(歯科衛生士になるには?より)。
〈仕事内容〉
歯科衛生士の三大業務と呼ばれる、歯科診療補助、歯科予防処置、歯科保健指導をおこないます。
歯科診療補助
歯科医師の指示を受け、診療の一部をおこないます。歯科衛生士ができる業務は次のような相対的歯科医行為と呼ばれるものです。
- 仮歯の調整、仮着
- 歯周組織検査
- 概形印象の採得
- 表面麻酔薬の塗布 など
なおこれらの行為の実施可否は、患者の状態や歯科衛生士のスキルに応じて歯科医師が判断します。
歯科予防処置
歯科医師の指示のもと、歯垢・歯石の除去(スケーリング)やフッ素塗布をおこないます。
歯科保健指導
むし歯や歯周病を予防するために、歯磨き指導や食事指導をおこないます。
小児歯科で働く歯科衛生士は、子ども(患者)・保護者・歯科医師の橋渡しとして重要な役割を担っています。
子どもや保護者が抱く不安な気持ちを聞き取って歯科医師へ伝えたり、歯科医師から受けた検査結果や治療方針を保護者にわかりやすく説明したり、治療中の子どもへ治療の目的や内容をわかりやすく伝えます。三者それぞれが安心できる信頼関係を築くことで、治療がスムーズに進みます。

〈給与〉
ジョブメドレーに掲載されている求人から賃金相場を抽出しました。2022年3月時点の全国の歯科衛生士の時給・月給・年収の相場は次のとおりです。
| 下限平均 | 上限平均 | 総平均 | |
|---|---|---|---|
| パート・アルバイトの時給 | 1,379円 | 1,757円 | 1,503円 |
| 正職員の月給 | 23万4,488円 | 30万8,169円 | 25万9,982円 |
| 正職員の年収* | 328万2,832円 | 431万4,366円 | 363万9,748円 |
歯科助手
〈必要な資格〉
必要な資格や免許はとくにありません。しかし業務では専門知識が求められるため、歯科助手資格認定制度などの民間資格が多くあります。
〈仕事内容〉
歯科助手は無資格のため、できる業務とできない業務が決まっています。
歯科助手ができる業務は、歯科医師に器具を手渡すなどの間接的なサポート、器具の準備や片付け、受付や会計といった事務業務などです。
一方で歯を削るなどの歯科医師がおこなう医行為や、フッ素塗布などの歯科衛生士がおこなう予防処置、そのほか患者さんの口腔内に手を入れる行為は一切おこなえません。
〈給与〉
ジョブメドレーに掲載されている求人から賃金相場を抽出しました。2022年3月時点の全国の歯科助手の時給・月給・年収の相場は次のとおりです。
| 下限平均 | 上限平均 | 総平均 | |
|---|---|---|---|
| パート・アルバイトの時給 | 1,043円 | 1,285円 | 1,113円 |
| 正職員の月給 | 18万8,268円 | 24万4,192円 | 20万5,688円 |
| 正職員の年収* | 263万5,752円 | 341万8,688円 | 287万9,632円 |
保育士
〈必要な資格〉
保育士資格が必要です。資格を取得するには、保育士養成校で所定の専門教育を修了するか、各都道府県で実施されている保育士試験に合格しなければなりません(保育士になるには?より)。
〈仕事内容〉
小児歯科で働く保育士は、ほとんどの場合が歯科助手との兼務となります。保育士としての知識や経験を活かして治療前の子どもに声かけをしたり、治療の間接的なサポートをしたりします。一般歯科も提供し、キッズスペースを設けている歯科診療所では、親の診療中に子どもを預かることもあります。
4.小児歯科の展望
厚生労働省と日本歯科医師会は「80歳になっても自分の歯を20本以上保つこと」を目標とした8020運動を推進しています。いつまでも自分の歯で食事や会話を楽しむには、歯が生え始めた頃からの管理が大切であり、子どもの口腔内の健康を守る小児歯科は欠かせない存在です。
歯に対する健康意識の高まりから子どものむし歯の数は年々減少し、小児歯科のニーズは修復治療から予防処置へとシフトしています。加えて都市部を中心に歯科診療所の数が増加していることから、業界の競争は激化しています。
そこで、子どもが通いやすい設備や内装を整えたり、妊娠期特有の歯科疾患に対応するマタニティ歯科を併設するといった専門性を打ち出したりすることで、新たな患者を獲得する動きが見られます。このような差別化をいかに図っていくかが、小児歯科の今後の鍵となりそうです。
参考
- 仲野和彦・権暁成・田中晃伸(2020年)『歯科衛生士のための小児歯科のきほん』デンタルダイヤモンド社