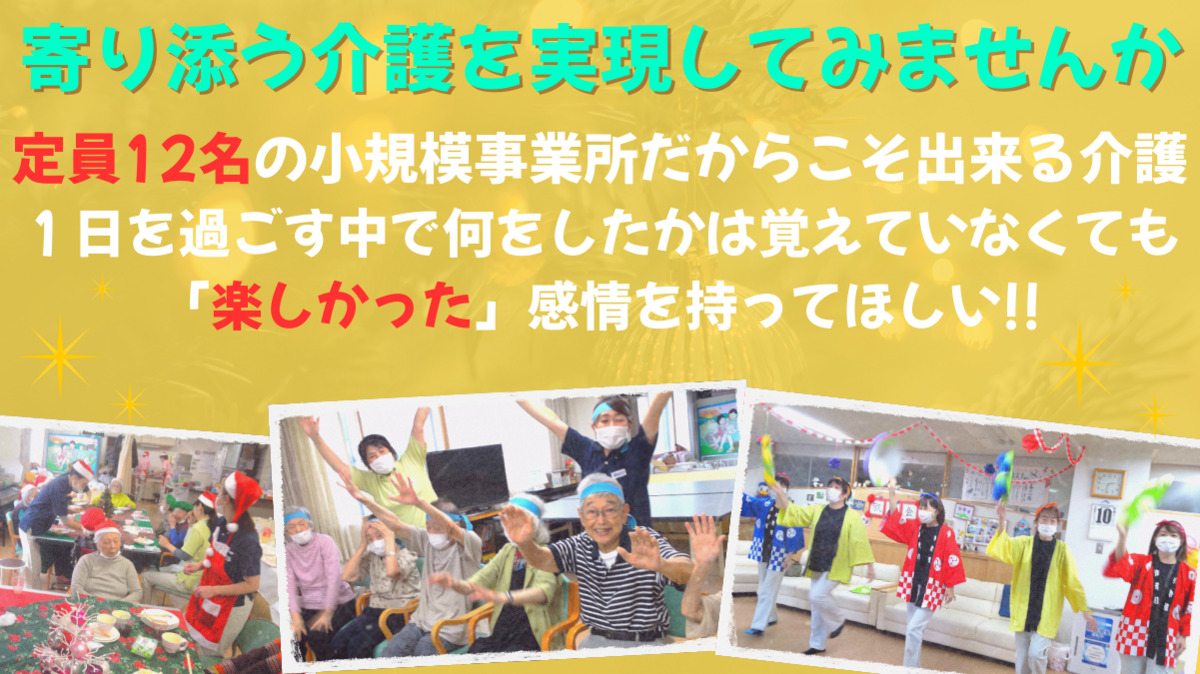新田恵利

1968年3月17日生まれ、埼玉県出身。おニャン子クラブのメンバーとして人気を博す。1986年「冬のオペラグラス」でソロデビュー。30万枚以上の売り上げを記録。2014年に実母が要介護4と認定され介護生活が始まる。6年半に及ぶ在宅介護の末、母を看取る。その後自身の介護経験を綴った著書『悔いなし介護』(主婦の友社)を出版。
わがままで愛らしい母親だった
──2021年に出版した『悔いなし介護』を読みました。経験をもとにした介護入門書のような内容でとてもわかりやすかったです。お母さまの人柄も伝わってきました、お茶目で頑固で優しい方だったんですね。
本当にそのとおりです! それが伝わったならちゃんと書けてたんだなと思います(笑)。お喋りが大好きで、すぐお友だちができちゃう人でした。その反面子どもっぽくてわがままで、私が大人になってからは親と子が逆転していましたね。
──子どもっぽいところもあったんですね。印象的な思い出はありますか?
ある日お買い物に行ったらコートをねだられたことがあって。季節の変わり目だったので、「もう少し待てば値下がりするんじゃない?」と言っても、「今どうしても欲しい」って聞かないんです。親なら「じゃあもう少し待とうかしら」とか言いそうなもんですけどね、駄々をこねられて買わされました(笑)。
突然訪れた介護。もっとも苦労したことは?
──そんなお母さまの介護が始まったのは2014年秋ですね。きっかけは骨折だったと。
母が68歳のとき、あまりにも腰が痛くて歩いたり立ったり、声を出すことすらできなくなったんです。救急車を呼んで検査をしたら、骨粗しょう症による腰椎の圧迫骨折と診断されました。
52歳のときにすでに骨粗しょう症の診断を受けていて、当時はまだ一般的な病気ではなかったのでとくに予防をしてなかったんです。腰痛の延長くらいに思っていました。
それから数年ごとに圧迫骨折をしては処方された薬を飲んでを繰り返したんですけど、次第に重いものを持ったり、勢いよく座ったりっていう日常動作だけで骨折するようになっていったんです。骨がどんどん脆くなっていったんですね。

──突然介護生活が始まるわけですが、初めはすべて手探りだったと思うんです。例えばオムツのつけ方なんてわからないじゃないですか。今振り返って、何が一番大変だったと思いますか?
そうですね……なんの準備も、覚悟もしていなかったというのが一番大変でした。家族に介護が必要になったらどこに連絡して、役所ではどの窓口に行くかぐらいは調べておけばよかったです。
「地域包括支援センター」って字面では見たことがありましたけど、「介護になったらここを頼るべきなんだ」ということすらわからなかったですから。
自分のために“言いふらす”
──事務的な手続きや準備など、やることが山ほどあったと思います。でも心が追いつかなかったんじゃないかと勝手に推察します。そういった気持ちにどう折り合いをつけましたか?
ブログで母の介護を公表した……と言うか吐き出したことによってすっきりしたのと、書いたことで自分がどういう状況にあるのかを整理できたんです。それと書いてから泣いたことですね。泣くとスッキリしますよね。
──「家族の介護をしている」と公言する人は少ないように思います。なぜそこで公表したんですか?
もちろん躊躇しましたよ。でも犯罪じゃないし、恥ずかしいことでもない。なにより自分が前を向くためにそうしたほうがいいと思いましたし、“言いふらす”ことで共感してくれる人もいて、気持ちがすごく楽になりました。

私が打ち明けたあと、幼友達が「実は私も介護をしている」と話してくれたんです。それからはランチをしながら介護あるあるなんかを話してストレス発散して、別れるときに「お互い頑張ろうね」って言い合ってね。
自分の状況を知ってもらうって大事なんだなと感じました。介護をしている皆さんにもぜひ言うだけじゃなく、“言いふらす”ぐらい心を開いてほしいですね。
在宅介護を選んだ理由

──お兄さんと旦那さんと3人でご自宅で介護をされたんですよね。施設に入居する選択はなかったのでしょうか?
在宅か施設かを悩んで選んだというわけではないんです。兄が同居することになり、在宅介護に支障がなかったのでそのままの流れで介護をしただけで。ある日の取材で「なぜ在宅介護を選択したんですか?」って聞かれて、「そうですよね、施設っていう手もありましたよね」って(笑)。それで兄と話して、もしもどちらかがギブアップしたらヘルパーさんにお願いして、改めて施設のことを考えようとなりました。
──「施設に預けたほうが介護をする人もされる人も幸せだ」と言う人もいますよね。
そのほうが長生きできるという考え方もあるんですけど、長生きを目標にはしていなかったんです。母が母らしく、母の希望の生活を送れたほうがいいと思ったので、在宅介護でよかったなって思います。
訪問看護師への感謝

──さまざまな医療職や福祉職との関わりがあったと思います。具体的にどのような方のお世話になりましたか?
理学療法士さんや訪問入浴介護の方にはとてもお世話になりました。終末期は訪問看護師さんにお世話になっていて、毎日来ていただきました。
バイタルチェックをして体を拭いてもらって、最後のほうは排便する力もなくなったんで、摘便といって便をかき出してもらったりとか。皮膚が重なるだけで皮が剥けちゃうんで、その対処をしていただいたりもしましたね。
──医療職との関わりの中で学んだことはありますか?
軟膏の塗り方みたいな技術的なこともそうですけど、私が仕事でいない間の姿を細かく教えてくれました。ケアのあと「こんなことを言っていましたよ、こんな話をしてくれましたよ!」って。
亡くなったあともお線香をあげに来てくれて、たくさんの思い出話をしてくれました。「お母さんには本当に笑わせてもらったの! 庭の杏の木の話とかお花のこととかたくさんお話していただいてね」なんて聞いて、改めて母の人柄を教えてもらった気がします。
皆さん孫より若い年代の方々だったんですけど、素直に母のことを好いてくださっていて、その気持ちというか心が今でも嬉しく思います。