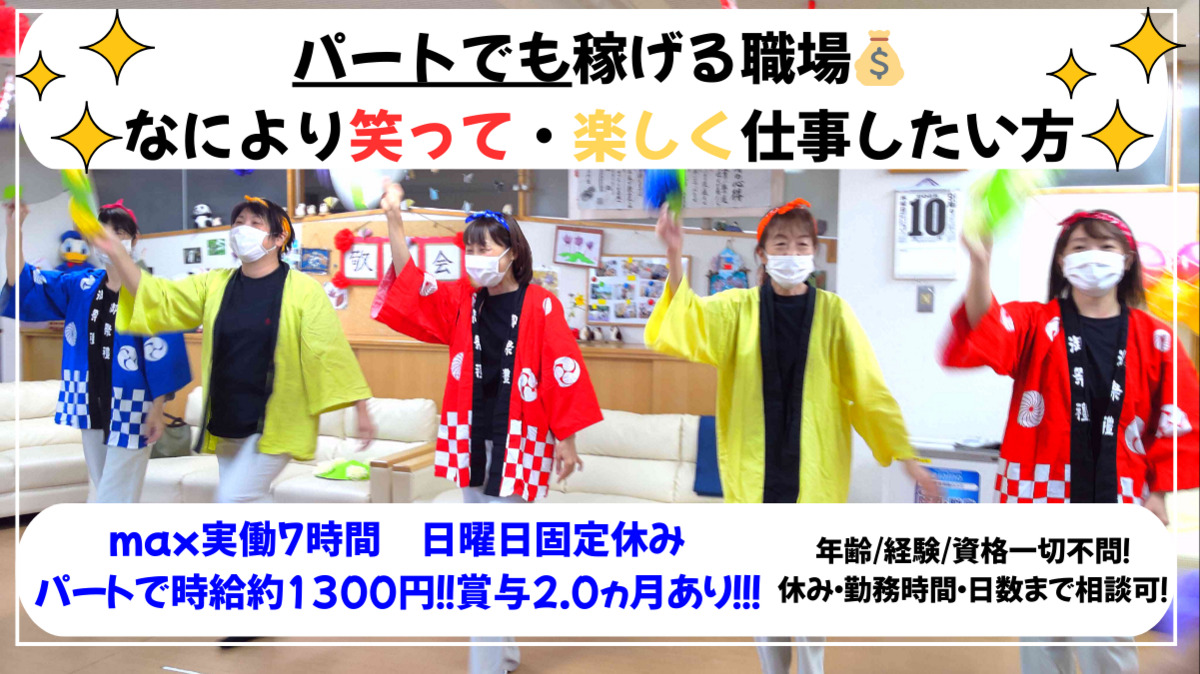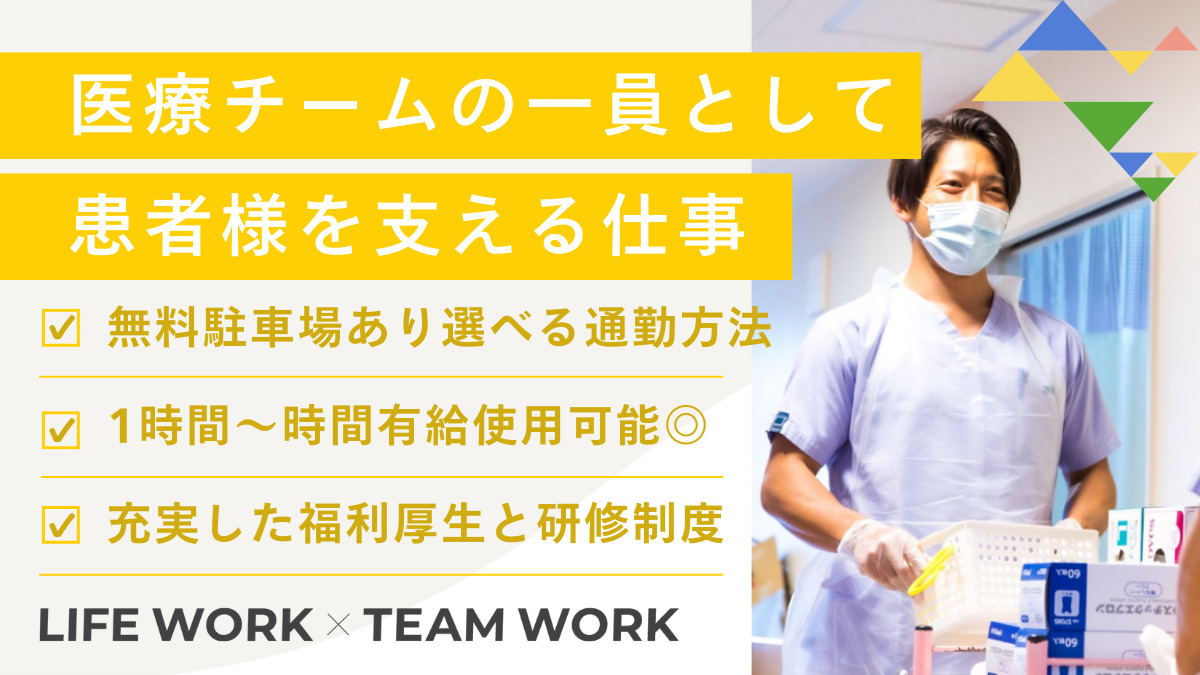目次
1.介護難民とは
介護難民とは、介護が必要な高齢者や障がい者が病院や自宅、あるいは施設において適切なサービスを受けられない人をいいます。介護施設の空きがなく入居できない、家族が遠方に住んでいて介護にあたれないなど理由はさまざまです。
2.介護難民の現状
介護難民の具体的な人数を示す公的なデータはありませんが、厚生労働省が公開した2022年4月時点の特別養護老人ホーム(特養)の待機者数を見ると、約27.5万人が入所待ちであることがわかります。
| 介護度 | 待機人数 |
|---|---|
| 要介護3以上 | 25.3万人 |
| 要介護1・2の特例入所対象者 | 2.2万人 |
特養入所は要介護3~5の人が対象ですが、1・2でも自宅での生活が困難な人などは特例として認めています。こうした特例入所の待機者が約2.2万人いると推計されています。
3.介護難民が増える2つの理由
高齢者の増加
介護難民が増える直接的な原因は、高齢者の増加です。
「令和5年版高齢社会白書(概要版)」によれば、日本の総人口は減少しているにもかかわらず、65歳以上人口の割合は年々増加しています。この割合は今後も増える見通しで、2025年には人口の約3割、2070年には約4割を65歳以上の人が占めると予測されています。
これにともない、介護を必要とする人も増えています。厚生労働省が発表した「令和2年度 介護保険事業状況報告(年報)」によると、2020年度の要介護(要支援)認定者数は約682万人で、公的介護保険制度がスタートした2000年度の約256万人と比べて約2.6倍増加していることがわかります。
介護の担い手不足
介護難民が増加する一方、介護職員の人手不足が深刻化しています。
介護労働安定センターが2021年度に実施した「介護労働実態調査」によれば、介護事業所全体の人材不足感を聞いた質問では「従業員が不足している」と回答した事業所は全体の60%以上を占めています。
4.問題解決に向けた4つの対策
介護難民の問題に対して国がおこなっている対策を4つ紹介します。
地域包括ケアシステムの推進

地域包括ケアシステムは、要介護状態と認定されたあとでも住み慣れた自宅や地域で自立した生活を続けられるよう、地域全体でサポートしていくシステムです。
>地域包括ケアシステムについてはこちらの記事で詳しく解説!
地域包括ケアシステムとは?
外国人介護人材の受け入れ
人材不足を補う対策として、外国人材の受け入れも積極的におこなわれています。出入国在留管理庁の在留外国人統計によると、2022年12月末時点で全国で6,284人の留学生が介護分野で働いています。
>外国人介護人材についてはこちらの記事で詳しく解説!
EPA介護福祉候補者とは?
在留資格(就労ビザ)とは?
介護ロボットやICTの導入
さらに、介護ロボットやICT(情報通信技術)の導入も推進されています。厚生労働省は見守りセンサーや介護ロボットの活用などを条件に配置基準の緩和を検討し、2022年に実証実験をおこないました。この結果、文書作成時間の短縮や介護ロボット導入による介護職員の身体的負担の軽減など、一定の効果が認められています。
>介護とテクノロジーについてはこちらの記事で詳しく解説!
介護ロボット・ICTでどう変わる? 介護業界の現状と未来
介護職員の処遇改善
介護職員の労働環境を改善する施策として、「介護職員処遇改善加算」が設けられました。この加算は、介護職員の待遇や労働環境の改善の財源にすることが定められています。
>処遇改善についてはこちらの記事で詳しく解説!
処遇改善で給料はいくら上がる?
介護難民は高齢者の増加や介護人材の供給不足など、さまざまな要因が絡み合って増加しています。この問題は近い未来の課題ではなく現在起きている社会問題です。私たちに何ができるか、一緒に考えていきましょう。