目次
1.ケースワーカーとは
健康への不安や生活保護などの相談・支援をする公務員
ケースワーカー(Case Worker:CW)とは、病気や障がいなどの困りごとを抱えている人や、経済的な問題を抱えている人の相談に応じ支援につなげる公務員で、現業員(げんぎょういん)とも呼ばれています。主な職場は福祉事務所や児童相談所などの公的機関です。幅広い相談内容に耳を傾け、問題の把握と必要な支援の策定や手続きをおこないます。
厚生労働省の「福祉事務所人員体制調査について」によると、全国に設置されている福祉事務所は1,247ヶ所あり(2022年4月時点)、ケースワーカーの数は2万7,621人でした(令和3年地方公共団体定員管理調査結果より)。
ソーシャルワーカーとの違い
ケースワーカーと似た職種にソーシャルワーカーがあります。主な違いは、勤務先と資格の有無です。ケースワーカーが福祉事務所など公的機関で働く公務員であるのに対し、ソーシャルワーカーは医療機関や介護施設、福祉施設などさまざまな勤務先で働きます。
ケースワーカーになるには地方公務員試験に合格し、社会福祉主事の任用資格を得る必要があります。一方、ソーシャルワーカーの場合社会福祉士や精神保健福祉士の資格が応募条件にあるところや、無資格でも可としているところなど勤務先によります。
一般的に社会福祉に関わる職種全般をソーシャルワーカーと呼ぶため、ケースワーカーはソーシャルワーカーの一つと捉えられます。
2.ケースワーカーになるには?必要な資格

5つのルートで必要な過程を修了し、社会福祉主事の任用資格を取得することが必要です。資格取得後は、地方公務員試験に合格し一般の行政職として入職します。入職後に福祉事務所に配属されることで、ケースワーカーとして働けます。
地方公務員はおおむね3〜5年ほどで異動があり、希望どおり配置されるとは限りません。自治体によってはケースワーカーとして長く勤務できるところもあれば、担当部署が変わるところもあります。
3.ケースワーカーの仕事内容
ケースワーカーの主な仕事は、地域住民が抱える貧困や健康、高齢などの悩みの相談に応じ、課題の把握や支援につなげることです。ケースワーカーを5年経験した地方公務員のインタビュー内容も交えて、業務内容を紹介します。
話を聞いた人

がんちゃんさん
過去に地方都市で5年間ケースワーカーを経験。福祉事務所に入職後庶務関係の部署を経験し、最初の異動でケースワーカーに。主に生活保護世帯に対する生活支援・指導を担当した。
ブログでは、現役ケースワーカーの心が折れないよう乗り切り方やアドバイスを発信している。
相談を受ける
生活保護や貸付の相談
病気や生計中心者との別離など、自分の力で生活するのが困難になったときに最低限の生活を保障します。相談者から話を聞き預貯金、不動産などの資産調査や、就労可能性を探ります。生活保護支給後も継続して自立への支援や指導をおこないます。
また、低所得者や高齢者、障害者世帯を対象にした貸付制度に関する相談にも応じています。教育や不動産など目的ごとにいくつか種類があり、いずれも無利子や低金利で利用できます。
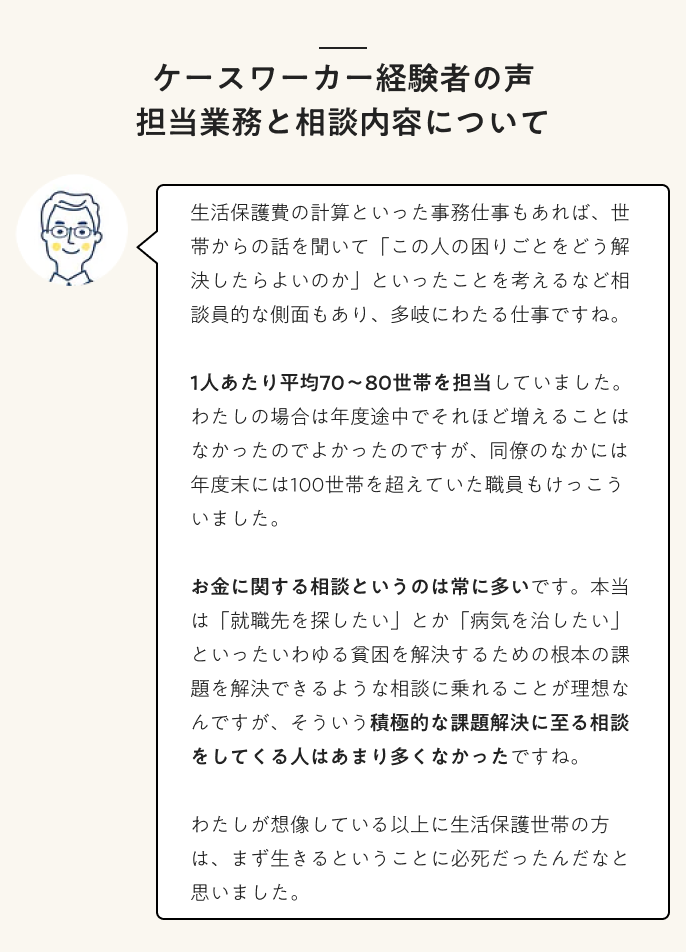
高齢者に関する相談
福祉事務所では、特別養護老人ホームへの入所手続きや、老人福祉サービスに関する広域的な調整もおこなっています。支援を必要とする本人が相談に来られないケースもあるため、その家族からの相談に応じて家庭を訪問し、生活指導や施設への入所措置をすることもあります。
子どもに関する相談
福祉事務所には家庭児童相談室が設置されており、ほかの職員とともにケースワーカーが相談や援助に応じています。相談内容には、18歳未満の子どもを取り巻く家庭問題や子育ての悩みがあります。具体的には保護者の病気や離婚、経済的問題や、発達の心配、非行、虐待など多岐にわたります。
とくに、虐待予防においては妊産婦の段階から把握と支援に努めることが重要です。そのため、精神疾患の既往歴や援助者の不在、未婚など育児への不安が予測される人に関しては、保健所や児童相談所などと連携をとり把握と支援をおこないます。
20歳未満の子どもを扶養している人を対象とした、母子父子寡婦福祉資金の貸付にかかる審査や手続きもおこないます。

障がいに関する相談
障がいをもつ人やその家族が利用可能な手当や医療費助成などの相談に応じます。また、自治体によっては福祉事務所で障害者手帳を交付しているところもあります。
支援につなげる
相談内容や調査結果をふまえて支援計画を作成します。支援内容には援助の目標や内容、方法などを盛り込みます。計画作成後は給付金の支給を開始する以外にも、自立相談支援機関や生活支援事業など、相談者に必要な支援機関や制度につなげます。
支援が開始されたあとも計画どおりに援助が実施されているか、本人への働きかけ、状況の確認を継続的におこないます。生活保護者や路上生活者に対する支援では、宿泊所への入所や健康・金銭管理の指導、就労支援などがあります。

4.ケースワーカーの働く場所
ケースワーカーの勤務先は福祉事務所です。福祉事務所は都道府県および特別区を含む市に設置が義務付けられている行政機関で、町村は任意で設置できます。
福祉事務所の数(2023年4月1日現在)
| 都道府県 | 市(特例区を含む) | 政令・中核市 | 町村 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 742 | 257 | 46 | 1,250 |
厚生労働省|福祉事務所
福祉事務所で働く人の数は地域の人口や実情に応じて条例で定められています。
ケースワーカーの人員配置
| 都道府県 | 市(特例区を含む) | 町村 |
|---|---|---|
| 被保護世帯が390以下の場合6人 65を増すごとに1人 | 被保護世帯が240以下の場合3人 80を増すごとに1人 | 被保護世帯が160以下の場合2人 80を増すごとに1人 |
5.ケースワーカーの働き方
ケースワーカーの一日

ケースワーカーの休日
ケースワーカーは地方公務員のため、基本的に土日祝日が休みです。ケースワーカーは一世帯を一人で担当することが多く、家庭訪問など業務スケジュールをほかの予定に合わせて調整できます。

6.ケースワーカーの給与
各自治体の職員の給与と同程度となります。総務省の2022年地方公務員給与実態調査によると、一般行政職の平均給与月額は35万8,878円でした。月給に加えて年に2回勤勉手当と期末手当が支給されます。これは一般企業でいうところのボーナスにあたり、民間業界全体のボーナス支給実績を参考に支給額が決められます。
7.ケースワーカーの将来性
ケースワーカーが担う相談業務の内容は、子どもに関することや貧困、病気など多岐にわたります。とくに担当する割合が多い生活保護受給者数は、2022年4月時点で約204万人と、2015年をピークに減少傾向にあります。
しかし、高齢化による高齢者世帯の増加や、一人のケースワーカーが担当する件数が80世帯を超える状態が続くなど負担の大きさが課題となっています。ケースワーカーの数もここ10年で約4,000人増加したものの、経験年数の浅い人が過半数を占めるなど質の向上の課題も指摘されています。
今後は研修の拡充や、困難なケースに遭遇したケースワーカーが燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥らないよう支援することが重要です。
参考
- 厚生労働省|福祉事務所ケースワーカー
- 厚生労働省|支援を担う体制づくり及び人材育成等について















