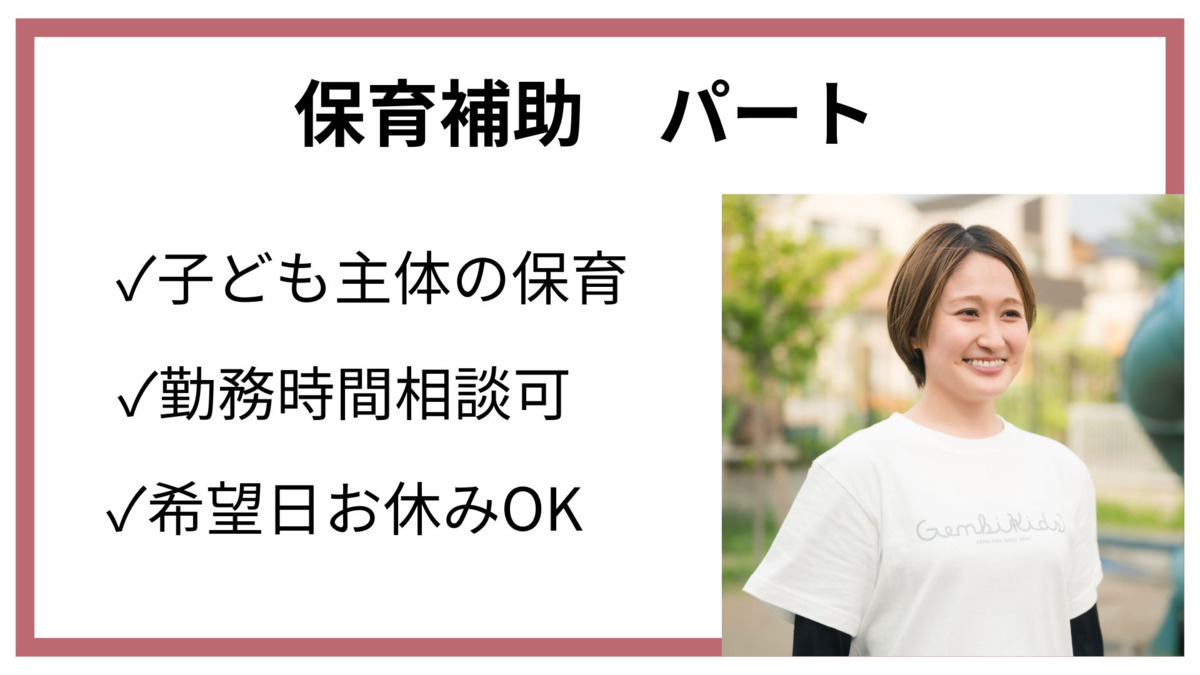目次
1.小規模保育園とは
小規模保育園とは、原則0~2歳児を対象に、定員6~19人と少人数で運営される保育園です。定員5人以下の家庭的保育と、定員20人以上の従来の認可保育園の中間に位置し、家庭的な環境のもときめ細かな保育を提供しています。
従来は3歳未満のみを対象としていましたが、2023年4月に全国で対象年齢を引き上げることが通知され、市区町村がニーズに応じて3歳児以降も柔軟に受け入れられるようになりました。
認可保育園・認可外保育園について詳しくはこちら
>保育園・保育所にはどんな種類がある?役割と利用状況、働く職員についてわかりやすく解説
小規模保育事業ができた背景
小規模保育事業は、2015年4月に施行された「子ども・子育て支援新制度」で、「小規模保育事業」のなかの「地域型保育事業」として新設されました。
この背景には、待機児童問題があります。都市部に多く存在する待機児童のうち、約9割は0〜2歳児とされており、保育園の拡充が求められました。しかし都市部では広い土地の確保が難しく、大規模な保育園は容易には作れません。
この立地問題を解決するために、小さなスペースでも開園できる保育園として制度化されたのが「小規模保育事業」です。大規模保育園のように園舎や園庭の整備に何ヶ月もかける必要がなく、一定の基準を満たせば既存のマンションの一室などでも認められるため、短期間での開園が可能になります。
市区町村の認可対象となったことで、財政支援が受けられるようになり、開園の後押しとなっています。
小規模保育園の3つのタイプ
小規模保育園は、地域の多様な保育ニーズに対応するため、保育所分園に近いA型、家庭的保育に近いC型、その中間的なB型の3つのタイプに分かれています。
2023年10月時点(※1)の全国の小規模保育園の施設数は、A型が8万2,103ヶ所、B型が1万123ヶ所、C型が691ヶ所となっています。
小規模保育園の認可基準
|
園児の定員 |
|
|---|---|
|
A型・B型 |
6〜19人 |
|
C型 |
6〜10人 |
|
職員の資格 |
|
|
A型 |
保育士 * |
|
B型 |
1/2以上が保育士 * |
|
C型 |
家庭的保育者 |
|
職員数 |
|
|
A型・B型 |
【0歳】園児3人に対して1人 【1〜2歳】園児6人に対して1人 【3歳】園児15人に対して1人 【4〜5歳】園児25人に対して1人 さらに1人の追加配置 |
|
C型 |
【0~5歳】園児3人に対して1人 家庭的保育補助者を置く場合は 5:2 |
|
面積 |
|
|
A型・B型 |
【0〜1歳】3.30㎡/人 【2〜5歳】1.98㎡/人 |
|
C型 |
【0〜5歳】3.30㎡/人 |
|
(参考)従来の認可保育園 |
|
|---|---|
|
園児の定員 |
20人以上 |
|
職員の資格 |
保育士 * |
|
職員数 |
【0歳】園児3人に対して1人 【1〜2歳】園児6人に対して1人 【3歳】園児15人に対して1人 【4〜5歳】園児25人に対して1人 |
|
面積 |
【0〜1歳】乳児室 1.65㎡/人、ほふく室 3.3㎡/人 【2〜5歳】保育室等 1.98㎡/人 |
保育士の資格を持つ職員の割合は「A型>B型>C型」の順に人数が減っているところがポイントです。また、A型・B型では、小規模事業であることを鑑み、従来の認可保育園の職員配置にプラス1名の追加配置とすることで、保育の質を担保しています。
C型の職員資格である家庭的保育者とは、市区町村がおこなう研修を修了し、保育士もしくは保育士と同等以上の知識や経験があると自治体から認められた人のことを指します。研修には「基礎研修」と「認定研修」があり、受講要件は以下のとおりです。
■家庭的保育者研修
◎ 基礎研修
目的:家庭的保育に必要な基礎的知識・技術等の習得
受講者:すべての家庭的保育者を目指す者
研修時間:座学21時間+実習2日以上
◎ 認定研修
目的:保育の知識・技術の習得
受講者:看護師、幼稚園教諭、その他の者
研修時間:
1. 看護師、幼稚園教諭、家庭的保育経験者(1年以上)…座学40時間+実習48時間
2. 家庭的保育経験のない者、家庭的保育経験者(1年未満)…座学40時間+実習48時間+実習20日間
家庭的保育者になるための条件にはほかにも、「年齢制限」「保育士資格を保有していること」「就学前の子どもがいないこと」「家族に要介護者がいないこと」など、自治体ごとに制限があるため、確認するようにしましょう。
家庭的保育者の詳しい仕事内容はこちら
>会社員から保育ママへ!やりがいは「子どもたちの成長」
また、2015年の「子ども・子育て支援新制度」により同じく新設された子育て支援員養成のための「地域保育コース(地域型保育)」を修了することでも、A型・B型の「保育従事者」またはC型の「家庭的保育補助者」として働くことができます。
子育て支援員について詳しくは、以下の記事で紹介しています。
保育の仕事がしたい人向けの新制度「子育て支援員」になる方法
連携施設
小規模保育園では、少人数でも適切な保育をおこなうため、また満3歳となり卒園を迎える子どもの受け入れ先として、近隣の保育園や幼稚園、小規模保育園と協定を結ぶ「連携施設」の形をとっています。連携対象となる内容は、以下のとおりです。
■保育内容への支援
集団保育を体験させるための行事参加や園庭開放などの機会の設定、適切な保育をおこなうために必要な相談や助言、自園調理ができない場合の給食搬入、合同での健康診断など
■代替保育の提供
小規模保育園の職員が病気や休暇などで保育ができない場合に、代わりに保育をおこなう
■卒園後の受け皿
小規模保育園を卒園する子どもが優先的に入園できる「優先的利用枠」を設定し、保護者の希望に基づき受け入れ、保育または教育を提供する
入園方法、保育料
小規模保育園へ入園を申し込むには、認可保育園と同じ方法でおこないます。市区町村が窓口となり保育認定をおこない、保育の必要性が高い子どもから優先的に入園先が決定します。
保育料についても同じく、市区町村が定めた金額が設定されています。保護者の勤労状況や世帯所得、子どもの年齢、兄弟の人数などのさまざまな条件を考慮して算出されます。
2.小規模保育園で働く
小規模保育園で働くメリット
職員にとっては、小規模保育園で働くうえでどのようなメリットがあるのか紹介します。
◎ 一人ひとりと向き合った保育ができる
従来の保育園と比べると子どもに対する保育者の人数が多いため、余裕を持って子どもたちと接することができます。一人ひとりにかけられる時間が増えることで、自分がやりたい保育を実践しやすくなり、やりがいにもつながります。
◎ 一人当たりの保育スペースが広い
定員20人以上の従来の保育園と比べると、一人当たりの保育スペースが広く、空間に余裕を持って子どもたちと過ごすことができます。
◎ 体力的な負担が少ない
原則0〜2歳児の子どものみを受け入れている施設では、3歳以上の子どもがするような活発な遊びや運動の機会が少なく、体力的な負担が少なくて済みます。
◎ 残業や持ち帰り仕事が少ない
行事が多い園では、その分準備のための残業や持ち帰り仕事が多く、保育士の悩みのタネになっています。しかし小規模保育園では行事自体少ないところが多く、開催しても乳幼児が対象で大掛かりにはならないため、業務量が少なくなる傾向があります。
◎ 職員や保護者との関わりも少人数で、連携がとりやすい
職員の人数も少ないため、職場全体での連携がとりやすいです。また保護者の人数も限られるため、より丁寧な保護者対応ができ、信頼関係の構築もしやすくなります。
小規模保育園で働くデメリット
反対に、小規模保育園で働くうえでのデメリットを見てみましょう。
△ 職員の保育スキルに差がある
とくにB型・C型では保育士資格を持たない保育従事者や家庭的保育補助者の配置割合が増えるため、人によっては保育スキルにバラツキがあります。職員同士でフォローしあうことが重要になるでしょう。
△ 人数が少ない分、欠員が出ると負担が大きい
基準をギリギリの人数で満たして運営している場合、職員に欠員が出てしまうとその穴を埋める負担も大きくなります。休みをとりにくい状況も発生しやすいです。
△ 集団保育の機会が少ない
連携施設との合同で、3〜5歳児の子どもたちを交えての異年齢保育を経験する機会もありますが、日常的には乳幼児の見守りを中心とした保育が中心となります。
給料
小規模保育園で働く職員の給料はどのくらいでしょうか? 2019年度の内閣府の調査結果を見てみましょう。
※常勤職員の金額には、月額給与のほかに前年度の賞与1/12を含む
※集計対象は私立園のみ
|
常勤(月給+賞与) |
非常勤(月給) |
||
|---|---|---|---|
|
A型 |
保育士 |
29万3,827円 |
23万3,363円 |
|
保育従事者(無資格者) |
24万4,122円 |
20万6,120円 |
|
|
B型 |
保育士 |
29万9,793円 |
20万7,921円 |
|
保育従事者(無資格者) |
24万687円 |
18万5,689円 |
|
|
C型 |
家庭的保育者 |
36万8,259円 |
16万472円 |
|
家庭的保育補助者 |
27万1,422円 |
19万968円 |
出典:令和6年度 幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査集計結果<速報>
施設型ごとの保育士と家庭的保育者(常勤)の年収を比較すると、A型は約352万円、B型は約360万円、C型は約442万円でした。A型・B型の保育士には大差がなく、 C型の家庭的保育者はA型・B型よりも82〜90万円高い結果となりました。
また、従来型の保育園(公立・私立)の保育士(常勤)の平均年収はそれぞれ約439(公立)と約418万円(私立)でした。
3.小規模保育園で働く魅力
「落ち着いた環境で、子ども一人ひとりと向き合った保育ができる」「残業が少なく体力的にも負担が少ない」といった点が魅力の小規模保育園。しかし小規模だからこそ、そこで働く職員や保育方針によって特色が出やすいです。これまで多人数保育をおこなってきた人にはそのギャップは小さくありません。気になる園がある場合は、一度見学をして自分に合うかどうか実際に見ることをおすすめします。
また保育士資格を持っていなくても、家庭的保育者や子育て支援員として働くことができるのも注目ポイントのひとつ。これから保育に携わりたい人は、お住まいの自治体の要件をチェックして、どの資格が向いているか検討してみてくださいね。
参考
厚生労働省|令和5年社会福祉施設等調査