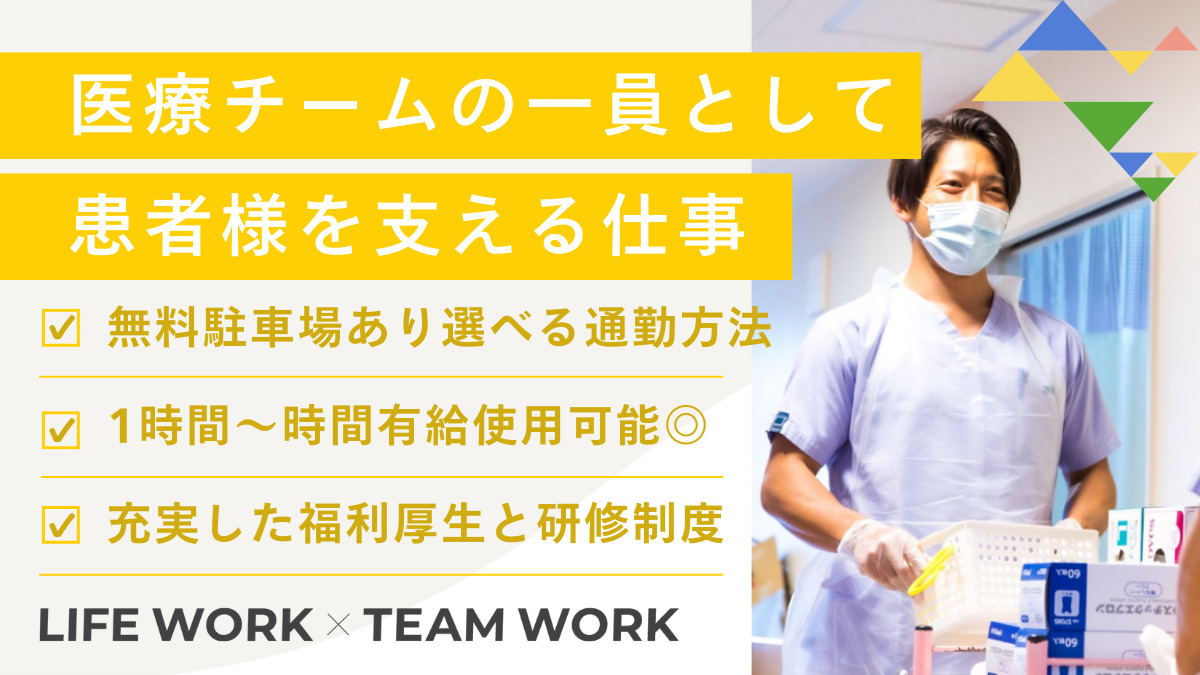目次
インテークとは?
介護・福祉業界でのインテーク(intake)は、利用者や家族との初回面接・電話相談を指します。インテークにはもともと「受け入れ」という意味があり、介護や支援を必要とする本人や家族から、それぞれの事情・要望などを聞き取ります。
相談を受ける担当者はインテーカー
相談を受ける担当者はインテーカーと呼ばれますが、インテーカーは相談者が話しやすい態度で接することが大切です。本人や家族にとって、介護や福祉の相談は初めての経験ということがほとんど。「この人は私たちの話をちゃんと聞いてくれるのかな」と、不安を抱いている方は多いものです。相談者の話を優しく穏やかに聞き入れ、適度なあいづちを打つなど、傾聴や共感の姿勢を示すことが大切です。また、不信感を与えないために、メモをとる際には承諾を得るようにしましょう。
インテークのコツ
インテーカー側としても聞きたいことはたくさんあると思いますが、一方的な質問の投げかけばかりでは、信頼関係は築きにくくなります。まずは傾聴と受容を心がけましょう。話を聞くなかで疑問点などが浮かび、どのような要望があるのかを聞き取りやすくなります。中立の立場で時間をかけてじっくりと面談し、その後の具体的な支援へとつなげていくのです。
情報収集も大切ですが、相談者にとってはインテーカーや相談先の印象が決定づけられる場面でもあるので、その後の支援を円滑に進めるうえで重要なプロセスです。インテークの重要性は、ケアマネジメントに関わるすべての人が理解しておきたいものですね。
アセスメントとは?
介護現場でのアセスメント(assessment)は、ケアプラン(介護サービス計画書)を立てるための情報収集を指します。介護・福祉業界では多くの場合、ケアマネジャーがアセスメントを担当します。また、客観的評価や査定と言った意味があり、自然環境や人材などさまざまな業界で使われる用語です。
アセスメントの流れ
アセスメントの大まかな流れは、まず相談者や家族が抱える課題(ニーズ)を明らかにすることから始まります。続いて、まずは何をするのかという「短期目標」と、その先にどのような生活をイメージするのかという「長期目標」を設定。そして、これらを達成のためにどのような支援が必要なのかを策定していきます。インテークは電話相談の場合も多いですが、アセスメントは基本的に本人とその家族を交えて相談者の自宅でおこないます。
相談者のニーズを正確に把握するため、アセスメントは客観的かつ適切な方法でおこなわなければなりません。そこで、アセスメントシートと呼ばれるツールを使用します。これは、厚生労働省が課題を分析するために必要と定めたヒアリングポイント(課題分析標準項目)をまとめたもので、漏れなく情報収集するうえで欠かせないツールです。
アセスメントの項目とコツ
具体的に見てみると、歩行や排せつなど日常生活における基本的な動作(ADL)を評価する項目、調理や掃除など日常生活における複雑な動作(IADL)を評価する項目、居住環境を評価する項目など、23の項目に分かれています。これだけ項目が多いと質問攻めになってしまいがちですが、インテークと同じく相手の話に耳を傾ける姿勢が大切です。項目は必ずしも上から埋めていく必要はないので、会話の流れを読んで相談者がとくに気にしていることや話しやすい内容から伺うのがよいでしょう。
専門用語はなるべく簡単な言葉に言い換え、時折「わからないことはありませんか?」と尋ねると、お互いの認識がずれにくくなります。質問のなかには、相談者が答えづらい内容もありますので、そういった質問はその場で無理に聞かず、話題を変えて後回しにしたり、日を改めたりするのがおすすめです。
また、メモを取ることに集中してしまい、会話に抑揚がなくなってしまうこともよくあります。メモは一言一句とるのではなく、重要なキーワードや図で表すと会話に集中でき、あとで読み返したときに全体のイメージが湧きやすくなります。
アセスメントを終え情報が網羅されたら、提供できるサービスを具体的に考え、ケアプランの原案を立てていきます。立案後にそのケアプランが適切かどうか、サービス担当者会議を開き内容を精査することも、ミスマッチなサービス提供をしないために大切なプロセスです。
モニタリングとは?
モニタリング(monitoring)は、介護サービスの提供開始後におこなう現状把握を指します。ケアマネジャーの業務のひとつで、モニタリングでは次のような点について確認します。
・ケアプランに沿って適切にサービスが実施されているか
・掲げた目標の達成に近づいているか
・利用者や家族の生活に変化が現れたか
・新たな課題が生じていないか
また、ケアプランに沿ってサービスを提供していても、利用者や家族の満足度が低ければ、長期的な目標の達成は難しくなります。そのため、事前の期待と実際のサービスにずれがないかといった点も、重要な確認事項となります。
モニタリングの頻度
利用者の状況は時間の経過とともに変化していくため、モニタリングは一回だけで終わるものではありません。介護保険制度では、少なくとも1ヶ月に一度は居宅にてモニタリングを実施することとなっています。モニタリングを通じて新たな課題が見つかったときや、設定した目標の実現が難しいと判断したときには、ケアプランを修正したうえで再交付します。この繰り返しによりケアプランは、利用者の課題を解決するためにより良いものとして更新されていきます。
また、サービスを提供している介護事業者へのモニタリングも大切です。ケアマネジャーが現場を直接見ることで気がつくこともありますし、普段接している事業者からしか聞けない情報もあります。さらに事業者側にとっても、モニタリングの結果を聞くことで、より利用者にマッチしたサービスの提供につながります。事業者とやりとりを重ねるほど信頼関係も築きやすく、コミュニケーションも円滑になっていくことでしょう。
エバリュエーションとは?
エバリュエーション(evaluation)は、介護サービスの提供後などに実施する事後評価を指します。モニタリングと混同されがちですが、モニタリングがサービス提供途中での現状把握を指すのに対し、エバリュエーションは事後評価である点が異なります。
エバリュエーションのポイント
エバリュエーションでは、これまで提供してきたサービスの効果を査定し、改善点はなかったかなども検討します。ポイントは、サービス提供者だけでなく、利用者とともにおこなう点です。提供側と利用側の視点があることで、より公平な評価となることが期待されます。そして、エバリュエーションの結果や利用者の状況変化に応じて再度アセスメントのプロセスに戻り、その後のサービス提供がより最適なものになるようサイクルを回していきます。
エバリュエーションは、自分が関わったケアマネジメントを客観的にとらえることができる機会です。時には厳しい評価が出ることもあるかもしれませんが、こうした事後評価を繰り返すことで、ケアマネジメントの力がつくはずです。そして何よりも利用者や、関わった人々の支援につながれば、大きな励みにもなることでしょう。