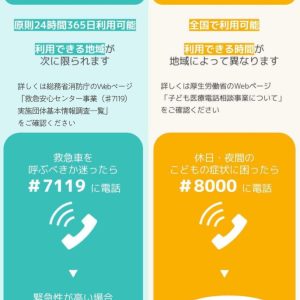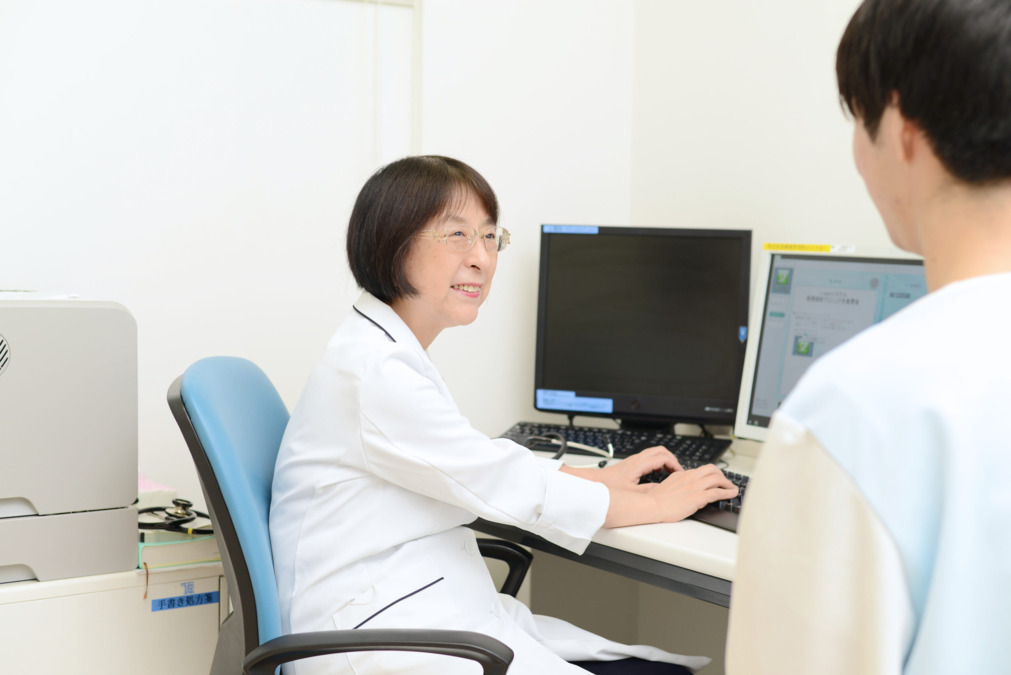目次
1.DMAT(災害派遣医療チーム)とは
DMATとは災害時の急性期(発災から48時間以内)に活動を開始できるよう訓練された医療チームのことです。Disaster Medical Assistance Teamの略で「ディーマット」と呼ばれ、2022年時点で2,040チーム・1万5,862人が登録しています。
DMATは原則医師1人、看護師2人、業務調整員1人の4人で構成され、チームで機動的に救急医療を提供します。業務調整員はロジスティクスとも呼ばれ、部隊の後方連絡の調整や情報収集、通信手段や医薬品などの確保を担います。業務調整員になれるのは薬剤師や臨床工学技士、救急救命士、事務職員など病院勤務の医師・看護師以外の職種です。
| 構成員 | 役割 |
|---|---|
| 医師 |
|
| 看護師 |
|
| 業務調整員 |
|
DMAT初動チームの活動時間は移動を除きおおむね48時間以内であり、状況に応じて1週間以上の活動が必要なときは2次隊、3次隊と追加派遣で対応します。被災後の精神的なケアに関しては、急性期を過ぎたあと災害派遣精神医療チーム(DPAT)などが担当します。
2.DMATの活動内容
DMATの活動内容は大きく以下の4つに分けられます。いずれにおいても、DMATは自力で移動・活動する自己完結性と、行政や現地の医療機関などとの連携を求められます。

被災地域での活動
被災地入りしたDMATは、その地域の災害拠点病院に設置される本部を拠点に活動を開始します。現場活動はいわゆる「がれきの下の医療」で、救出現場などで被災者の診察や外傷の治療にあたります。
救急医療と同じく重要な活動が、病院支援と域内搬送です。被災地では病院やそこで働く医療職も被災しているため、必要に応じて現地の病院長の指示に従い支援に入ります。また、災害現場から被災地域内の病院や広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)への域内搬送の際も、診療やトリアージをおこないます。
tips|トリアージとは
災害時は同時に多くの傷病者が発生するうえ、現地の病院も被災している可能性があり患者を受け入れられる医療資源が限られています。そこで重要なのが、緊急度・重症度を判断して治療の優先度を決め、適切な処置につなげる「トリアージ」です。
 トリアージには重症度で色分けした識別表(トリアージタッグ)が用いられます。赤、黄、緑の順に緊急度が高く、黒色は死亡または回復の見込みがないことを示します。裏面には患者の情報を記入する欄があり、処置段階では簡易カルテとしての役割も果たします。
トリアージには重症度で色分けした識別表(トリアージタッグ)が用いられます。赤、黄、緑の順に緊急度が高く、黒色は死亡または回復の見込みがないことを示します。裏面には患者の情報を記入する欄があり、処置段階では簡易カルテとしての役割も果たします。
広域医療搬送
広域医療搬送とは、被災地域内での治療が難しい重症患者を被災地域外の災害拠点病院などに緊急搬送することです。DMATは広域搬送拠点臨時医療施設(SCU)に運ばれた患者をケアするとともに、搬送の必要性を判断するトリアージをおこないます。
緊急搬送は自衛隊などの航空機や救急車でおこなわれ、DMATが航空機内の医療活動を提供する場合もあります。
後方支援
活動に必要な通信、移動手段、医薬品や食料、宿泊場所の確保などもDMATの重要な任務の一つです。被災地では現地の人的・物的資源を消費しないよう、DMATなどの救助活動はできる限り自力でおこなう必要があります(自己完結性)。
また、被災地の救助活動には当該地域の自治体はもちろん、厚生労働省、自衛隊、消防、近隣の都道府県、各地の病院などあらゆる機関が関わります。DMATは被災状況や負傷者の情報共有や、適切な搬送のための連絡調整もおこないます。
ドクターヘリ活用
被災地では緊急車両だけではなく、ドクターヘリおよび災害医療調査ヘリが活躍します。緊急搬送のほか、医療資源の輸送やDMATの移動にも使われます。災害医療調査ヘリは情報収集や人員派遣に用いられます。被災規模が大きいほど、ヘリコプターの搭乗・活用はDMAT活動と密接に関係することがわかります。
DMAT派遣要請から活動開始までの流れ
災害発生時は、都道府県があらかじめ協定を締結しているDMAT指定病院や災害拠点病院にDMAT出動を要請します。被災により地域内のDMAT派遣要請ができない場合は、ほかの都道府県へ派遣要請を依頼し、依頼を受けた自治体が管内の病院にDMAT出動を要請・派遣します。なお、厚生労働省が緊急性を認めた場合は、被災都道府県の要請を待たずにDMAT派遣を要請することができます。
また、広域災害救急医療情報システム(EMIS)でも災害発生地域や派遣要請が確認できるようになっています。

3.DMATになるには
医師、看護師、多職種がDMAT隊員になるために新たな免許や資格は必要ありませんが、以下の病院に所属していて、かつ研修を受け試験に合格する必要があります。
DMAT指定病院か災害拠点病院に所属
医師、看護師、多職種であればどの勤務先でもDMAT隊員になれるわけではなく、DMAT指定病院または災害拠点病院に勤務している必要があります。DMAT隊員を目指すには、これらの病院に就職することが最初のステップです。
各都道府県には原則一ヶ所以上置かれる基幹災害拠点病院と、2次医療圏ごとに設置される地域災害拠点病院があります。2023年4月時点で770病院(基幹64、地域706)が指定されており、都道府県からDMAT指定医療機関に認められるのは災害拠点病院であることがほとんどです。
| 施設 | 指定要件 |
|---|---|
| DMAT指定医療機関 |
|
| 災害拠点病院 |
|
DMAT隊員養成研修を受ける
DMAT隊員養成研修は厚生労働省DMAT事務局が開催する4日間の研修で、基本のチーム構成にいずれかの職種1人を加えた5人で受講します。災害医療の知識・技術を学び、筆記・実技試験に合格することでDMAT隊員となります。隊員資格は永続的ではなく、5年に一度更新をおこないます。
災害拠点病院などに所属する希望者(チーム)のうち、都道府県が選考し厚生労働省が認めた人が受講できます。また、DMAT隊員として登録されている医師で一定の要件を満たす場合に、DMAT本部の責任者として活動できるようになる「統括DMAT」研修もあり、こちらは2日間でおこなわれます。
具体的な研修内容は以下のとおりです。
| DMAT | 統括DMAT |
|---|---|
|
|
参考:厚生労働省医政局「災害派遣医療チーム研修実施要領」
4.DMAT発足の経緯と今後の展望
DMATは1995年の阪神・淡路大震災で十分な情報共有や初期医療がおこなわれず、多くの「避けられた災害死」があったのではという反省をきっかけにつくられた組織です。翌年には広域災害救急医療情報システム(EMIS)の運用が開始され、2005年にDMAT養成が開始されました。
その後、2011年の東日本大震災では初動から多くのDMATが活躍したと同時に、調整機能や広域医療搬送戦略の強化、中長期的な支援の必要性が浮き彫りとなりました。近年では災害医療のスキルを活かし、新型コロナウイルス感染症対策の初期対応をおこなうなど、災害による外傷治療にとどまらない活躍を見せています。
“災害大国”日本で、これからも一人でも多くの命が救われることを願ってやみません。