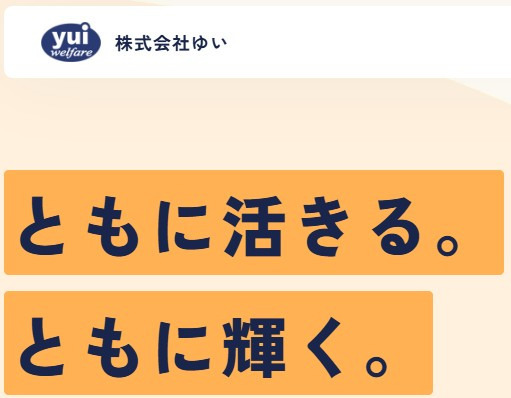目次
1.老人福祉法とは?
老人福祉法は高齢者福祉のあり方や、介護を担う施設・事業に関するルールを定めた法律です。65歳以上の高齢者を主な対象として、老人福祉施設と老人居宅生活支援事業について規定しています。老人福祉法は、2000年の介護保険法施行後においては、虐待など介護保険制度の例外に対応し、高齢者福祉を補完する役割を担っています。
老人福祉法ができた時代背景
老人福祉法は高度経済成長期の1963年に施行されました。当時の社会では核家族化などから、「家族の責任」とされてきた家庭での介護が難しくなっていました。このような問題に対応するため老人福祉法が制定され、1970年代以降は時代やニーズの変化に合わせ、改正を繰り返しています。
|
1963年 |
老人福祉法施行 |
|---|---|
|
1973年 |
老人医療費支給制度(70歳以上の医療費無償化)制定 →老人医療費の増大を招いたため、1983年の老人保健法の施行と共に廃止 |
|
1978年 |
ねたきり老人短期保護事業(ショートステイ)開始 |
|
1979年 |
デイサービス事業開始 →在宅福祉の三本柱(ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービス)が出揃う |
|
1982年 |
老人保健法制定 →医療事業…高齢者医療費の一部自己負担(のちの後期高齢者医療制度) 保健事業…疾病の予防・治療・リハビリを総合的に推進(のちの健康増進法) →高齢者医療が社会福祉から社会保険へ |
|
1990年 |
都道府県と市区町村に対して老人福祉計画の作成を義務付け |
|
1994年 |
老人福祉施設に老人介護支援センター(在宅介護支援センター)を追加 |
|
2000年 |
介護保険法施行に伴い、老人居宅生活支援事業に認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)や小規模多機能型居宅介護事業を追加 |
|
2006年〜 |
有料老人ホームに関する規定の厳格化 |
参考:杉本敏夫・家高将明/編著『新・はじめて学ぶ社会福祉1 高齢者福祉論[第2版]』
2.老人福祉法に基づく老人福祉施設
老人福祉法では高齢者の暮らしを支える施設として、7種類の公的な老人福祉施設を規定しています。
|
施設 |
特徴 |
|---|---|
|
1.養護老人ホーム |
65歳以上で経済的理由や家庭環境、心身の状況により自宅での生活が困難な高齢者が入所する |
|
常時介護が必要で自宅での介護が困難な65歳以上の要介護3以上の高齢者が入所する |
|
|
3.軽費老人ホーム |
家庭環境や住宅事情などの理由で自宅での生活が困難な60歳以上の高齢者が入所する。A型・B型・C型(ケアハウス)・都市型などがある |
|
4.老人デイサービスセンター |
65歳以上で心身の状況により、日常生活を営むのに支障がある人などが日中通所する |
|
5.老人短期入所施設 |
65歳以上で家族の介護者の疾病などの理由により、在宅介護が一時的に困難となった人が短期間入所する |
|
6.老人福祉センター |
無料か低額で高齢者に関する各種の相談に応じる施設。高齢者に健康の増進や講座、レクリエーションなども提供する |
|
7.老人介護支援センター (地域包括支援センター*) |
自宅で暮らす援護が必要な高齢者や家族などからの相談に応じ、総合的に福祉サービスを受けられるように市区町村やサービス実施機関などと連携する |
*2005年の介護保険法改正により、多くの施設が地域包括支援センターへと発展的に移行した
老人福祉法は民間の有料老人ホームも規定
有料老人ホームは、老人福祉法の定める老人福祉施設ではありませんが、同法で設立や運営について定められています。有料老人ホームは高齢者を入居させ、食事の提供や介護、家事、健康管理などのサービスを提供する民間施設です。
介護付き、住宅型、健康型の3種類があり、費用や提供されるサービス内容は施設によって異なります。近年は有料老人ホームの設置に関する規制が強化され、設立の際の届出厳密化など、入居者保護のための措置が講じられています。
tips|介護老人保健施設(老健)やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)を定める法律は?
高齢者が暮らす施設は老人福祉施設だけではなく、さまざまな種類の施設があります。例えば、介護老人保健施設や介護医療院は介護保険法によって定められています。また、介護の必要のない高齢者も暮らすサ高住は、2011年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により生まれました。
3.老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業
老人福祉法では高齢者の暮らしを支える福祉事業を、以下の6つに分けて規定しています。
|
事業 |
特徴 |
|---|---|
|
1.老人居宅介護等事業 |
65歳以上で日常生活に支障がある高齢者の自宅に訪問し、食事・排泄・入浴などの介護や、掃除・洗濯・調理などの援助をおこなう |
|
2.老人デイサービス事業 |
日帰りで、食事・排泄・入浴などの介護や、機能訓練、レクリエーションなどを提供する |
|
3.老人短期入所事業 |
介護者の疾病や休養などの理由で、一時的に在宅介護が困難になった高齢者を短期間施設で受け入れる。介護保険法でのショートステイが該当する |
|
4.小規模多機能型居宅介護事業 |
「通い」を中心に、利用者の状態や希望に応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供する |
|
5.認知症対応型老人共同生活援助事業 |
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、食事・排泄・入浴などの介護や、機能訓練などのサービスを受けられる。介護保険法でのグループホームが該当する |
|
6.複合型サービス福祉事業 |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて提供する。介護保険法での看護小規模多機能型居宅介護(看多機)が該当する |
tips|デイサービスやショートステイを定める法律
デイサービスやショートステイは介護保険法で定められ、提供されています。ただし、虐待など特別な事情がある場合には、老人福祉法に基づく市区町村の権限として入所などの措置が実施されます。
4.老人福祉法と介護保険法の違い
現在、日本の高齢者福祉は老人福祉法に加え、介護保険法によって規定されています。老人福祉法は高齢で経済的に困っていたり、身寄りがなかったりする人を公費で支えるという、社会福祉の側面が強い法律です。
一方、介護保険法は、介護が必要な人を社会全体で支えるための介護保険制度について定めています。誰もが必要な支援を受けられるよう、介護認定や給付、事業者、施設などについて広範にルールを定める法律です。
2つの法律は、どちらも福祉施設や介護サービスに関して規定していますが、施行の背景や目的などに違いがあります。
|
老人福祉法 |
介護保険法 |
|
|---|---|---|
|
施行年 |
1963年7月 |
2000年4月 |
|
背景 |
・高度経済成長期に都市化、核家族化が進展 ・家庭内の互助機能が低下 ・地方における高齢者福祉が問題に |
・認知症や高齢者介護に対する社会的関心の高まり ・高齢化が急速に進んだことで社会保障費が財政を圧迫 ・バブル崩壊後の経済停滞・高度経済成長期に都市化、核家族化が進展 |
|
目的 |
高齢者の心身の健康保持と生活の安定を図ること |
加齢による病気等で要介護状態になった人が、その能力に応じて自立した日常生活を営めるよう、介護保険制度を設立し必要な保健医療サービスと福祉サービスを提供すること |
|
主な内容 |
高齢者福祉を担当する機関や施設、事業に関するルールについて定めた法律 |
介護が必要な人を社会全体で支えるための仕組み(介護保険制度)について定めた法律 |
|
制度 |
社会福祉・措置制度(社会的弱者に対して公費をもとに措置をおこなう公助の仕組み) |
社会保険・契約制度(利用者に対して保険料をもとに給付をおこなう互助の仕組み) |
また、老人福祉法は「措置制度」が中心で、行政が必要と判断した高齢者に対して、行政の責任と費用でサービスを提供する仕組みでした。そのため、対象者には選択肢がなく、行政が指定した施設やサービスを利用する形式です。
一方、介護保険法は「契約制度」を採用しています。そのため、利用者は自ら事業者と契約を結び、自分に合ったサービスを選択できます。
5.高度経済成長期から高齢者を支え続ける老人福祉法
老人福祉法は高齢者の福祉を支える基本的な法律として、今日まで重要な役割を果たしてきました。介護保険法の施行後も、両制度が互いに補完し合いながら、高齢者の生活を支えています。
ジョブメドレーでは、老人福祉法に基づくさまざまな施設やサービスの求人を多数掲載しています。あなたのスキルや希望に合った職場を見つけるために、ぜひ活用してみてください。