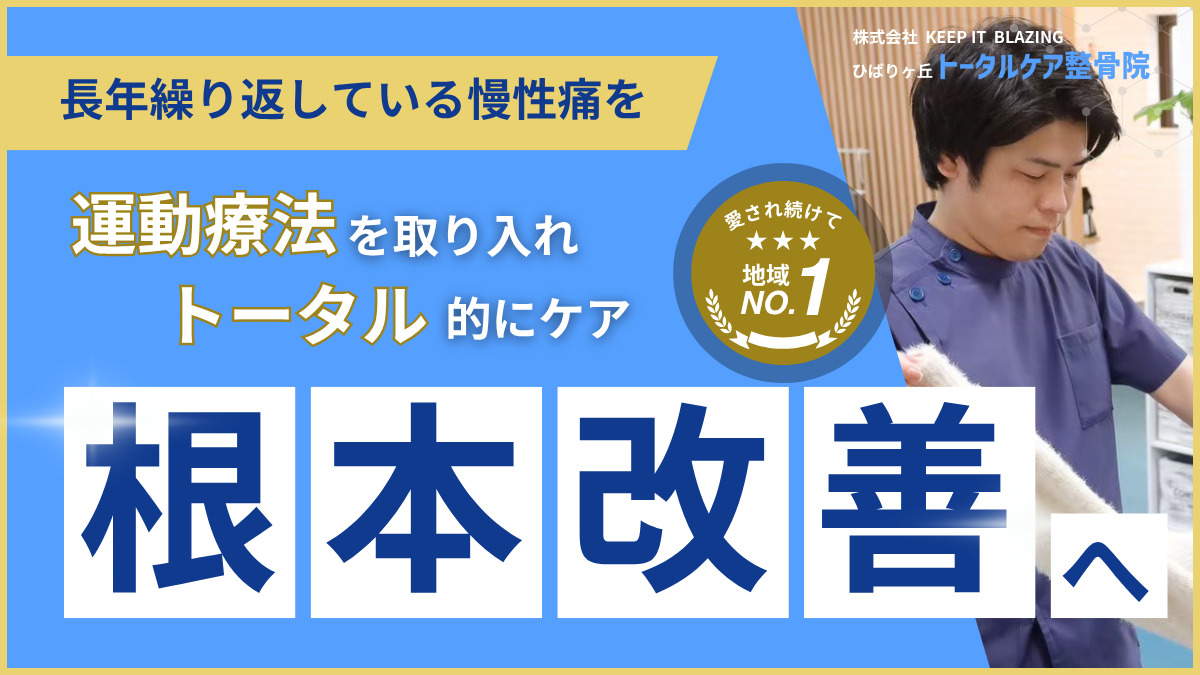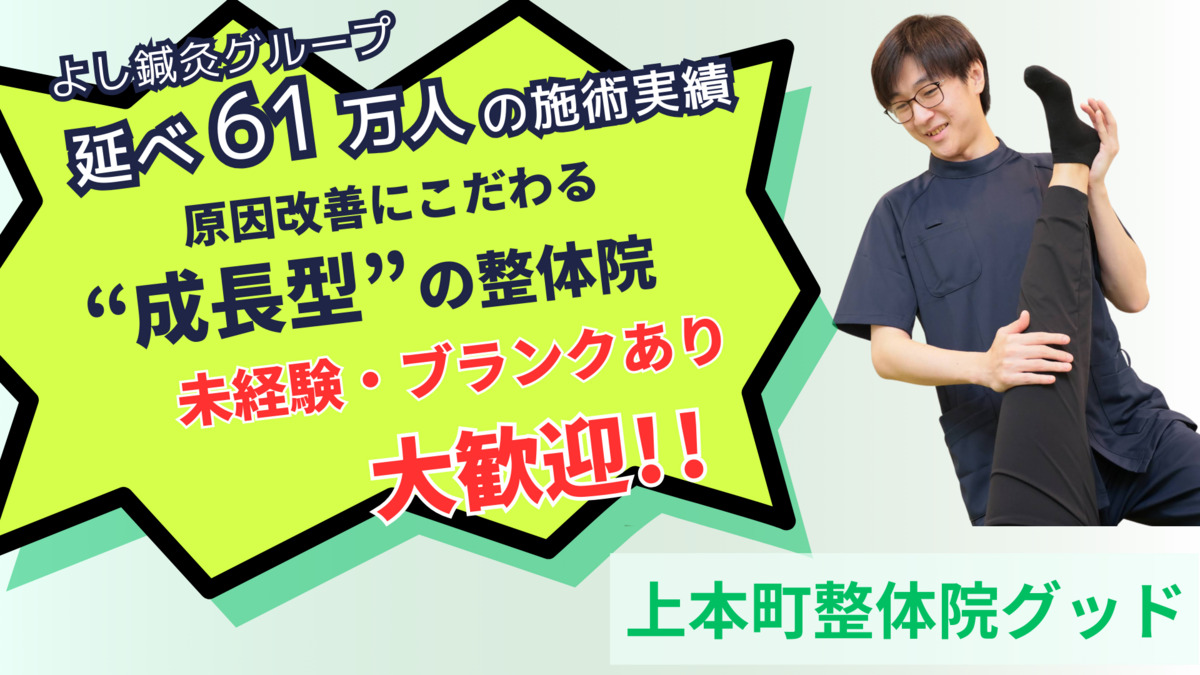1.長引くコロナ対応 withコロナの時代
度重なる緊急事態宣言の発令と延長を経てもなお、新型コロナウイルスの感染者が増えています。2021年4月25日から3回目の緊急事態宣言が発令され、新型コロナウイルスに対応する医療・福祉職を中心に、長引くコロナ禍の影響でストレスやメンタル面の不調を感じる方が多いのではないでしょうか。
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査」では、感染症・生活・仕事・家族などの視点で、困ったこと・ストレスに感じたことを調査しています。各視点での上位結果は次のとおりでした。
感染や感染症の情報に関すること
- 自分や家族が感染するかもしれないこと(75.5%)
生活に関すること
- 医療用品・衛生用品(マスクなど)が入手困難なこと(57.6%)
- 旅行やレジャーができないこと(50.4%)
医療・福祉、仕事に関すること
- 医療機関を受診しづらいなど医療サービスを受けづらくなったこと(43.1%)
家族などに関すること
- 家族・親戚・友人などに会えないこと(47.9%)
調査期間 : 2020年9月
調査対象 : 一般の方々(15歳以上)
回収サンプル : 10,981件
参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査概要・結果、新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査データ集 困ったことやストレス(性別年代別)【表10-1】~【表10-4】
また、職種別の調査結果を見ると、医療・福祉職は職種全体と比較して「自分や家族が感染するかもしれないこと」「家族・親戚・友人などに会えないこと」に対してストレスを感じている人がより多いことがわかります。

参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査概要・結果、新型コロナウイルス感染症に係るメンタルヘルスに関する調査データ集 困ったことやストレス(産業別)【表11-1】~【表11-4】
「withコロナ」と呼ばれる現代では、このようなストレスと上手に付き合うことが大切です。
2.ストレスチェックで自分の状況を把握しよう
コロナ禍では誰もがストレスを感じやすい状況に置かれています。とくに、感染リスクの高い職業である医療・福祉職は差別や偏見の対象となりやすく、コロナ禍特有のストレスを感じやすいと言えます。
日本赤十字社が発表した「COVID-19対応者のためのストレスチェックリスト」では、該当する項目をチェックすることで、今の自分がどの程度ストレスを感じているかを客観的に把握することができます。
チェックが多いほどストレスが多い環境・状況であると考えられます。自分が何に対してストレスや不安を抱いているのか、自己理解のために役立ててみてください。
COVID-19対応者のためのストレスチェックリスト
□ 仕事の順番・やり方に柔軟性を持たせることができない
□ 慎重な注意を要する業務を行う
□ 事前の説明が不十分だったり、刻一刻と情報が変化する
□ 感染することや死への恐怖を経験した
□ 職務を通して同僚に感染者が出た
□ 上長や同僚に職務に関する不安を話すことができない
□ 職務について、家族に伝えることができない
□ 職務について、家族からの反対を受ける
□ 直接対応を行わないスタッフとの間で温度差を感じる
□ 近しい人から避けられるような経験をする
□ 対応を行っている部署内で意見の食い違いがある
□ 対応を直接行っていない部署からの孤立がある
□ 患者やメディア等と対立したり、非難されたり、避けられたりする
□ 体温や体調を強く気にする
□ 他者から孤立しひきこもる
□ ウイルスに関する情報を過度にチェックする
□ 過度な手洗い、うがいをする
□ 世の中の反応(買い占め等)に対し皮肉的な見方になる
□ 防護具の扱いに不安を持つ
□ 活動の中でいつものようなタッチングや傾聴を十分に行う事ができないことへのジレンマを感じる
□ 活動を公表できないこと、活動への承認が弱いことにより、組織に対する怒りや不信感を持つ
□ 隔離により孤立・孤独感を持つ
□ 周りからの視線に過敏になる
□ 自分も感染している/したのではないかという恐怖心・不安がある
□ 周りの人には気持ちが分かってもらえない、と感じる
引用:日本赤十字社|COVID-19対応者のためのストレスチェックリスト より
ただし、このチェックリストはあくまで目安であり、診断や判定をおこなうものではありません。心配事があるときは、「ひとりで抱え込まずに相談する」で紹介している窓口への相談をおすすめします。
3.心の負担を軽減するためにできること
・こころの健康維持に必要な4要素を意識する
ストレスと上手に付き合いながら心の健康を維持するためには、周囲のサポートやセルフケアなど、次の4つの要素が重要です。
| 職務遂行基盤 |
| 個人がスキルや知識を持って、身の安全の確保や環境を整備すること |
| 個人のセルフケア |
| 自分自身でストレスをマネジメントすること |
| 家族や同僚からのサポート |
| メンタルヘルスに対して、家族や同僚からのサポートを受けること |
| 組織からのサポート |
| メンタルヘルスに対して、組織からのサポートを受けること |
参考:日本赤十字社|新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対応する職員のためのサポートガイド より
これらの4つの要素は、コロナに対応する医療・福祉職本人だけでなく、同僚・家族・知人・上司・施設管理者にも求められます。コロナに対応する医療・福祉職が抱えるストレスに周りが気付き、改善していくことも大切です。
日本赤十字社が発表している新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対応する職員のためのサポートガイドでは、同僚・家族・知人・上司・施設管理者それぞれの立場からできることを紹介しています。自身の立場に当てはめて「自分のためにできること」「周りのためにできること」を確認してみてください。
心の健康を維持するためには、セルフケアと周囲からのサポートのバランスが大切です。しっかりとしたセルフケアという土台の上に、周りからの理解やサポートを積み重ねましょう。
・実体験を参考にする ─コロナ禍で働く人の声─
なるほどジョブメドレーがおこなった「コロナ禍による仕事の変化」のインタビューでは、ストレスとの付き合い方について次のような声がありました。
──現場で働くスタッフもコロナ禍でストレスを抱えているかと思いますが、どうでしょう?
ストレスはみんな溜まってきてるなーって感じますね。
(中略)
やっぱり僕らの仕事はチームで動くことがほとんどなので、少しでもそういう歯車がずれると職場の空気はすごく悪くなりますし、業務にも影響が出てきますね。
──コロナ禍ではスタッフのマネジメントも重要になってきますね。
なので、できるだけ感染対策に気をつけつつ個別でご飯に行ったりして業務外でも関わりを持つようにしています。そうすると結構本音を喋ってくれるので。
作業療法士のIさんの場合、コロナ対応のストレスによりチーム全体の空気が悪くなったことを受け、マネジメントの立場からスタッフと個別に関わりを持つことで本音を聞き出していたようです。
チームで働くことが多い医療・福祉職では、困っていること・ストレスに感じていることを相談できる場を作ることも重要です。
自粛生活でストレスが溜まっちゃったり、利用者が少なくて暇だったりで、ある店舗のバイトスタッフたちがすごく荒れちゃってたんですよね。
(中略)
──売り上げ以外にも問題が出てきたんですね。
なので、その店舗のバイトの子一人ひとりと面談して「何がやりたくて入ってきたのか」「どんな仕事が好きなのか」などヒアリングして。
(中略)
あとは、しつこいくらいコミュニケーションを取ってましたね。
それこそ一人ひとりに毎日電話して「調子どう?」とか「みんなが頑張ってるのを会議で報告したいから、今週の新規獲得数を教えて」とか。
とにかく「みんなの頑張りを見てるよ」ってことが伝わるようにしました。
スポーツインストラクターのHさんは、コロナ禍のストレスからアルバイトスタッフが荒れてしまったことを受け、一人ひとりとしっかりコミュニケーションをとることで、不安や不満の原因を聞き出していたようです。
──コロナ禍のなかで出産を控え、ご自身はどんな対策をしていましたか?
妊娠がわかってからは友だちにも会わず、電車にも乗らず……、できる限りの感染対策はしていました。
(中略)
「怖がりすぎず、でも感染はしないように」って感じですかね。
──「怖がりすぎず」っていうのが難しいですよね。神経質になりすぎてもストレスが溜まりますし……。ストレスを溜めないように気をつけていたことはありますか?
早寝早起き、バランスよく栄養を摂ることも大切なんですが、心が元気でなくてはいけないので、よく笑うようにしたり。
(中略)
主人とぶつかることもありました。少しでも気分転換になるように、夜中とか人の少ない時間帯に2人で近くを散歩したりしてましたね。
児童指導員のSさんはコロナ禍での出産を経験。神経質になりすぎてストレスを溜めないよう、笑うことを心がけ、散歩をしてリフレッシュしていたようです。
こうした心がけや気分転換を個人で意識することは、ストレスのセルフケアにも繋がるでしょう。自分なりのストレス解消法を見つけておくと安心です。
・ひとりで抱え込まずに相談する
ストレスをマネジメントするには周りの協力も不可欠であり、なかなか思うようにいかないこともあるかもしれません。
困ったことや悩みが解消しない場合はひとりで抱えこまず、相談窓口を活用しましょう。
お住まいの自治体へ相談したいとき
4.周りとサポートしあいながら負担を軽減しましょう
人は身の危険を感じるような強いストレスにさらされたとき、落ち込んだりイライラしたりします。こうした反応は自然なことであり、決して悪いことではありません。大切なのはストレスと上手に付き合いながら対処していくことです。
自分がどんなことにストレスを感じているかに気付き、セルフケアと周りからのサポートをバランス良く取り入れ、正しい情報のもと不安や悩みを解消していきましょう。
また自分だけでなく、周りの人が抱えるストレスに気付くことも大切です。お互いに手を取り合いながら困難な状況を乗り越えていきましょう。
「コロナ禍での変化インタビュー」まとめ
- 【コロナ禍インタビュー】幼稚園教諭 31歳 女性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】薬剤師 35歳 女性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】歯科衛生士 33歳 女性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】児童指導員 31歳 女性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】柔道整復師 31歳 男性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】看護師 32歳 男性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】美容師 28歳 男性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】エステティシャン 39歳 女性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】生活支援員 30歳 男性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】スポーツインストラクター 31歳 男性の場合
- 【コロナ禍インタビュー】作業療法士 34歳 男性の場合