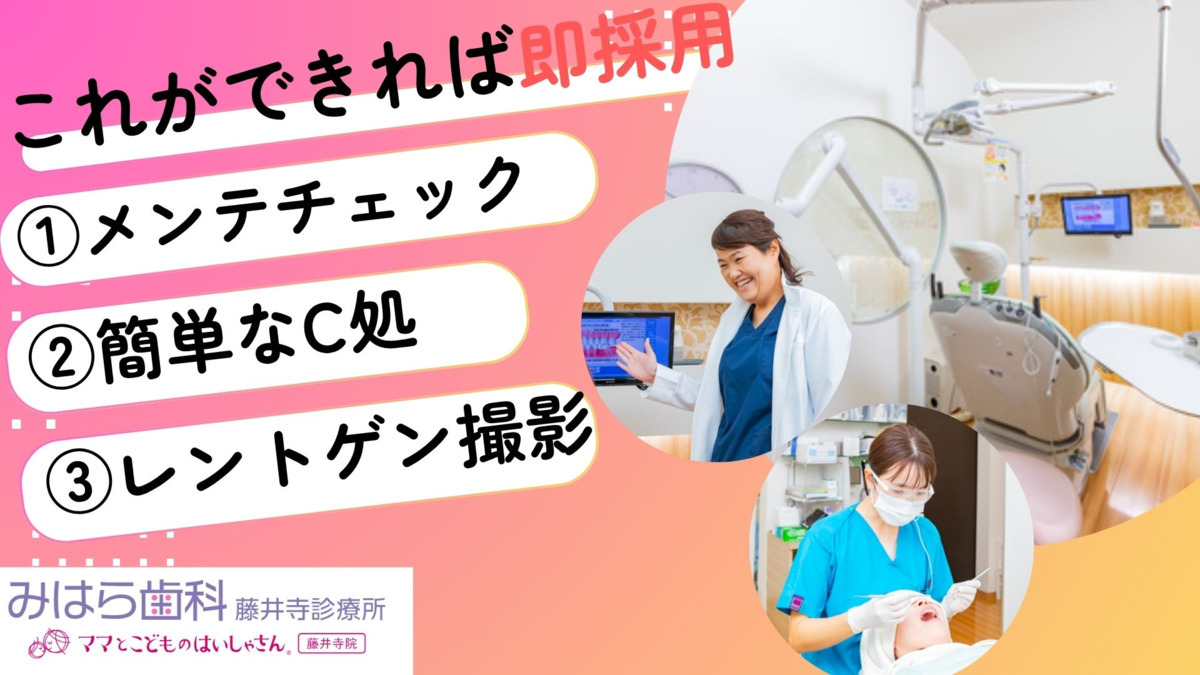目次
- 1.高齢者虐待防止法とは?
- 高齢者の安全や権利、利益を守るための法律
- 増加する高齢者虐待件数
- 2.高齢者虐待と定義されている5種類
- 1.身体的虐待
- 2.介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
- 3.心理的虐待
- 4.性的虐待
- 5.経済的虐待
- 身体的虐待の割合が大きい
- 3.通報の流れと通報先
- 通報の流れ
- 通報した内容や個人情報は保護規定で守られる
- 調査拒否や虚偽の答弁は罰則対象
- 4.医療・福祉従事者の責務と対応方法
- 早期発見の努力義務がある
- 虐待を発見した場合の対応方法
- 未然に防ぐための対策
- 5.高齢者虐待防止にかかわる主な職種
- 介護サービス従事者
- 医療機関従事者
- 公的・民間機関従事者
- 6.高齢者や養護者を孤立させない
1.高齢者虐待防止法とは?
高齢者の安全や権利、利益を守るための法律
高齢者虐待防止法とは、高齢者に対する虐待を防ぎ、保護するための措置や支援について定めた法律です。2005年に制定され、正式には「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。
主に、高齢者虐待防止に関する国の責務や養護者への支援、医療・福祉従事者の早期発見の努力義務などがあります。
法律では65歳以上の人を高齢者と定めており、高齢者虐待を「養護者によるもの」と「養介護施設従事者によるもの」に分けて定義しています。
養護者とは高齢者を介護・世話をする立場にある家族や親族を指し、養介護施設従事者は、以下の施設や事業に従事する人と定められています。
| 養介護施設 | 養介護事業 | |
|---|---|---|
| 老人福祉法による規定 | ・老人福祉施設 ・有料老人ホーム | ・老人居宅生活支援事業 |
| 介護保険法による規定 | ・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・介護療養型医療施設 ・地域密着型介護老人福祉施設 ・地域包括支援センター | ・居宅サービス事業 ・地域密着型サービス事業 ・居宅介護支援事業 ・介護予防サービス事業 ・地域密着型介護予防サービス事業 ・介護予防支援事業 |
なお、上記に該当しない施設における虐待についても、高齢者を現に養護する者による虐待と考えられる場合は「養護者による高齢者虐待」として対応していくことが求められています。
増加する高齢者虐待件数
法律制定の背景の一つとして、高齢者虐待件数の増加があります。
厚生労働省がおこなった調査によると、養介護施設従事者による虐待と判断された件数は増加しており、養護者(世話をしている家族、親族、同居人など)による件数はほぼ横ばい状態となっています。
2.高齢者虐待と定義されている5種類
法律では、高齢者虐待を以下の5つに分類しています。
1.身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えることや、外部との接触を意図的に断つことなどを指します。
身体的虐待の例
- 殴る、蹴る、やけどを負わせる
- 無理やり口に食事を入れる
- 身体的拘束*や抑制をする
2.介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ることを指します。意図的か結果的かは問わず、高齢者の生活環境や身体・精神的な状態を悪化させる行為が該当します。
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)の例
- 入浴させず異臭がする
- 水分や食事を提供せず、脱水症状や栄養失調が見られる
- ごみが放置されたままなど、劣悪な住環境
3.心理的虐待
暴言を吐いたり著しく拒絶的な対応をしたりすることで、高齢者に心理的外傷を与える言動を指します。
心理的虐待の例
- 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
- 高齢者を無視する
- 排泄の失敗を叱責、嘲笑するなど高齢者に恥をかかせる
4.性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、または高齢者にわいせつな行為をさせることを指します。
性的虐待の例
- 性的行為の強要
- 排泄の失敗に対し、懲罰的に衣服を着用させずに放置する
- 身体への不必要な接触
5.経済的虐待
養護者や親族が高齢者の財産を不当に処分したり、高齢者から不当に財産上の利益を得たりすることを指します。
経済的虐待の例
- 生活費を渡さない
- 自宅や車を勝手に売却する
- 年金や貯金を高齢者の意思・利益に反して使用する
また、高齢者虐待は状況の深刻度によって「緊急事態」「要介入」「要見守り・支援」の3つのレベルに分かれます。
| 緊急事態 | 生命に関わるような重大な状況で、一刻も早い介入が必要 |
|---|---|
| 要介入 | 放っておくと心身の状況に重大な影響を生じる可能性がある状態。当事者の自覚の有無にかかわらず、専門職による介入が必要 |
| 要見守り・支援 | 心身への影響は部分的または顕在化していない状態。介護の知識不足や負担などにより不適切なケアになっていたり、長年の生活習慣の中で生じた言動が虐待につながったりする可能性がある場合など |
身体的虐待の割合が大きい
厚生労働省の調べによると、養護者・養介護施設従事者による虐待ともにもっとも大きい割合を占めていたのは「身体的虐待」という結果でした。
3.通報の流れと通報先
通報の流れ
高齢者虐待を発見した場合、すみやかに通報することが求められています。もし、職場や地域などで虐待を発見、または可能性を疑ったら市区町村の担当窓口へ通報しましょう。通報の流れは次のとおりです。

まず、被虐待者本人または発見者が、市区町村の高齢者虐待対応所管課や地域包括支援センターなどへ相談・通報をします。次に、相談・通報先が虐待の可能性について協議し、事実確認をおこなうために情報収集をします。情報をもとに、施設や居宅などを訪問するほか、関係する人物からの情報を集めます。その後、情報の整理や虐待有無・緊急性の判断、対応方針の決定がなされ、ケースごとの対応をおこなう流れです。
高齢者への虐待および保護、養護者への支援において、法律では市区町村が果たす役割を以下のように規定しています。

とくに高齢者虐待防止法において、養護者への支援が明記されている点は特徴的です。虐待発生の背景には、身体的、精神的、社会的、経済的な要因が複雑に絡み合って存在しています。
厚生労働省がおこなった高齢者虐待の発生要因に関する調査によると、「虐待者の介護疲れ・介護ストレス(27.4%)」「虐待者の障害・疾病(21.3%)」「経済的困窮(14.8%)」の順に多いという結果でした。
高齢者だけでなく養護者が抱える問題を把握し、必要に応じて適切な支援につなげることで虐待のリスクを減らすことができます。
養護者支援として高齢者虐待防止法第14条に、「ショートステイ居室の確保」があります。ショートステイは養護者が一時的に介護から離れ、リフレッシュしてもらうための「レスパイトケア」のために利用されます。
>ショートステイについて詳しくはこちら
ショートステイとは?仕事内容、給与、施設の種類・特徴、利用状況などをまとめました
ほかにも、高齢者虐待防止法第9条では、都道府県や市区町村が高齢者本人や養護者に代わり成年後見開始を申し立てることができるとされています。後見人を立てることで本人の代わりに、財産管理や介護サービスの利用・契約などを実施できるようになります。
>成年後見制度について詳しくはこちら
成年後見制度とは? なれる人や気をつけることをわかりやすく解説!
通報した内容や個人情報は保護規定で守られる
法律には、虐待の早期発見・対応を図るために「通報等をしたことを理由に解雇その他不利益な取り扱いを受けない(虚偽・過失による通報を除く)」という保護規定があります。また、通報や届出を受けた市区町村や地域包括支援センターの職員にも、守秘義務が課されているため、通報者に関する情報が漏えいすることはありません。
調査拒否や虚偽の答弁は罰則対象
高齢者の虐待に対応する養介護施設従事者などの協力者、市区町村の関係者が職務上知り得た情報を漏えいした場合は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が課されます。
また、虐待の事実確認のための立入調査を拒んだり、虚偽の発言をする・させる行為も30万円以下の罰金が課されることとなっています。
4.医療・福祉従事者の責務と対応方法
早期発見の努力義務がある
高齢者虐待防止法第5条では、医療・福祉従事者が高齢者虐待の早期発見に努めることが求められています。
養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。
2021年に厚生労働省がおこなった調査によると、養護者による虐待に関する相談・通報者でもっとも多いのは警察32.7%、養介護施設従事者による虐待の場合は施設職員が最多の29.8%という結果でした。
虐待を発見した場合の対応方法
もし高齢者の虐待を発見、または可能性を疑った場合は先に紹介したように、まずは市区町村の高齢者虐待対応窓口や地域包括支援センターへ相談しましょう。
虐待をしている養護者や虐待を受けている高齢者自身が虐待の事実を否定したり、介入を拒むケースもあります。当時者に虐待の意識がなかったとしても虐待と判断されるケースは十分あります。以下を参考に、該当する場合は相談や通報をしましょう。
虐待が疑われる主なサイン
- 高齢者の身体に傷やあざがある
- 家から怒鳴り声や悲鳴、うめき声、物を投げる音などが聞こえる
- 高齢者が家に帰りたがらなかったり、長時間外にいたりする
- 近隣とのつきあいがなく、訪問しても高齢者に会えない
- 光熱費や家賃の滞納が見られる
- 適切な診療や介護サービスを受けていない様子が見られる
未然に防ぐための対策
高齢者虐待の早期発見・対応と同様に大切なのが、虐待を未然に防ぐことです。以下に、虐待を防止するためのポイントを紹介します。
関係機関の連携
高齢者の虐待を防ぎ、万が一発生した場合もその後安心して暮らすためには、切れ目のない支援と対策が欠かせません。そのためには医療・介護・地域の関係機関が情報提供をし合うなどの連携が大切です。
また、虐待を発見した場合も一人の職員が対応するのではなく、組織的に対応するのが望ましいです。誰か一人に負担がかかるのを避けるほか、客観性を確保するためにも複数の職員で対応しましょう。
積極的なアプローチ
虐待を未然に防ぐための権利意識の啓発や介護や認知症に関する正しい知識を持つことも有効です。また、養護者の負担軽減を図るべく、介護保険制度の利用を促すなど積極的な取り組みが期待されます。
また、養護者自身が経済的、精神的な理由から支援を必要としているケースもあります。その場合には、家庭が抱える問題や状況を把握し、市区町村の福祉担当部署や社会福祉協議会などへの橋渡しが重要です。
6.高齢者や養護者を孤立させない
厚生労働省の推計では、65歳以上の高齢者数は2025年に3,657万人となり、その後も増加を続け2042年には3,878万人とピークに達する見込みです。人口の4割近くが高齢者となり、要介護者や認知症を患う高齢者も増え続けることが予想されます。
高齢者が安全に生活するために、切れ目のない支援や関係機関の連携が大切です。虐待を早期発見しやすい立場にある医療・福祉従事者は、高齢者や養護者が孤立しないための環境づくりを心がけ、高齢者や養護者に異変を感じたら早期に対応するようにしましょう。
参考
- e-gov|高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 厚生労働省|Ⅰ高齢者虐待防止の基本
介護事業所の管理者さまへ|ジョブメドレーアカデミーが高齢者虐待の早期発見に役立つ資料をご用意しました!
本資料では、虐待の「疑い」を見逃さないために介護職員が身につけるべき気づきの視点(サイン)や、対応のポイントをお伝えします。高齢者虐待の早期発見にお役立てください!
ジョブメドレーアカデミーとは?
介護現場で役立つ知識・スキルを効率的に学べるオンライン動画研修サービスです。高齢者虐待防止及び身体拘束等適正化をはじめとした各種法定研修に対応しています。
【詳細はこちら】ジョブメドレーアカデミー