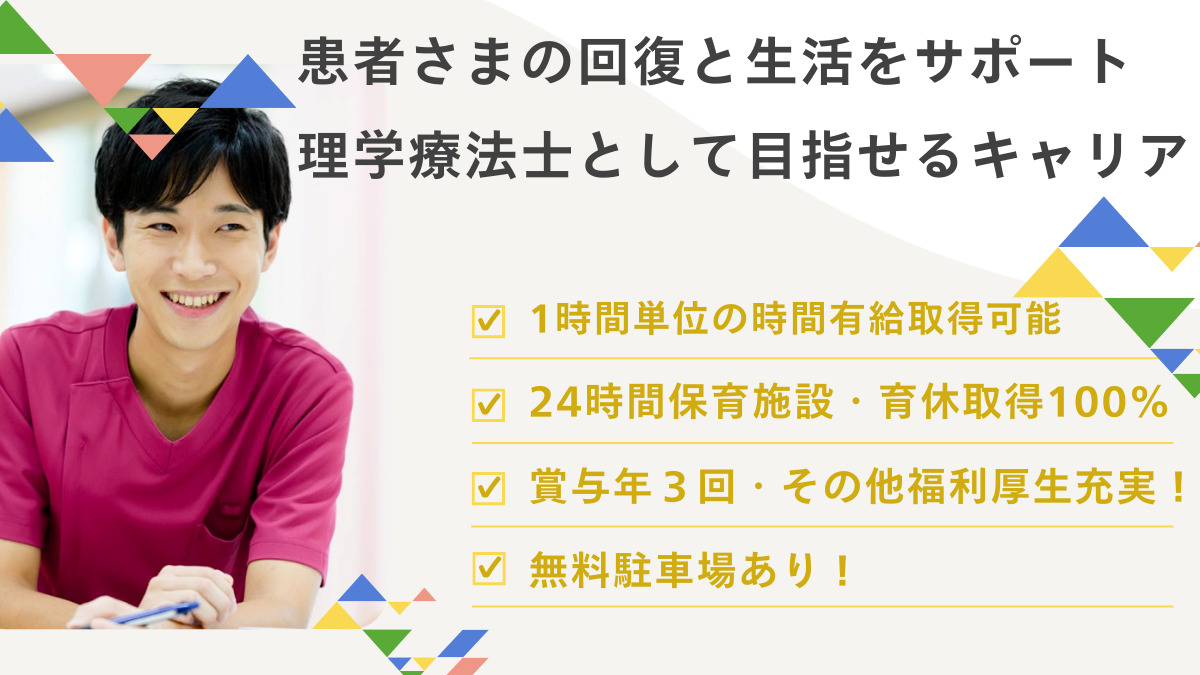目次
1.児童相談所とは
子どもの権利を守るための相談・援助をおこなう機関
児童相談所とは、児童福祉法に基づき各自治体に設置されている行政機関です。原則0〜17歳までの子どもに関する相談や通告を受け、適切な支援につなげることで子どもの権利を守ることを目的としています。
児童相談所は都道府県、指定都市に設置義務が課されており、全国に232ヶ所設置されています(2023年4月時点)。
児童相談所に寄せられる相談・通告のなかでも多くの割合を占めるのが「児童虐待」です。2021年度に児童相談所が虐待相談として対応した件数は20万7,659件と過去最多となっています。虐待のなかでも心理的虐待が全体の約60%と多く、次いで身体的虐待が約24%と続いています。
児童相談センター、青少年センターとの違い
児童相談所と似た機関に「児童相談センター」と「青少年相談センター」があります。
児童相談センターと児童相談所の主な違いは、機関の位置付けにあります。児童相談所が家庭内やその関係者などからの相談を一次的に受け付け支援をおこなうのに対し、児童相談センターは各児童相談所の後方支援をおこなう中央児童相談所としての役割があります。また、電話相談事業や児童相談所同士の連携をはかる場の設置もおこなっています。
青少年相談センターと児童相談所の主な違いは相談内容と対象年齢にあります。青少年相談センターは、青少年の社会参加を目的としており、おおむね15〜39歳の人を対象にひきこもりや不登校、家庭内暴力、家出などの悩みの相談に対応しています。一方、児童相談所は18歳未満を対象に青少年相談センターと同様の相談も扱うほか、子どもの育成や発達、里親に関する相談などより幅広い相談に応じています。
2.児童相談所の主な4つの機能
1.市区町村援助機能
市区町村からの子どもや家庭に関して寄せられた相談に対し、自治体間の連絡調整や情報提供、その他必要な支援をおこないます。
2.相談機能
子育てや子どもの健康、発達、非行などさまざまな悩みごとや通告に応じ、専門的な角度から調査、診断、判定をおこないます。問題を引き起こしている原因を分析したうえで、援助や治療につなげます。
3.一時保護機能
家庭環境や状況によって必要があれば、一時的に子どもを保護者から離し保護します。
4.措置機能
児童福祉司、児童委員が子どもや保護者を指導するほか、必要に応じて児童家庭支援センターなどの関係機関にも指導の依頼をします。子どもの観察が必要な場合には、児童福祉施設や養育家庭(養子縁組を目的とせず短期間子どもを預かり養育する里親)において一定期間入所させ、保護します。
上記4つ以外にも、知的障害を持つ子どもを対象とした療育手帳の交付や、ひきこもりなどの問題を抱える子どもと年齢の近いボランティアを「メンタルフレンド」として派遣する事業などもおこなっています。
3.相談できる内容
児童相談所で相談できる内容は主に次のとおりです。
| 相談区分 | 相談内容 | |
|---|---|---|
| 養護相談 | ・虐待 ・保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院などによる養育困難 ・迷子 ・里親、養育家庭の登録、委託などの相談 | |
| 保健相談 | ・乳児 ・早産児 ・虚弱児 ・児童の疾患 ・事故・ケガなど健康管理に関する相談 | |
| 障害相談 | 視聴覚障害相談 | ・弱視を含む盲 ・難聴を含むろうなど視聴覚障害を持つ子どもに関する相談 | 言語発達障害等相談 | ・口唇・舌・口蓋や脳機能などの障害により、話しことばを正確・明瞭に発音できない状態(構音障害) ・吃音 ・失語 ・言語発達遅滞がある子どもに関する相談 |
肢体不自由相談 | 肢体不自由、運動発達の遅れがある子どもに関する相談 | 重症心身障害相談 | 重度の知的障害と重度の肢体不自由がある子どもに関する相談 | 知的障害相談 | 知的障害がある子どもに関する相談 | ことばの遅れ相談(知的遅れ) | ことばの遅れを主訴とし、知的遅れによると思われる子どもに関する相談 | 発達障害相談 | ・自閉症 ・アスペルガー症候群 ・その他の広汎性発達障害 ・注意欠陥多動性障害 ・学習障害 などがある子どもに関する相談 |
| 非行相談 | ぐ犯行為等相談 | ・虚言癖、金銭持ち出し、浪費癖、家出、浮浪、暴力、性的逸脱などのぐ犯行為*や問題行動のある子ども ・警察署からぐ犯少年として通告のあった子どもに関する相談 | 触法行為等相談 | ・14歳未満で刑罰法令に触れる行為があったとして警察署から児童福祉法第25条による通告のあった子ども ・罪を犯し家庭裁判所から送致のあった14歳〜20歳までの子どもに関する相談 |
| 育成相談 | 不登校相談 | 学校、幼稚園、保育所に登校(園)できない、していない状態にある子どもに関する相談 | 性格行動相談 | ・友達と遊べない ・落ち着きがない ・内気 ・日々の生活でしゃべらない ・家庭内暴力 ・生活習慣の著しい逸脱など性格または行動上の問題がある子どもに関する相談 |
しつけ相談 | 家庭内における幼児のしつけ、遊びなどに関する相談 | 適性相談 | ・学業不振・進学・就職など進路選択に関する相談 | ことばの遅れ相談 (家庭環境) | ことばの遅れを主訴とする相談で、家庭環境など言語環境の不備によると思われる児童に関する相談 |
| その他の相談 | 措置変更、在所期間延長に関する相談など | |
出典:厚生労働省|児童相談所の運営指針について:図表
*犯罪行為には至らないものの、将来的に罪を犯し刑罰法令に触れる可能性があること
4.相談・通報・一時保護の流れ

児童相談所ではさまざまな相談を受け付けているため、個々の状況に合わせた対応をおこなっています。まず、相談内容をもとに調査・一時保護・診断のいずれかをおこないます。続いて援助方針会議にてその後の支援方法を決め、指導や適切な支援につなげます。
児童相談所に相談するには、居住地の管轄児童相談所に直接行くか、電話で相談します。開所時間外の場合は、児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」でも相談を受け付けています。
すでに相談した人で緊急の場合や医療施設、学校などは、各都道府県に設置されている中央児童相談所に電話します。
>全国の児童相談所一覧はこちら
虐待に関する通告の場合は、原則すみやかに緊急受理会議を開いたのち、面談や家庭訪問の実施により子どもや保護者の状態を確認します。この時点で必要性があれば一時保護をおこなうか立入調査などを実施し、警察に援助を要請するなど法的手段に出る点が特徴です。
>児童虐待について詳しくはこちらをチェック
児童虐待防止法をわかりやすく解説! 医療・福祉従事者の責務とは
5.児童相談所で働く職種
児童相談所は人口によりA〜Cまで3つの区分に分類されており、必要となる職員数は規模別に異なります。
- A級……人口150万人以上の地方公共団体の中央児童相談所
- B級……人口150万人以下の地方公共団体の中央児童相談所
- C級……A級B級以外の児童相談所
それぞれの児童相談所で必要となる職種は以下のとおりです。
| A級 | B級 | C級 | |
|---|---|---|---|
| 教育・訓練・指導担当児童福祉司(ス-パ-バイザ-) | ● 児童福祉司おおむね5人につき1人 | ||
| 児童福祉司 | ● | ||
| 相談員 | ● | ||
| 児童心理司 | ● | ||
| 心理療法担当職員 | ● | ||
| 精神科医 | ● | ||
| 小児科医 | ● | ● | – |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | ● | – | – |
| 保健師 | ● | ● | – |
| 臨床検査技師 | ● | – | – |
| その他必要とする職員 | ● | ||
児童福祉司
児童相談所で働く児童福祉司は担当する地域内の子ども・保護者からの相談に応じ、必要な調査や診断の実施や支援・指導・関係機関との調整などをおこないます。
また、相談援助業務において10年程度の実務経験があると、児童福祉司およびその他相談担当職員のスキル向上を目的として教育や訓練にあたる「教育・訓練・指導担当児童福祉司(ス-パ-バイザ-)」として働くことも可能です。
相談員
相談の受付や面接、援助、受理会議などに関する業務をおこなう「受付相談員」と、子どもの福祉に関する相談に応じ、調査・診断、指導をおこなう「相談員」、電話で相談に応じる「電話相談員」がいます。
相談員、児童福祉司ともに地方公務員試験に合格し、児童相談所に配属、任用される必要があります。いずれも子どもや保護者の調査・診断を実施し、必要な支援・指導をおこないますが、児童福祉司は親子間の関係調整をおこなうなど業務範囲が異なります。
医師
いずれの児童相談所にも精神科医師の配置が義務付けられており、A級とB級には小児科医の配置も必要です。
医師は子どもや保護者に対して医学的検査の実施や診断、虐待が子どもの心身に及ぼした影響に関する判断などをおこないます。また、児童心理司や心理療法担当職員がおこなう心理療法への指導も主な業務です。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
A級の児童相談所では身体機能の回復のためのリハビリをおこなう理学療法士、日常生活で必要となる動作の改善をおこなう作業療法士、聴覚や発語に関するリハビリを実施する言語聴覚士の配置も義務付けられています。
それぞれの職種について詳しくはこちら
理学療法士/作業療法士/言語聴覚士
保健師
保健指導や衛生管理などの専門家である保健師は、相談に来た子どものアセスメントやケアの実施、市区町村や医療機関など関係機関への情報提供、連絡調整などをおこないます。また、一時保護している子どもの健康管理も保健師の役割です。
臨床検査技師
病気の診断や治療、健康の維持のために必要な検査をおこなう臨床検査技師。児童相談所では主に脳波測定などの検査を実施します。
臨床検査技師について詳しくはこちら
臨床検査技師の求人をチェックする
6.体制強化と関係機関の連携が大切
子どもの権利を守るための相談・援助をおこなう児童相談所。子どもの養育に関する不安や虐待、健康など相談内容は多岐にわたります。
なかでも、児童虐待に関する相談・対応件数の増加は喫緊の課題です。2022年に決定された「児童虐待防止対策の更なる推進について」では、児童相談所および市区町村の体制強化が打ち出されており、児童福祉司と児童心理司の増員などが盛り込まれています。
子どもが心身ともに健やかで安全に暮らしを送るために、児童相談所の人員体制の充実や迅速な対応、関係機関との連携が期待されています。
参考
厚生労働省|児童相談所運営指針